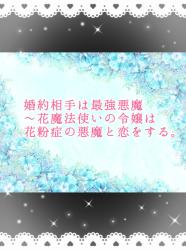今日は天気がよくて、春の匂いもした。
外を歩くと気持ちがいい。
歩いていると突然、高瀬が空に向かって左手を伸ばした。
僕の視線は高瀬の左手を追う。
僕たちは、はっとした。
高瀬の左手の指周りが……。
「今、何となく光を当ててみただけなのに……はっきり見えるんだけど」
「ね、見えるね。色の名前は詳しく分からないけど、緑系だね」
「赤井は……赤井の色はどうなの?」
高瀬は手を下ろし、ちょっと不安そうな表情をしながら僕を見つめてきた。
僕はもう自分の色を知っている。赤っぽいようなピンクっぽいような色が見えた。高瀬が運命の相手だったらいいなと願いながら、僕の色の補色になる可能性がある色をひっそり全部調べていた。
そして今、高瀬の色を知った。
気持ちが高ぶりすぎて――。
「高瀬、手、繋いでいい?」
「う、うん」
普段なら自分から手を繋ごうなんて、絶対に言えない。だけど今は――。
僕の右手と高瀬の左手。繋いだ手を空にある太陽の光に繋げようとした。
「いや、前に反応何もなかったのがトラウマで……」
ぐっと手に力を入れ、頑なに手を上げるのを拒否する高瀬。
僕は、答えを知っているから――。
無理やり僕たちの手を上げ、光に当てた。明るい光が僕たちの手を包んだ。
「僕たちの手の周りが……こんな風に輝くんだ……」
「すごいなこれ」
輝きながら繋がっている手をしばらくふたりで見つめていた。しばらくすると「そろそろ手が疲れてきた」と高瀬は言った。
手を下ろしても、ずっと高瀬と繋がっていたかった。
「僕、この手を離したくない」
「俺も。この手、一生離せないかも」
「いや、それは困るかも……」
手を繋ぎながらふたりで笑った。
光に照らされた温かい雪が降ってきて、僕たちを祝福してくれたみたいだった。
外を歩くと気持ちがいい。
歩いていると突然、高瀬が空に向かって左手を伸ばした。
僕の視線は高瀬の左手を追う。
僕たちは、はっとした。
高瀬の左手の指周りが……。
「今、何となく光を当ててみただけなのに……はっきり見えるんだけど」
「ね、見えるね。色の名前は詳しく分からないけど、緑系だね」
「赤井は……赤井の色はどうなの?」
高瀬は手を下ろし、ちょっと不安そうな表情をしながら僕を見つめてきた。
僕はもう自分の色を知っている。赤っぽいようなピンクっぽいような色が見えた。高瀬が運命の相手だったらいいなと願いながら、僕の色の補色になる可能性がある色をひっそり全部調べていた。
そして今、高瀬の色を知った。
気持ちが高ぶりすぎて――。
「高瀬、手、繋いでいい?」
「う、うん」
普段なら自分から手を繋ごうなんて、絶対に言えない。だけど今は――。
僕の右手と高瀬の左手。繋いだ手を空にある太陽の光に繋げようとした。
「いや、前に反応何もなかったのがトラウマで……」
ぐっと手に力を入れ、頑なに手を上げるのを拒否する高瀬。
僕は、答えを知っているから――。
無理やり僕たちの手を上げ、光に当てた。明るい光が僕たちの手を包んだ。
「僕たちの手の周りが……こんな風に輝くんだ……」
「すごいなこれ」
輝きながら繋がっている手をしばらくふたりで見つめていた。しばらくすると「そろそろ手が疲れてきた」と高瀬は言った。
手を下ろしても、ずっと高瀬と繋がっていたかった。
「僕、この手を離したくない」
「俺も。この手、一生離せないかも」
「いや、それは困るかも……」
手を繋ぎながらふたりで笑った。
光に照らされた温かい雪が降ってきて、僕たちを祝福してくれたみたいだった。