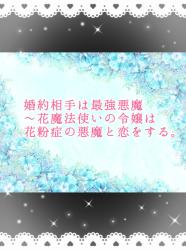***オルタンシア視点・プロローグ
大切な人が必ず不幸な死を遂げる。
あらかじめ分かっているのに、何もできないのは己の死よりも恐ろしい。
何度も繰り返されるのならば、大切な人の運命を変えるしか逃れる方法はない――。
ならば、大切な人の近くにいよう。
誰よりもそばに。
三回目の人生、ソナタを守る――。
*
***マーガレット視点
朝から晩まで、ネロカイア国の第三皇子の元で今日も忙しなく働いている。
私はメイドの新人下っ端だから、朝一番の仕事は、先輩たちが嫌がる、庭掃除の担当だった。今も早朝から庭掃除をしていた。
何故庭掃除が嫌われているかというと――。
枯葉を集め終えた瞬間、赤いドラゴンが飛んできた。ドラゴンの風圧で集めた枯葉が再び散らかる。
――またか。
「おい、お前、いつから枯葉を集めている?」
「はい、一時間ほど前から枯葉を集めております」
「それなのに、まだ全然集まってないのか?」
だって、それはさっきから皇子のドラゴンが散らかしてくるから……なんて言えるわけがないから言葉を心の底まで飲み込んだ。ブトン第三皇子は私よりもみっつ年上の二十歳。だけど同じ歳とは思えないほど言動が幼い。
「申し訳ございません」
深々とお辞儀をすると、鼻で笑いながら満足そうに去っていった。
――嫌がらせをすることでしか満足出来ないのかしら。
少し可哀想だなと感じながらそっと深いため息をつき、再び枯葉をほうきで集める。
すると今度は少女がやってきて 「お姉さん、今日はどんなお話を聞かせてくださるの? あ、そうそう召喚魔法って知ってる?」と、その子が可愛い声で聞いてきた。
この子の名はローズ。最近、庭で掃き掃除をしている時によく話しかけてくる。ふわふわで綺麗な金色の長い髪の毛がとても似合う五歳くらいの女の子。高級そうなワンピースドレスを常に着ているから、おそらく位は高い子なのだと思う。私はまだここには来たばかりで話せる相手は数少ないから、彼女と話すと気持ちが癒される。
「そうね……今日は、これからローズ様も関わることになる召喚獣についてのおはなしをしようかしらね」
「召喚獣って、未来の護衛のことよね?」
「えぇ、そうです。もう少し大きくなったら、ローズ様も召喚魔法を修得し、召喚獣と共に人生を歩まれることになると思います」
「お姉さん、私、詳しく教えてほしいわ!」
私は集まった庭の枯葉をホウキでまとめると、手を休めた。そして近くにある白いベンチの上に私のハンカチを置くと、そこに座っていただいた。
「かつて召喚獣は、戦争の道具として利用されていたのです。人対人の……一切争いには関係のない召喚獣達が戦争に巻き込まれておりました。やがて召喚獣の存在意義は変化していき、争いのない現在の我が国では、人の護衛としての役割を担うために存在しているのです。性格も凶暴だった召喚獣たちは、暮らしに合わせて穏やかになっていきました」
女の子は、手を組みながら真剣に話を聞いている。
「戦いに巻き込まれた召喚獣たちは人間と一緒にいて、嫌ではなかったのかしら」
「召喚獣にも心はあります。なので人間との性格の相性だってあります。あんまり大きな声では言えないけれど、嫌だと思う召喚獣も多くいたでしょう。今も、一緒になった人間が実は苦手と思う召喚獣もいるでしょうね……」
ちらっと私はブトン皇子が歩いていった方向を向いた。
少し経つと「あっ、呼ばれた。帰らなきゃ! お姉さん、またね」と、ローズ様は立ち上がった。
私には何も聞こえなかったけれど……ローズ様は耳がとても良いのかしら。
「えぇ、またいつでもお話しに来てください」
彼女の後ろ姿を消えるまで見送ると、掃き掃除を再開させた。再開させ少し経った時、枯葉が空に向かって渦巻き状に舞い、粉々になりながら、消えた。ただ呆然としながら空まで進んでいる枯葉を眺める。
集まったり散らかったり、そして今は粉々になり消えた。今日の枯葉は私よりも忙しそうね。
じっと枯葉の最期を見守っていると視線を感じ、後ろを向くと高身長で顔の整った、黒いローブを着ている男が魔法を使っていた。
「召喚獣に詳しいんだな? 召喚魔法を修得したいのか?」
視線が合うとその男は話しかけてきた。
「いいえ、修得したいだなんて、別に……それに、もしも召喚したいと思っていても、私は身分の低い女。なので全く無縁のお話ですから」
そう、私は召喚獣とは無縁だ――。
私は身分の高い公爵家で育った。両親共に当たり前のように護衛としての召喚獣が近くにいる日々を送っていたから、私も成人した日には魔法石を与えられ、召喚獣と一緒にいられる日々が来る。と、待ち遠しかった。
けれど アルトリア家は没落した。両親が優しい性格すぎたから、悪意ある者たちに利用され財産を隅々まで奪われた。そして代々築きあげられてきた我が家は没落した。両親共にストレスで身体が弱まり、私は家族の生活費を稼ぐために、今ここで今働いている。
もうすぐ私は成人を迎える。その時に魔法石を与えられるはずだった。
召喚獣の話なんて、メイドとして働く下流階級となった今の私には全く関係ないのだけど……。召喚獣を護衛として利用できるのは、召喚するための魔法石を配られる上流階級の人達だけなのだから。
だけど、召喚獣をお飾りのように扱う令嬢や、さっきの皇子みたいに遊びの道具として扱う人々を見ると、嫌気と嫉妬のような変な気持ちが込み上げてくる。
その男は、すっと私の右手を掴み、手のひらを上に向けさせた。すると手のひらに何かを乗せる。
「もしも召喚魔法を使いたい願望が少しでもあるのなら、夜中零時にあの木の下で会おう。召喚魔法を教える」
「私に、召喚魔法を?」
「そうだ」
男の人と話していると、先輩メイドふたりの視線が突き刺さってきた。先輩たちが早歩きでこっちに向かって来た。さぼっていたから怒られる。
「あの、私、掃除をしないと」
「あぁ、邪魔して悪かったな」
「いいえ……あの、お名前は?」
「自分の名はオルタンシアだ」
「私の名は、マーガレットです」
名前を伝えると彼は微笑みながら「知ってた」 と呟いた。
私の名前を、知っていた?
「じゃあ、待ってるからな」
オルタンシア様は去っていった。
「ちょっと、どういうことよ?」
「あのお方って、あの、優秀な召喚魔法使いのオルタンシア様よね?」
私たちの様子を眺めていた先輩メイドたち、ふたりがモンスターのような形相で攻めてきた。
「あ、あの、あの方は有名な方なんですか?」
「何よ、あんたもしかして知らないの?」
「はい、何度かお見かけはしていたのですが……」
「オルタンシア様は、召喚魔法修得の講師もしていて、ここ、王家でも教育なさっているのよ。あの整った容姿端麗なお姿は令嬢たちにもとても人気があるらしくて、引っ張りだこらしいわよ」
「年齢は、私と同じくらいで、二十五辺りかしら。恋人はいないって噂よ」
恋人がいない……あんなに格好がよいのに、意外。
先輩が思い切り私を睨む。
「何故あなた方が話をしていたのかわからないけれど、身分が全く違うのだから気安く話さない方がいいわよ。だって、あの方は国の四大名家のひとつ、 ヴァロイア家の跡継ぎの噂もあり、頭脳明晰で国の未来の頭脳部分も担うとも言われているとても高貴なお方よ」
「……」
そんなに身分の高い人だったの?
そんな彼がメイドなんかの私の名前をしっていて、何故、私に魔法を教えると言っていたの?
疑問しか浮かび上がらない。
今日の夜中、どうしたらいいのかしら。
夜、約束の時間が過ぎる。
今の私に召喚魔法なんて教えてもらう資格はないわ。
私がもしもいかなくても、彼は待っているのかしら?
ずっと彼のことを考えていると目が冴えて眠れない。
結局、白い薄手のナイトウェアの上に一枚ピンク色のものを羽織ると、同じ部屋で眠っている他のメイド三人を起こさないようにそっと静かに、メイドの寮の裏口から外へ出た。
月明かりで外は明るい。
一枚羽織っては来たけれど、ちょっと寒い。はぁっと白い息で私は手を温めながら進む。
約束の場所には、小さな池がある。そこはちょうど、夜中眠れない時にたまに行く場所。その時は池の中で揺れている月の明かりを眠くなるまで眺めていた。人もめったに通らないし、結構お気に入りの場所だった。
着くとオルタンシア様は……まだいた。
「来てくれたんだ?」
オルタンシア様は月よりも輝いているように見え、まるで暗闇の世界を明るく照らしているようだった。
「来てしまいました。教えてもらえる身分ではないのに」
「いや、そんなことはない。だって、自分たちは深い繋がりがあるのだから……」
「深い繋がり……ですか?」
こくんとオルタンシア様は頷いた。
初対面のはずなのに、深い繋がりとは?
「では今日は、さっき少女に伝えていた内容と重複するが、召喚獣について伝える」
聞こうか迷っていた矢先、本題に入った。
「今日ということは、また次も、ですか?」
「あぁ、そうだ。魔法の基礎から実践まで教えなければ使えないからな」
またこうやって会えるのかな?
この状況に、胸が高まっていた。
彼と目が合うと何か熱いものが全身を巡る。それは召喚魔法を使えるからか、それとも――。
「まずは、基礎知識を――」
オルタンシア様は、昼間私が女の子に教えた、過去、そして今の召喚獣の話を簡潔におさらいとして、説明してくれた。
「それと、大切なのは人が召喚魔法を唱えた瞬間から召喚獣には、恐れや悲しみなどの感情が召喚魔法を唱える人間から伝わるということだ」
「それを踏まえて、できるだけ優しい気持ちでいるのが理想だということでしょうか?」
「そういうことだな。早速だが、召喚獣を操る練習をしよう。魔法石は持ってきているか?」
「はい、持ってきております」
私は丁寧にハンカチに包んだ魔法石を手のひらに乗せ、彼にみせた。
「この魔法石は生徒たちが最初の練習に使うものだ。中には、穏やかな性格のカーバンクルがいる。まずは、自分が手本をみせる」
オルタンシア様が魔石をみつめ、手をかざすと魔石が虹色に輝いた。
「カーバンクルルー」と高い声と共に姿を現した、小さな兎のような狐のような姿をしたその幻獣はふわっと私の手に着地した。
「綺麗な若草色ね……カーバンクル、久しぶりに見たわ」
頬に寄せようとするとカーバンクルは自ら頬を擦り寄せてきた。ふわふわな感触が気持ちいい。
「可愛い! 人懐っこい……」
「カーバンクルは警戒しないからな。次は、マーガレットの番だ」
オルタンシア様がそう言いながらカーバンクルに手をかざすと、カーバンクルは魔法石の中に吸い込まれていった。
「私にできるのかしら……」
「できる。が、しかし最初は上手くいかないかもしれない。出てきてほしいと強く願いを込めて魔法石に手をかざすんだ」
「はい、やってみます」
左手のひらにある魔法石の前に右手を当て、目を閉じ今見たばかりのカーバンクルの姿を頭の中に浮かばせて……。
――お願い、お外に出てきてください。
辺りはしんとなる。何も変化は起こらない。すると耳元で「大丈夫だから、信じて」と、オルタンシア様の囁く声がした。
両手が温かくなってくる。
そして――。
「カーバンクルルー」と、カーバンクルの声も聞こえてきたから目を開けた。
目の前には再びカーバンクルがいた。
「最初の難関、すぐにクリアしたな。生徒たちの中で練習なしですぐに使えるのはおよそ一割ぐらいだ」
初めて魔法を使った。
魔法が、使えた。
――憧れていたけれど、無縁だと思っていた召喚魔法を。
出てきてくれたカーバンクルを強く抱きしめた。
「ただ、今そなたが使った魔力は、教育用の魔力だ。講師の自分がいる時にしか使えない。常に召喚魔法を使える状態にするには、魔法事務局が運営する試験を受け、合格する必要がある」
「では、この子を召喚できるのは今限り……」
「そうだ。合格すると常に共に過ごすことになる相性の良い召喚獣の魔法石を、数ある中から選び、その魔法石と共鳴する魔力が授けられ、正式に使えるようになるのだ」
「でも、そもそも召喚魔法は上流階級の方々しか使えないのでは?」
「例外もある」
「例外?」
「そう、それは自分が推薦した者も試験を受ける資格が与えられる」
私も、もしかしたら正式に召喚魔法が?
ゼロだった可能性が一気に跳ね上がり、期待感が増してくる。本当は、召喚獣と共に過ごす人生に憧れていた。でもそれは、推薦してもらわないと何も始まらない。
「あの、推薦をお願いいたします」
私のような地位の者が、オルタンシア様のような位の方にお願いするなんて、とんでもないことだ。けれど私は、ついお願いの言葉を吐いてしまった。
「もちろん、推薦する」
「……ありがとうございます。あの、お聞きしたいことがあるのですが、何故オルタンシア様は、そんなに私に良くしてくださるのですか?」
「――それは……」
「そなたが幸せになれるための、力に少しでもなれたらいいと思ったからだよ」
オルタンシア様は私をみつめてそう言った。口角は上がっているものの、何故か目はとても切ないような、悲しみを帯びているように見える。
「あっ、むこうから人が来た」と、オルタンシア様が言うと、私を来た人たちから見えないように隠してくれた。オルタンシア様と距離が近すぎて心臓の音が早くなってくる。私は顔を上に向け、オルタンシア様に「あの、本当にまたこうやって、教えてくれますか?」と、問う。
「もちろんだ。今日は、初めての練習だから、魔力を多めに使えるようにした。本来、召喚魔法を使うための魔力は今日使った魔力の3分の1の量だ。ただ、魔力を少なくするとその分魔法を使う難易度が上がる。難易度は上がるが、慣れると簡単になる。練習して、魔力が少ない量でも簡単に使えるよう、まずは慣れよう」
「ありがとうございます」
「では、また明日。この時間、ここで待ってる」
「はい、ありがとうございます」
「マーガレット!」
オルタンシア様の元から去ろうとすると名前を呼ばれた。直接名前を呼ばれドキリと強い胸の音がなる。私は振り向く。
「部屋まで、送る」
「いえ、近いから大丈夫です。それに、ここは人が滅多に来なくて大丈夫だと思いますが、私の部屋に戻るために通る道は、人が通ると思います。私たちがこんな時間に一緒にいることがバレたらやっかい……」
「では、こうしよう」
オルタンシア様が一瞬輝く、そしていなくなった。
――オルタンシア様が、消えた?
「オルタンシア様?」
「ここだ」
今、オルタンシア様の小さな声が聞こえた。そして足元に小さな光が。
「オルタンシア様!」
なんと、オルタンシア様が小粒になっていた。私はしゃがむと、手のひらにオルタンシア様を乗せた。
「これなら周りにも見つからないし、自分は変わらず魔法が使えるからそなたを守ることができる」
オルタンシア様は、部屋の前まで来ると私の手から降りて、建物の陰に行き、周りに人がいないことを確認した。そしていつもの大きさに戻った。
「ではまた明日」
「はい。今日はありがとうございました」
私は離れていくオルタンシア様の背中を見守る。
もっと一緒にいたかったな。でもまた明日も会えるんだわ!
空を見上げると、いつもよりも明るく輝いている満月が笑っていた。
朝から夜まで休みなく働いて、夜中の少しの間オルタンシア様から召喚魔法を教えてもらう。そんな日々を送るようになった。
オルタンシア様はあちこち色々な国へ行っていたから会えない日もあったけれども、そんな時は「お土産だ」と、見たことのないクッキーや素敵なブレスレットもプレゼントしてくれた。
そんな日々を過ごしていたけれど、ある日リーダー格の先輩メイドに「あんた、何か隠し事してない?」と、第三皇子ブトンの部屋を掃除中、こっそりと問い詰められた。
「何のことでしょうか?」
「私、あなたが夜中抜けだしてること、知っていたのよ。そして先日、後をつけてみたの」
もしかして、バレた?
気持ちの良くない汗が全身から流れてきた。私は何も答えられずにいた。
「あなた、オルタンシア様と密会してるでしょ?」
「はい」と認めてしまえばどうなるか分からない。何かいいアイディアはないか、私は私の全細胞を使い考えた。
「甘いものは、お好きですか?」
答えとは全く関係のない質問を先輩に投げる。先輩は質問を受け取ってくれるのか、緊張しながら様子を伺った。
「好きよ。大好きよ!」
「あの、先輩。素敵なお菓子があるのですが……」
私はエプロンのポケットからお洒落な袋に包まれたクッキーを出す。あとでこっそり間食しようとしていたお菓子。もちろんオルタンシア様からいただいたもの。
「まぁ、こんな素敵なお菓子いただけるの? 初めて見たわ!」
「いつも先輩にはお世話になっていますので。折り入ってお願いがあるのですが……」
「何よ、言ってごらんなさいよ」
いつもよりも高く弾んだ声。あきらかに先輩のご機嫌は良い。それもそうだ。私たちメイドにとってクッキーは高級なものでなかなか食すことはできないのだから。
「お、美味しい……こんな美味しいもの初めて食べたわ」
先輩は目を丸くして驚いていた。
というかここで食べても良いのか? ここはブトン皇子の部屋なのに。それよりも、今なら私の願いを聞いてくれるかもしれない。
「夜中に先輩がご覧になられたことはご内密にしていただきたいのですが……」
「そんなこと? いいわよ! その代わり、またおすそ分けちょうだいよ」
「はい! ありがとうございます」
私は先輩に向かって、丁寧にお辞儀をした。
***
オルタンシア様から召喚魔法を教わり、半年経った。
「よし、完璧だな」
「ありがとうございます」
今では、少ない魔力でもカーバンクルを軽々出せるようになった。そしてカーバンクルの能力である、人を心身ともに元気にする力も指示すると使ってくれるようにもなった。ちなみにカーバンクルは攻撃系の召喚獣ではないから、護衛の召喚獣から除外されている。
「試験が合格したら、当日、相性の合う召喚獣が入った魔石を体内に取り込むことになるのでしたよね?」
「あぁ、そうだ」
「私、カーバンクルがいいな……」
練習で使っていくうちに、カーバンクルに対しての情が湧いてきていた。
「この子がいいのか?」
「……はい。というか、これはただのワガママですよね! 召喚魔法が使えるだけで贅沢なのに」
「そんなことはない。カーバンクルがいいのか……」
オルタンシア様は顎に手を当て考え事をしていた。
「今のお話、なかったことにしていいですから……では、試験の日は、採点よろしくお願いいたします」
***
そうして私はついに試験の日を迎えた。
当日の移動手段である馬車は、オルタンシア様が手配してくれた。普段乗っている馬車とは違い、全てが立派。長時間座っていてもお尻が痛くないふわふわな椅子。内装も私が好きな花柄模様の煌めくデザイン。だから馬車に乗った朝から気分が高まっている。
試験会場である滅多にお目にかかれない立派な神殿に着くと、中で受付をすませた。
オルタンシア様は、どちらにいらっしゃるのかしら。
長い廊下を進んでいくと、広場へ続く扉があり、そこは開いていた。中を覗くとオルタンシア様がいた。試験を受ける人たちがずらっと並んでいる。男性は高級そうなタキシード、女性は華やかなドレス。私も持っている中で一番華やかな、唯一のドレスを着てきたけれども、場違いかな?と思うほどに地味。
けれども今日はファッションショーではなくて、召喚魔法の試験日。気にしないでいこう。私は一番後ろに並んだ。
試験を受ける人は、二十人くらいか――。
黒いローブを纏い書類を持つ、比較的年齢が高めな審査員が男女五人並んでいた。オルタンシア様は胸に手をやり深呼吸している。
オルタンシア様、緊張しているのかしら?
見つめていると、オルタンシア様と目が合った。ふたり同時に、軽く会釈した。
「早速ですが試験を始めます。それでは一番の方、前へどうぞ」と、審査員の一番お年を召しているお婆さんの言葉を皮切りに、審査が始まった。
「それでは、試験用の魔力を本日試験を受けられる皆様に与えますので、この並べられた魔法石からお好きなものを選んで召喚獣を出し、命令をしてください」
一番目の受験者の、柔らかな雰囲気で同じくらいの歳に見える男の人が前に出た。同時に色や形が様々な魔法石が、長テーブルの上に10程並べられた。男の人は真ん中辺りの一番大きな赤い魔法石を手に取った。その男は魔法石を左の手のひらに乗せ、右手を魔法石にかざすと、その魔法石は輝き、赤い竜の召喚獣が出てきた。
召喚獣と共鳴すると、その召喚獣がどんな攻撃の技が使えるのか頭の中に浮かび上がるらしい。
「召喚獣よ、空に向かって火を吐くのだ」と、男が叫ぶと竜は空に向かって大きな火を吐いた。
――もしかして、全ての召喚獣がこんなに強そうなの? というか、私が選んだ魔法石からも召喚獣が出てきて、共鳴してくれるのかしら。
心配をよそに、試験は進んでいく。中には上手く共鳴できない人もいた。
そしてついに、私の番が来た。
緊張溢れて、心臓の音が早くなる。
無意識にオルタンシア様の方を向いたけれど、オルタンシア様はいなかった。
私の番なのに、どうして――?
お手洗いに行ったのかしら。オルタンシア様がいなくて少しだけ不安な気持ちが押し寄せてきた。
「20番目の方、お願いいたします」
きっと大丈夫、上手くいくわ!と自分に言い聞かせる。
審査員の声を合図に私は並んだ魔法石の前に立った。常に補充され、テーブルの上には、10種類の魔法石が置かれていた。
どれにしようか悩む。相性の良い魔法石はすぐに分かるらしいけれども、少しも分からない。と、思っていたら、突然ひとつの薄紫色の小さく丸みを帯びた魔法石が輝いているように見えた。それは多分、私だけだろう。
こういうふうになるの?
念の為に他の魔法石もひとつひとつ手をかざし確認してみたけれどぱっとするものはなかった。
――これだわ。
魔法石を左手のひらに乗せ、右手をかざすと、魔法石と私が共鳴したからなのか、輝きだした。そして何故か、オルタンシア様のお姿が頭の中で浮かび上がる。
何故召喚獣が思い浮かばないのかしら?
まさか、オルタンシア様を召喚するわけ……あった。
会場がざわめく。
私も思わず「何故?」と大きな声で叫んでしまった。
それは、魔法石から出てきたのはオルタンシア様だったから――。
「どうしてオルタンシア様が?」
「それは、マーガレットの召喚獣となるからだ」
「いや……でも……」
どうすればよいの?
オルタンシア様は堂々とそう主張なさっている。
私は他の審査員の方に視線を向けた。
ずっと全員がどよめいている。おそらく誰もそのオルタンシア様の、その話を聞いてはいなかったからだろう。
「で、では。全ての受験生の試験は終わりましたので、三十分後に結果発表を行います」
司会をしていたベテラン召喚士が驚きすぎたのか、口を開いたまま止まっていたので一番若い男の召喚士が代わりに進行をした。
他の生徒たちは試験会場から離れていく。オルタンシア様も審査員たちに呼ばれて、私から離れていった。私も時間が来るまで、外で散歩をすることにした。この流れの意味が理解できずに、待っている間、ずっと胸の奥がそわそわしていた。
そして結果発表の時間がついに来た。
「それでは、番号を呼ばれた者は前へ」
召喚魔法は使えたけれど、魔法石から出てきたのはなんとオルタンシア様で。
合格なのか、不合格なのか。全く予想ができない。
「1番、3番、6番……」
番号は想像よりも飛ばされている様子。より緊張は高まる。
「8番、11番、15番、16番……」
私は胸の辺りで手を組み、呼ばれますようにとお祈りをした。
「そして、20番」
――呼ばれた!
「はい!」と返事をすると、前に出た。
出たけれども、私の召喚獣となるオルタンシア様は審査員たちのところに並んでいた。
試験に合格すると、人間と召喚獣が一生一緒にいられるように、魔法石が体内に入り、心臓の一部となる。人間の心臓が動き続ける限り共に過ごす、運命共同体となる。すなわち、人間の死により、召喚獣は開放されるということ。
1番目の男の人の前に、この国で一番トップの召喚士が立った。召喚士は手に魔法石を持っていて、男の人の胸元に魔法石を当てると虹色に輝き、あっという間に男の人の胸の中に吸い込まれていった。そしてついに私の順番が来た。
「あの、私はどの召喚獣が?」
答えを求めていると、オルタンシア様が目の前に立つ。手には魔法石を持っている。
「自分でいいか?」
「いや、いいかと聞かれましても……」
動揺していると、オルタンシア様が私の胸の近くに魔法石をかざしてきた。
そして、その魔法石は虹色に輝き私の中へ。だけど、オルタンシア様は目の前で立ったまま。
……オルタンシア様はそのまま? だとしたら、今私の中に入っていった魔法石には何の召喚獣が入っているというの?
「オルタンシア様、私の召喚獣は――?」
「自分だ」
――本当に、オルタンシア様が私の召喚獣に?
オルタンシア様は真剣な眼差しで、私を見つめた。
大切な人が必ず不幸な死を遂げる。
あらかじめ分かっているのに、何もできないのは己の死よりも恐ろしい。
何度も繰り返されるのならば、大切な人の運命を変えるしか逃れる方法はない――。
ならば、大切な人の近くにいよう。
誰よりもそばに。
三回目の人生、ソナタを守る――。
*
***マーガレット視点
朝から晩まで、ネロカイア国の第三皇子の元で今日も忙しなく働いている。
私はメイドの新人下っ端だから、朝一番の仕事は、先輩たちが嫌がる、庭掃除の担当だった。今も早朝から庭掃除をしていた。
何故庭掃除が嫌われているかというと――。
枯葉を集め終えた瞬間、赤いドラゴンが飛んできた。ドラゴンの風圧で集めた枯葉が再び散らかる。
――またか。
「おい、お前、いつから枯葉を集めている?」
「はい、一時間ほど前から枯葉を集めております」
「それなのに、まだ全然集まってないのか?」
だって、それはさっきから皇子のドラゴンが散らかしてくるから……なんて言えるわけがないから言葉を心の底まで飲み込んだ。ブトン第三皇子は私よりもみっつ年上の二十歳。だけど同じ歳とは思えないほど言動が幼い。
「申し訳ございません」
深々とお辞儀をすると、鼻で笑いながら満足そうに去っていった。
――嫌がらせをすることでしか満足出来ないのかしら。
少し可哀想だなと感じながらそっと深いため息をつき、再び枯葉をほうきで集める。
すると今度は少女がやってきて 「お姉さん、今日はどんなお話を聞かせてくださるの? あ、そうそう召喚魔法って知ってる?」と、その子が可愛い声で聞いてきた。
この子の名はローズ。最近、庭で掃き掃除をしている時によく話しかけてくる。ふわふわで綺麗な金色の長い髪の毛がとても似合う五歳くらいの女の子。高級そうなワンピースドレスを常に着ているから、おそらく位は高い子なのだと思う。私はまだここには来たばかりで話せる相手は数少ないから、彼女と話すと気持ちが癒される。
「そうね……今日は、これからローズ様も関わることになる召喚獣についてのおはなしをしようかしらね」
「召喚獣って、未来の護衛のことよね?」
「えぇ、そうです。もう少し大きくなったら、ローズ様も召喚魔法を修得し、召喚獣と共に人生を歩まれることになると思います」
「お姉さん、私、詳しく教えてほしいわ!」
私は集まった庭の枯葉をホウキでまとめると、手を休めた。そして近くにある白いベンチの上に私のハンカチを置くと、そこに座っていただいた。
「かつて召喚獣は、戦争の道具として利用されていたのです。人対人の……一切争いには関係のない召喚獣達が戦争に巻き込まれておりました。やがて召喚獣の存在意義は変化していき、争いのない現在の我が国では、人の護衛としての役割を担うために存在しているのです。性格も凶暴だった召喚獣たちは、暮らしに合わせて穏やかになっていきました」
女の子は、手を組みながら真剣に話を聞いている。
「戦いに巻き込まれた召喚獣たちは人間と一緒にいて、嫌ではなかったのかしら」
「召喚獣にも心はあります。なので人間との性格の相性だってあります。あんまり大きな声では言えないけれど、嫌だと思う召喚獣も多くいたでしょう。今も、一緒になった人間が実は苦手と思う召喚獣もいるでしょうね……」
ちらっと私はブトン皇子が歩いていった方向を向いた。
少し経つと「あっ、呼ばれた。帰らなきゃ! お姉さん、またね」と、ローズ様は立ち上がった。
私には何も聞こえなかったけれど……ローズ様は耳がとても良いのかしら。
「えぇ、またいつでもお話しに来てください」
彼女の後ろ姿を消えるまで見送ると、掃き掃除を再開させた。再開させ少し経った時、枯葉が空に向かって渦巻き状に舞い、粉々になりながら、消えた。ただ呆然としながら空まで進んでいる枯葉を眺める。
集まったり散らかったり、そして今は粉々になり消えた。今日の枯葉は私よりも忙しそうね。
じっと枯葉の最期を見守っていると視線を感じ、後ろを向くと高身長で顔の整った、黒いローブを着ている男が魔法を使っていた。
「召喚獣に詳しいんだな? 召喚魔法を修得したいのか?」
視線が合うとその男は話しかけてきた。
「いいえ、修得したいだなんて、別に……それに、もしも召喚したいと思っていても、私は身分の低い女。なので全く無縁のお話ですから」
そう、私は召喚獣とは無縁だ――。
私は身分の高い公爵家で育った。両親共に当たり前のように護衛としての召喚獣が近くにいる日々を送っていたから、私も成人した日には魔法石を与えられ、召喚獣と一緒にいられる日々が来る。と、待ち遠しかった。
けれど アルトリア家は没落した。両親が優しい性格すぎたから、悪意ある者たちに利用され財産を隅々まで奪われた。そして代々築きあげられてきた我が家は没落した。両親共にストレスで身体が弱まり、私は家族の生活費を稼ぐために、今ここで今働いている。
もうすぐ私は成人を迎える。その時に魔法石を与えられるはずだった。
召喚獣の話なんて、メイドとして働く下流階級となった今の私には全く関係ないのだけど……。召喚獣を護衛として利用できるのは、召喚するための魔法石を配られる上流階級の人達だけなのだから。
だけど、召喚獣をお飾りのように扱う令嬢や、さっきの皇子みたいに遊びの道具として扱う人々を見ると、嫌気と嫉妬のような変な気持ちが込み上げてくる。
その男は、すっと私の右手を掴み、手のひらを上に向けさせた。すると手のひらに何かを乗せる。
「もしも召喚魔法を使いたい願望が少しでもあるのなら、夜中零時にあの木の下で会おう。召喚魔法を教える」
「私に、召喚魔法を?」
「そうだ」
男の人と話していると、先輩メイドふたりの視線が突き刺さってきた。先輩たちが早歩きでこっちに向かって来た。さぼっていたから怒られる。
「あの、私、掃除をしないと」
「あぁ、邪魔して悪かったな」
「いいえ……あの、お名前は?」
「自分の名はオルタンシアだ」
「私の名は、マーガレットです」
名前を伝えると彼は微笑みながら「知ってた」 と呟いた。
私の名前を、知っていた?
「じゃあ、待ってるからな」
オルタンシア様は去っていった。
「ちょっと、どういうことよ?」
「あのお方って、あの、優秀な召喚魔法使いのオルタンシア様よね?」
私たちの様子を眺めていた先輩メイドたち、ふたりがモンスターのような形相で攻めてきた。
「あ、あの、あの方は有名な方なんですか?」
「何よ、あんたもしかして知らないの?」
「はい、何度かお見かけはしていたのですが……」
「オルタンシア様は、召喚魔法修得の講師もしていて、ここ、王家でも教育なさっているのよ。あの整った容姿端麗なお姿は令嬢たちにもとても人気があるらしくて、引っ張りだこらしいわよ」
「年齢は、私と同じくらいで、二十五辺りかしら。恋人はいないって噂よ」
恋人がいない……あんなに格好がよいのに、意外。
先輩が思い切り私を睨む。
「何故あなた方が話をしていたのかわからないけれど、身分が全く違うのだから気安く話さない方がいいわよ。だって、あの方は国の四大名家のひとつ、 ヴァロイア家の跡継ぎの噂もあり、頭脳明晰で国の未来の頭脳部分も担うとも言われているとても高貴なお方よ」
「……」
そんなに身分の高い人だったの?
そんな彼がメイドなんかの私の名前をしっていて、何故、私に魔法を教えると言っていたの?
疑問しか浮かび上がらない。
今日の夜中、どうしたらいいのかしら。
夜、約束の時間が過ぎる。
今の私に召喚魔法なんて教えてもらう資格はないわ。
私がもしもいかなくても、彼は待っているのかしら?
ずっと彼のことを考えていると目が冴えて眠れない。
結局、白い薄手のナイトウェアの上に一枚ピンク色のものを羽織ると、同じ部屋で眠っている他のメイド三人を起こさないようにそっと静かに、メイドの寮の裏口から外へ出た。
月明かりで外は明るい。
一枚羽織っては来たけれど、ちょっと寒い。はぁっと白い息で私は手を温めながら進む。
約束の場所には、小さな池がある。そこはちょうど、夜中眠れない時にたまに行く場所。その時は池の中で揺れている月の明かりを眠くなるまで眺めていた。人もめったに通らないし、結構お気に入りの場所だった。
着くとオルタンシア様は……まだいた。
「来てくれたんだ?」
オルタンシア様は月よりも輝いているように見え、まるで暗闇の世界を明るく照らしているようだった。
「来てしまいました。教えてもらえる身分ではないのに」
「いや、そんなことはない。だって、自分たちは深い繋がりがあるのだから……」
「深い繋がり……ですか?」
こくんとオルタンシア様は頷いた。
初対面のはずなのに、深い繋がりとは?
「では今日は、さっき少女に伝えていた内容と重複するが、召喚獣について伝える」
聞こうか迷っていた矢先、本題に入った。
「今日ということは、また次も、ですか?」
「あぁ、そうだ。魔法の基礎から実践まで教えなければ使えないからな」
またこうやって会えるのかな?
この状況に、胸が高まっていた。
彼と目が合うと何か熱いものが全身を巡る。それは召喚魔法を使えるからか、それとも――。
「まずは、基礎知識を――」
オルタンシア様は、昼間私が女の子に教えた、過去、そして今の召喚獣の話を簡潔におさらいとして、説明してくれた。
「それと、大切なのは人が召喚魔法を唱えた瞬間から召喚獣には、恐れや悲しみなどの感情が召喚魔法を唱える人間から伝わるということだ」
「それを踏まえて、できるだけ優しい気持ちでいるのが理想だということでしょうか?」
「そういうことだな。早速だが、召喚獣を操る練習をしよう。魔法石は持ってきているか?」
「はい、持ってきております」
私は丁寧にハンカチに包んだ魔法石を手のひらに乗せ、彼にみせた。
「この魔法石は生徒たちが最初の練習に使うものだ。中には、穏やかな性格のカーバンクルがいる。まずは、自分が手本をみせる」
オルタンシア様が魔石をみつめ、手をかざすと魔石が虹色に輝いた。
「カーバンクルルー」と高い声と共に姿を現した、小さな兎のような狐のような姿をしたその幻獣はふわっと私の手に着地した。
「綺麗な若草色ね……カーバンクル、久しぶりに見たわ」
頬に寄せようとするとカーバンクルは自ら頬を擦り寄せてきた。ふわふわな感触が気持ちいい。
「可愛い! 人懐っこい……」
「カーバンクルは警戒しないからな。次は、マーガレットの番だ」
オルタンシア様がそう言いながらカーバンクルに手をかざすと、カーバンクルは魔法石の中に吸い込まれていった。
「私にできるのかしら……」
「できる。が、しかし最初は上手くいかないかもしれない。出てきてほしいと強く願いを込めて魔法石に手をかざすんだ」
「はい、やってみます」
左手のひらにある魔法石の前に右手を当て、目を閉じ今見たばかりのカーバンクルの姿を頭の中に浮かばせて……。
――お願い、お外に出てきてください。
辺りはしんとなる。何も変化は起こらない。すると耳元で「大丈夫だから、信じて」と、オルタンシア様の囁く声がした。
両手が温かくなってくる。
そして――。
「カーバンクルルー」と、カーバンクルの声も聞こえてきたから目を開けた。
目の前には再びカーバンクルがいた。
「最初の難関、すぐにクリアしたな。生徒たちの中で練習なしですぐに使えるのはおよそ一割ぐらいだ」
初めて魔法を使った。
魔法が、使えた。
――憧れていたけれど、無縁だと思っていた召喚魔法を。
出てきてくれたカーバンクルを強く抱きしめた。
「ただ、今そなたが使った魔力は、教育用の魔力だ。講師の自分がいる時にしか使えない。常に召喚魔法を使える状態にするには、魔法事務局が運営する試験を受け、合格する必要がある」
「では、この子を召喚できるのは今限り……」
「そうだ。合格すると常に共に過ごすことになる相性の良い召喚獣の魔法石を、数ある中から選び、その魔法石と共鳴する魔力が授けられ、正式に使えるようになるのだ」
「でも、そもそも召喚魔法は上流階級の方々しか使えないのでは?」
「例外もある」
「例外?」
「そう、それは自分が推薦した者も試験を受ける資格が与えられる」
私も、もしかしたら正式に召喚魔法が?
ゼロだった可能性が一気に跳ね上がり、期待感が増してくる。本当は、召喚獣と共に過ごす人生に憧れていた。でもそれは、推薦してもらわないと何も始まらない。
「あの、推薦をお願いいたします」
私のような地位の者が、オルタンシア様のような位の方にお願いするなんて、とんでもないことだ。けれど私は、ついお願いの言葉を吐いてしまった。
「もちろん、推薦する」
「……ありがとうございます。あの、お聞きしたいことがあるのですが、何故オルタンシア様は、そんなに私に良くしてくださるのですか?」
「――それは……」
「そなたが幸せになれるための、力に少しでもなれたらいいと思ったからだよ」
オルタンシア様は私をみつめてそう言った。口角は上がっているものの、何故か目はとても切ないような、悲しみを帯びているように見える。
「あっ、むこうから人が来た」と、オルタンシア様が言うと、私を来た人たちから見えないように隠してくれた。オルタンシア様と距離が近すぎて心臓の音が早くなってくる。私は顔を上に向け、オルタンシア様に「あの、本当にまたこうやって、教えてくれますか?」と、問う。
「もちろんだ。今日は、初めての練習だから、魔力を多めに使えるようにした。本来、召喚魔法を使うための魔力は今日使った魔力の3分の1の量だ。ただ、魔力を少なくするとその分魔法を使う難易度が上がる。難易度は上がるが、慣れると簡単になる。練習して、魔力が少ない量でも簡単に使えるよう、まずは慣れよう」
「ありがとうございます」
「では、また明日。この時間、ここで待ってる」
「はい、ありがとうございます」
「マーガレット!」
オルタンシア様の元から去ろうとすると名前を呼ばれた。直接名前を呼ばれドキリと強い胸の音がなる。私は振り向く。
「部屋まで、送る」
「いえ、近いから大丈夫です。それに、ここは人が滅多に来なくて大丈夫だと思いますが、私の部屋に戻るために通る道は、人が通ると思います。私たちがこんな時間に一緒にいることがバレたらやっかい……」
「では、こうしよう」
オルタンシア様が一瞬輝く、そしていなくなった。
――オルタンシア様が、消えた?
「オルタンシア様?」
「ここだ」
今、オルタンシア様の小さな声が聞こえた。そして足元に小さな光が。
「オルタンシア様!」
なんと、オルタンシア様が小粒になっていた。私はしゃがむと、手のひらにオルタンシア様を乗せた。
「これなら周りにも見つからないし、自分は変わらず魔法が使えるからそなたを守ることができる」
オルタンシア様は、部屋の前まで来ると私の手から降りて、建物の陰に行き、周りに人がいないことを確認した。そしていつもの大きさに戻った。
「ではまた明日」
「はい。今日はありがとうございました」
私は離れていくオルタンシア様の背中を見守る。
もっと一緒にいたかったな。でもまた明日も会えるんだわ!
空を見上げると、いつもよりも明るく輝いている満月が笑っていた。
朝から夜まで休みなく働いて、夜中の少しの間オルタンシア様から召喚魔法を教えてもらう。そんな日々を送るようになった。
オルタンシア様はあちこち色々な国へ行っていたから会えない日もあったけれども、そんな時は「お土産だ」と、見たことのないクッキーや素敵なブレスレットもプレゼントしてくれた。
そんな日々を過ごしていたけれど、ある日リーダー格の先輩メイドに「あんた、何か隠し事してない?」と、第三皇子ブトンの部屋を掃除中、こっそりと問い詰められた。
「何のことでしょうか?」
「私、あなたが夜中抜けだしてること、知っていたのよ。そして先日、後をつけてみたの」
もしかして、バレた?
気持ちの良くない汗が全身から流れてきた。私は何も答えられずにいた。
「あなた、オルタンシア様と密会してるでしょ?」
「はい」と認めてしまえばどうなるか分からない。何かいいアイディアはないか、私は私の全細胞を使い考えた。
「甘いものは、お好きですか?」
答えとは全く関係のない質問を先輩に投げる。先輩は質問を受け取ってくれるのか、緊張しながら様子を伺った。
「好きよ。大好きよ!」
「あの、先輩。素敵なお菓子があるのですが……」
私はエプロンのポケットからお洒落な袋に包まれたクッキーを出す。あとでこっそり間食しようとしていたお菓子。もちろんオルタンシア様からいただいたもの。
「まぁ、こんな素敵なお菓子いただけるの? 初めて見たわ!」
「いつも先輩にはお世話になっていますので。折り入ってお願いがあるのですが……」
「何よ、言ってごらんなさいよ」
いつもよりも高く弾んだ声。あきらかに先輩のご機嫌は良い。それもそうだ。私たちメイドにとってクッキーは高級なものでなかなか食すことはできないのだから。
「お、美味しい……こんな美味しいもの初めて食べたわ」
先輩は目を丸くして驚いていた。
というかここで食べても良いのか? ここはブトン皇子の部屋なのに。それよりも、今なら私の願いを聞いてくれるかもしれない。
「夜中に先輩がご覧になられたことはご内密にしていただきたいのですが……」
「そんなこと? いいわよ! その代わり、またおすそ分けちょうだいよ」
「はい! ありがとうございます」
私は先輩に向かって、丁寧にお辞儀をした。
***
オルタンシア様から召喚魔法を教わり、半年経った。
「よし、完璧だな」
「ありがとうございます」
今では、少ない魔力でもカーバンクルを軽々出せるようになった。そしてカーバンクルの能力である、人を心身ともに元気にする力も指示すると使ってくれるようにもなった。ちなみにカーバンクルは攻撃系の召喚獣ではないから、護衛の召喚獣から除外されている。
「試験が合格したら、当日、相性の合う召喚獣が入った魔石を体内に取り込むことになるのでしたよね?」
「あぁ、そうだ」
「私、カーバンクルがいいな……」
練習で使っていくうちに、カーバンクルに対しての情が湧いてきていた。
「この子がいいのか?」
「……はい。というか、これはただのワガママですよね! 召喚魔法が使えるだけで贅沢なのに」
「そんなことはない。カーバンクルがいいのか……」
オルタンシア様は顎に手を当て考え事をしていた。
「今のお話、なかったことにしていいですから……では、試験の日は、採点よろしくお願いいたします」
***
そうして私はついに試験の日を迎えた。
当日の移動手段である馬車は、オルタンシア様が手配してくれた。普段乗っている馬車とは違い、全てが立派。長時間座っていてもお尻が痛くないふわふわな椅子。内装も私が好きな花柄模様の煌めくデザイン。だから馬車に乗った朝から気分が高まっている。
試験会場である滅多にお目にかかれない立派な神殿に着くと、中で受付をすませた。
オルタンシア様は、どちらにいらっしゃるのかしら。
長い廊下を進んでいくと、広場へ続く扉があり、そこは開いていた。中を覗くとオルタンシア様がいた。試験を受ける人たちがずらっと並んでいる。男性は高級そうなタキシード、女性は華やかなドレス。私も持っている中で一番華やかな、唯一のドレスを着てきたけれども、場違いかな?と思うほどに地味。
けれども今日はファッションショーではなくて、召喚魔法の試験日。気にしないでいこう。私は一番後ろに並んだ。
試験を受ける人は、二十人くらいか――。
黒いローブを纏い書類を持つ、比較的年齢が高めな審査員が男女五人並んでいた。オルタンシア様は胸に手をやり深呼吸している。
オルタンシア様、緊張しているのかしら?
見つめていると、オルタンシア様と目が合った。ふたり同時に、軽く会釈した。
「早速ですが試験を始めます。それでは一番の方、前へどうぞ」と、審査員の一番お年を召しているお婆さんの言葉を皮切りに、審査が始まった。
「それでは、試験用の魔力を本日試験を受けられる皆様に与えますので、この並べられた魔法石からお好きなものを選んで召喚獣を出し、命令をしてください」
一番目の受験者の、柔らかな雰囲気で同じくらいの歳に見える男の人が前に出た。同時に色や形が様々な魔法石が、長テーブルの上に10程並べられた。男の人は真ん中辺りの一番大きな赤い魔法石を手に取った。その男は魔法石を左の手のひらに乗せ、右手を魔法石にかざすと、その魔法石は輝き、赤い竜の召喚獣が出てきた。
召喚獣と共鳴すると、その召喚獣がどんな攻撃の技が使えるのか頭の中に浮かび上がるらしい。
「召喚獣よ、空に向かって火を吐くのだ」と、男が叫ぶと竜は空に向かって大きな火を吐いた。
――もしかして、全ての召喚獣がこんなに強そうなの? というか、私が選んだ魔法石からも召喚獣が出てきて、共鳴してくれるのかしら。
心配をよそに、試験は進んでいく。中には上手く共鳴できない人もいた。
そしてついに、私の番が来た。
緊張溢れて、心臓の音が早くなる。
無意識にオルタンシア様の方を向いたけれど、オルタンシア様はいなかった。
私の番なのに、どうして――?
お手洗いに行ったのかしら。オルタンシア様がいなくて少しだけ不安な気持ちが押し寄せてきた。
「20番目の方、お願いいたします」
きっと大丈夫、上手くいくわ!と自分に言い聞かせる。
審査員の声を合図に私は並んだ魔法石の前に立った。常に補充され、テーブルの上には、10種類の魔法石が置かれていた。
どれにしようか悩む。相性の良い魔法石はすぐに分かるらしいけれども、少しも分からない。と、思っていたら、突然ひとつの薄紫色の小さく丸みを帯びた魔法石が輝いているように見えた。それは多分、私だけだろう。
こういうふうになるの?
念の為に他の魔法石もひとつひとつ手をかざし確認してみたけれどぱっとするものはなかった。
――これだわ。
魔法石を左手のひらに乗せ、右手をかざすと、魔法石と私が共鳴したからなのか、輝きだした。そして何故か、オルタンシア様のお姿が頭の中で浮かび上がる。
何故召喚獣が思い浮かばないのかしら?
まさか、オルタンシア様を召喚するわけ……あった。
会場がざわめく。
私も思わず「何故?」と大きな声で叫んでしまった。
それは、魔法石から出てきたのはオルタンシア様だったから――。
「どうしてオルタンシア様が?」
「それは、マーガレットの召喚獣となるからだ」
「いや……でも……」
どうすればよいの?
オルタンシア様は堂々とそう主張なさっている。
私は他の審査員の方に視線を向けた。
ずっと全員がどよめいている。おそらく誰もそのオルタンシア様の、その話を聞いてはいなかったからだろう。
「で、では。全ての受験生の試験は終わりましたので、三十分後に結果発表を行います」
司会をしていたベテラン召喚士が驚きすぎたのか、口を開いたまま止まっていたので一番若い男の召喚士が代わりに進行をした。
他の生徒たちは試験会場から離れていく。オルタンシア様も審査員たちに呼ばれて、私から離れていった。私も時間が来るまで、外で散歩をすることにした。この流れの意味が理解できずに、待っている間、ずっと胸の奥がそわそわしていた。
そして結果発表の時間がついに来た。
「それでは、番号を呼ばれた者は前へ」
召喚魔法は使えたけれど、魔法石から出てきたのはなんとオルタンシア様で。
合格なのか、不合格なのか。全く予想ができない。
「1番、3番、6番……」
番号は想像よりも飛ばされている様子。より緊張は高まる。
「8番、11番、15番、16番……」
私は胸の辺りで手を組み、呼ばれますようにとお祈りをした。
「そして、20番」
――呼ばれた!
「はい!」と返事をすると、前に出た。
出たけれども、私の召喚獣となるオルタンシア様は審査員たちのところに並んでいた。
試験に合格すると、人間と召喚獣が一生一緒にいられるように、魔法石が体内に入り、心臓の一部となる。人間の心臓が動き続ける限り共に過ごす、運命共同体となる。すなわち、人間の死により、召喚獣は開放されるということ。
1番目の男の人の前に、この国で一番トップの召喚士が立った。召喚士は手に魔法石を持っていて、男の人の胸元に魔法石を当てると虹色に輝き、あっという間に男の人の胸の中に吸い込まれていった。そしてついに私の順番が来た。
「あの、私はどの召喚獣が?」
答えを求めていると、オルタンシア様が目の前に立つ。手には魔法石を持っている。
「自分でいいか?」
「いや、いいかと聞かれましても……」
動揺していると、オルタンシア様が私の胸の近くに魔法石をかざしてきた。
そして、その魔法石は虹色に輝き私の中へ。だけど、オルタンシア様は目の前で立ったまま。
……オルタンシア様はそのまま? だとしたら、今私の中に入っていった魔法石には何の召喚獣が入っているというの?
「オルタンシア様、私の召喚獣は――?」
「自分だ」
――本当に、オルタンシア様が私の召喚獣に?
オルタンシア様は真剣な眼差しで、私を見つめた。