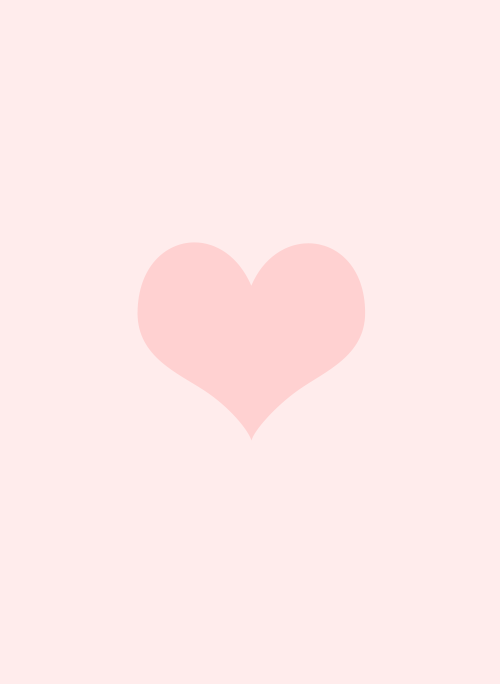ほら、櫂に会うとわたしもダメになっちゃうんだよ。
どうしようもない感情が湧いて出てくるから困っちゃう。
「……なんでも、ない」
わたしのことを展示してくれたことが嬉しくて切なくて泣いた、なんて言えるわけがない。
「ごめんな。勝手に展示しちゃって」
なんでもないわけがないのに、そこは深く追求しようとはしないところにも彼の優しさを感じてまた泣けてくる。
「ううん、大丈夫」
「あのさ、美桜」
「なに?」
硝子玉のような澄んだ瞳がじっとわたしを見つめる。
わたしたちの間に妙な緊張感が流れ、それに便乗するようにわたしの鼓動がどんどん加速していく。
「―――好きだ」
彼の口から飛び出した言葉をすぐには理解できなかった。
いや、その言葉の意味を理解したくないだけ。
本当はさっきの写真を見た時から薄々感じていた。
だけど、見なかったことにしようとしたのだ。
だって、それはわたしが向けられていい感情じゃないから。
「美桜のことが好きなんだ。だから……」
「ごめんなさい。わたし好きな人がいるし、櫂の気持ちには応えられない」
何か言われる前にわたしは櫂の言葉を遮った。