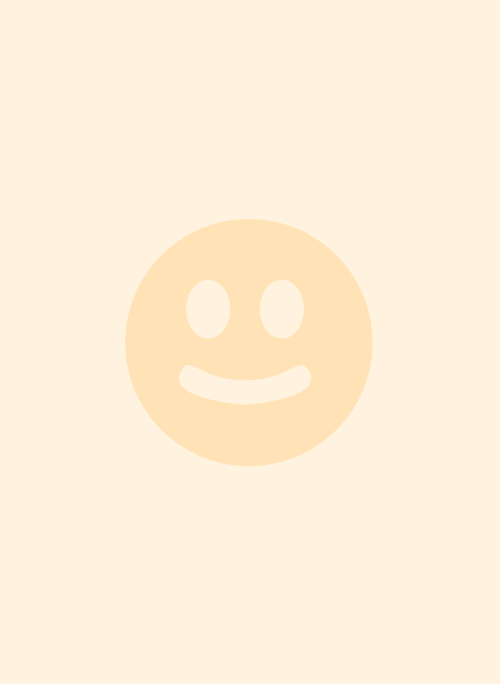「…………えっ?」
「……何か言ってたろ」
アカツキは睨むようにこっちを見てた。
「……何か言ったな」
言うと、アカツキは頷いた。
「…その言った言葉を覚えてるか、って訊いてんだ」
俺は突然話題を変えられたことに違和感を感じつつも、仕方なく正直に「覚えてる」と答えた。
「……本当に、か?」
「本当だって。どうしたんだよ」
「じゃあ、今ここでもう一回同じことを言ってみろ」
「…お前、覚えてるんじゃないのか?」
「いいから、もう一回言ってみろ、って言ってんだ」
えらい剣幕で詰め寄ってきた。
ベッドの上なので退けなかったが、思わず上体を後ろへと少しそらした。
そして、俺は気圧されるようにして、ぽろりと言ってしまっていた。
「お前のことが好きだって――言った」
アカツキは詰め寄ってきた姿勢のまま、ぴしゃん、と固まった。
息さえ止めてるかのような硬直ぶりだった。
俺は両方の意味で驚いていた。
一つはアカツキの反応。
そして
もう一つは――、
存外にあっさりと告白してしまえている自分に。
「……なっ…」
アカツキはベッドの上に座って居ながらよろめいた。
驚天動地の出来事に直面したような表情をしている。
「なに、あっさりぬかしてんだ、お前はっ」
目を白黒させながら、なぜか怒っている。
「なんで、そんなことを、そんな平然と言えるんだ。どんな神経してんだ」
まくし立てるように言ってきた。
「……なんで、って…」
俺は困った。
「……だって、本当にそうだから」
そうとしか言いようがない。
「ずっと好きだった。
……そのことに気づいたのがつい今しがたってだけで」
自分でも驚くほど落ち着いて言えた。
あれだけ言えなかったことが、こんなにすんなり言えるって不思議だ。
一方、アカツキのほうを見ると固まったまま、どんどんと頬を赤くしていた。
目は完全に泳いでいる。
さっきまでのあの勢いはどうしたのか、言葉を失っているようだった。