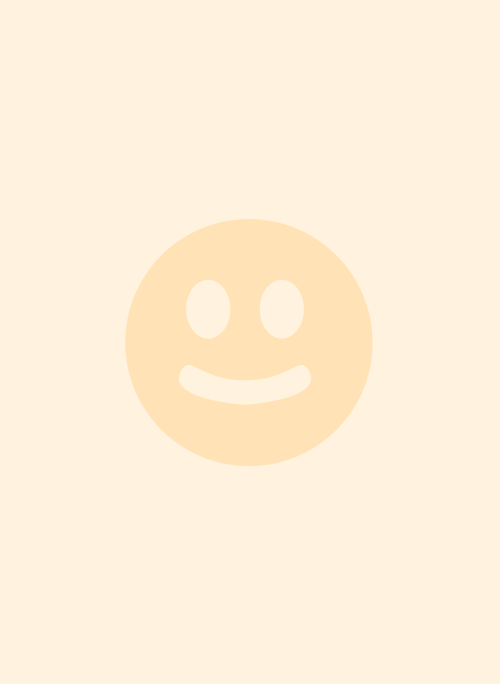その時、ピンポーンと玄関の呼び鈴が呑気に鳴った。
「はーい」と応じる。
残念ながら我が家の呼び鈴はただ鳴るだけで、部屋で来訪者の顔を確認出来ちゃったりとかいう機能は付いてない。あと会話したりも出来無い。
わざわざ玄関まで出なきゃいけないのが面倒だ。
ドアの覗き窓からその向こうの訪問者のお顔を拝む。
するとあちらさんの顔が超ドアップで目に映った。
どこをどう見ても見知った顔だった。
「ナゼに?」と不思議に思いつつもガチャッとドアを開ける。
その拍子にゴツンと鈍い音がした。
開いた先で「いたぁいん」と額を手で押さえてる相手を見るからに、開いたドアに頭をぶつけたのだろう。近づきすぎ。
「わりぃ」と謝る。
するとその相手はすぐさま痛みから立ち直り、パッと表情を一転させ、
「おはよっ、シュン」
爽やかに挨拶を言ってきた。
「お、おはよ…白石さん」
その明るさに面食らいながら、ぎこちなく挨拶。
(なんで白石さんが朝っぱらからうちに?)
疑問符が頭の中で飛び交う。
大きな違和感が、またも降って湧いてくる。
戸惑うこちらもお構いなしに、白石さんは膨れた。
「もぅっ。いい加減に名前で呼んでよ。付き合ってだいぶ経つのに」
「………え?……つ、付き合う?」
その言葉にぶったまげそうになった。
「……そ、それは…いったい…どーいう…」
………冗談?
頬が引き攣るのをはっきりと自覚する。
俺と白石さんが付き合ってる――だと?
どこをどう記憶を辿っても、頭をはたいてみても、そんな事実など出てきそうにない。
ほとほとに困り果てて、その根本的原因である相手を見た。
そんな胸中を察したのか、
「むぅ~。シュンってば寝ぼけてる?」
ますます膨れながら、ずいっと顔を寄せてくる。
「……いや…そんなことは無……んぐ?!」
もともと接近してきてただけに、避けるすべなど無かった。
否定しかけた口をすかさず白石さんの唇でふさがれてしまった。わわわ…。
白石さんはわざと「チュッ」と音を立ててから、その口を離した。