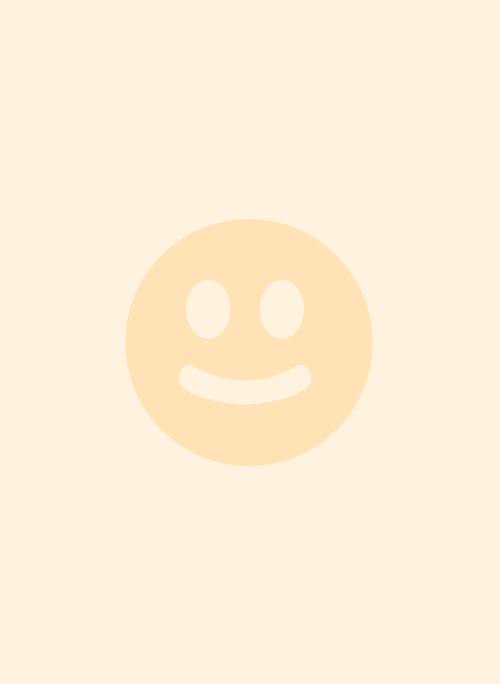「――でさぁ。お前、月村とはどこまで進んでんの?」
こいつは教室に着いてからなおもしつこくそんな事を訊いてきた。
無視し続けようとしたのに、奴は俺の前の席に陣取り、椅子にまたがってこちらを見ている。
ちょうど俺の前の座席の奴は出席日数ギリのサボリ魔でほとんど欠席か遅刻か早退。
席が空いてるので、じきにサトシがのさばる。
真面目に出て来いよ、と心底に思ったり。
「あのなぁ」
うんざりしつつ、コンビニのおにぎりを頬張る。
「進んじゃいないし。そもそもそういう関係じゃねーし」
「はーん。よく言うぜ」
サトシは俺を見て意味ありげに笑う。
「学祭ん時、二人揃って遅くまでエスケープしてて?」
「……おい」
頬が引き攣る。
「何度言うんだよ、それ」
げんなりと吐く。
あれ以来、こいつは何かにつけてその事を引き出してきては冷やかしてくる。
「だって気になんだろ。後夜祭の時まで仲良く戻って来なくてさー。色々噂も立ってるんだぜ?あんな遅くまで二人でナニやってたんだかってね」
「…………」
黙り込む。
無視しようとしても、何ともいえない後ろめたい感情がせり上がってくる。
ナニやってたかって。
勿論その全て、しっかり覚えている。
その記憶の一端、一番際どい部分が脳内で自動再生され、顔がカーッと熱を帯びてくるのを感じる。
俺は何の気の迷いで、あんなことをしようとしちまったんだろ。
「おんや。黙りこむっつうことはますます怪しいな。
二人っきりで一体どこで何をやってたんだ?ん?」
顔を近づけて詰め寄ってくる。
俺は椅子ごと後ろへ下がった。
こいつはちょっと危ない一面を密かに持ってて、こないだの学園祭でそれを思い知らされたばかりだ。
出来れば封印したい記憶のうちの一つ。
こともあろうか、女装した俺に…、
「あっ、そーだ」
そんな当の変態馬鹿は、俺の顔を見て思い出したように、ポケットから携帯を出してきた。