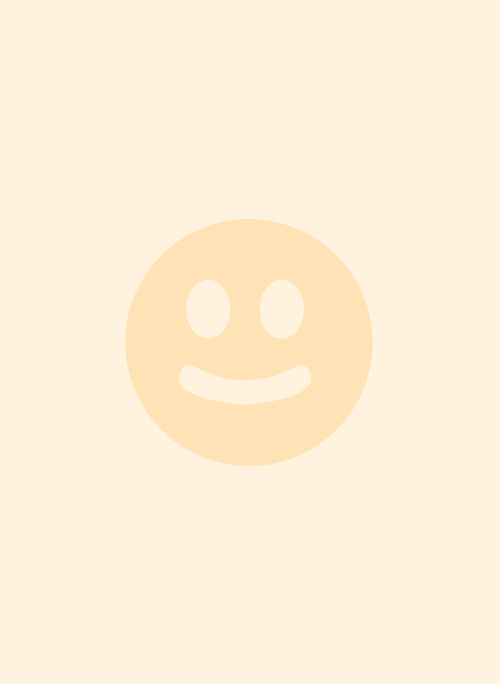「いいんだよ。どーせ後で丸く焼くんだから」
気にせず、雑なことを言うアカツキ。
「んな問題じゃない!」
慌てて制止の声を掛けるが、アカツキはその手を止めない。
「ってこら!待て!勝手に具を入れんな!」
「いいだろ。別に」
「よかぁない。見ろ。洪水みたいになってんじゃねぇか」
「うっせぇなぁ。細かいこと言うな」
面倒くさげに言いながら、赤いものをどさどさと投入。
「だからストップ!止まって!紅ショウガどんだけ入れてんだ!」
「うるさい!手が滑っただけだ!」
生地が溢れ返ってとんでもない惨状に。
テーブルの上に新聞紙を敷いてて良かったよ、ホント。
「……はぁ」
その様子を見て悟る。このままだとまともなタコ焼きは出来上がらない。
「分かった。お前はもう何もすんな」
「…何だと?」
「後は全部俺がするから」
「は?意味分かんね。じゃあ私はお好み焼きの方をするぞ」
伸ばしかけたその手より先に、素早く俺が生地の入ったボールを取る。
「いいからお前は座ってろ」
「あん?ここは分担した方がいいに決まってんだろ」
アカツキが強引にボールを掴んでくる。
「絶対分担しない方がいいって。だから座ってて」
「絶対私がやる。てめぇの方こそすっこんでろ」
互いにボールから手を離さないまま、テーブルを挟んでギリギリと睨みあう。
……いや。実際は俺の方がかなり押され気味で。
と、そこへ。
「はいはい。喧嘩するほど仲がいいというのは身に染み渡るほどよぉく分かりましたから、意地張らずに楽しくやりましょうね」
俺とアカツキのどちらもの腕を掴んで、完全に傍観者となっていた奴が割って入ってニコニコと仲裁してきた。