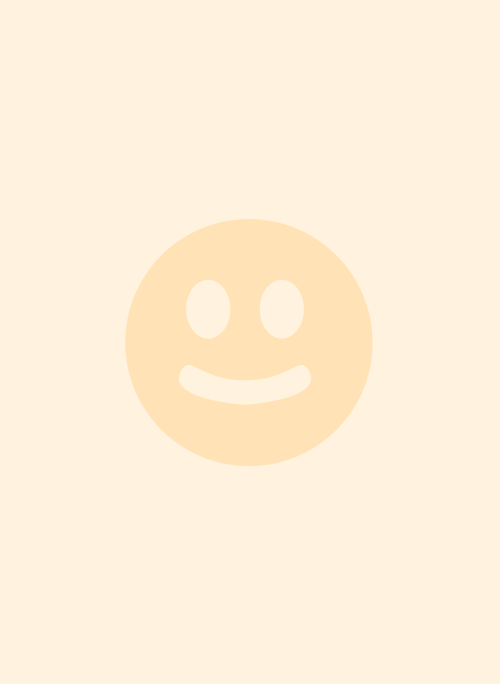自然と口調が尖る。
是が非でも訊き出さなければならない。そんな強い気持ちに駆られていた。
「…それを俺に訊くんはどうかと思うけど?」
ヘラッと笑っていた瀬川の口元が愉悦に歪んだ。
「……何?」
空気の質が変わるのを気配で感じた。
何かを押し込め、内包したかのような…。
張り詰めた…。
不自然に笑う奴の口が告げる。
「お前自身のことはお前自身で気づくべきなんとちゃうかな?」
その言葉とともに、張り詰めていた殺気が一気に弾けた。
「 ……っ」
全身に戦慄が走った。
先ほどまで飄々と話してた奴が――。
人とは思えないほどの凄絶な殺気を噴出させていた。
ガタンッッ!!
反射的に体が動く。
座っていたソファーを蹴り、机の上に飛び乗る。
手をシャツの襟の裏側に突っ込み、穴に指を引っかけた短い刃物――クナイをくるりと手の内で廻す。
瀬川達が編入してきてから、もしもの時に備えて、身体中に暗器を隠し持っていたのだ。
奴に肉薄すると同時に、その首筋にピタリとクナイの刃を押し付けた。
身動きすれば斬れる位置に。
それなのに相手は眉一つ動かさず、ただそこに居ただけ。
そう。
全く動いてなかったというのに…。
…俺だけが動いてしまっていた。
危険信号を発した本能に従って。
奴はそんな俺を楽しそうに見る。
「――殺気に反応して体が動くなんて…」
押し殺した笑いが漏れ出る。
「…まるで獣みたいやないか。なぁ?」
けれど何も答えられない。
「一つだけ教えたろ」
こちらの構えている武器など見えてないように、瀬川は平然とこう言った。
「お前のその身に流れてるんは、人の血だけやない。――異形の血が混じってる」