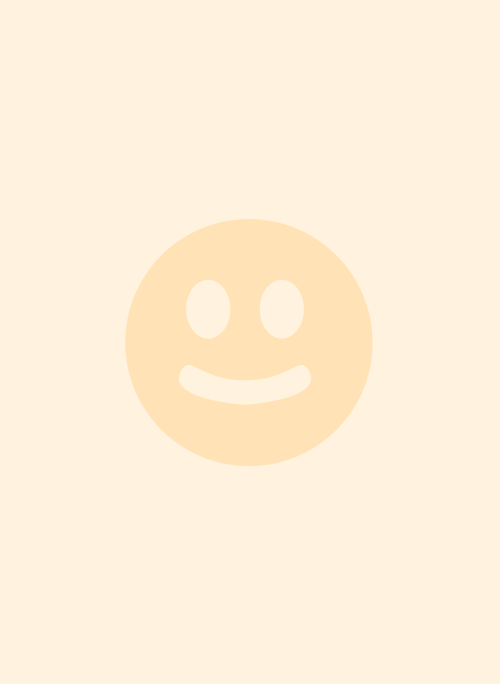一方の白石さんは余裕げに言葉を続ける。
「…どう?月村さんはきっとこんな気持ち良いことしてくれないよ?」
「………」
いいです。してくれなくて。
白石さんはふふふっと暗闇を震わせ、笑う。
「私って支配欲強いのよね…。
でも自分から動くのは苦手。
だから言い寄ってくる男は全員一応付き合って、相手を困らせてやって楽しんでいたの。わざとお金遣いを荒くして振り回したり」
うわっ。
脳が機能しなくても分かる。
この人は生粋のサディストだ。
「だけどシュンは違う――」
甘美な熱っぽい声で言う。
「こんなにも自分から誰かに対して積極的になったの初めてよ。
私、シュンの為なら何だってできると思う。
だっていつもシュンにどう思われてるかばかり気になってしまうもの…」
「………」
なぜだろう。
頬が一気に熱くなる。
異性からこんなにも直接的に思いを伝えられたのは初めてかもしれない。
俺が内心ぼーっとしている間に白石さんは立ち上がった。
「――だからいずれ必ずあなたを物にする…」
そうはっきり告げる白石さんの表情はどこか決然としていた。
立ち上がった白石さんはそのまま扉の方へ向かう。
ガラッと音が響いた。
室内に白い光が線のように差し込み広がる。
扉が開いたのだ。
「……あれ?鍵…」
掠れた声が出た。
霞みがかったぼんやりとした頭で不思議に思う。
「嘘よ」
届かないかと思われたその声に、白石さんは明るく答えた。
「…鍵なんて最初から掛かってなかったの」
うふふふと悪戯っぽく笑う声。
その様子は小悪魔そのもの。
俺は未だ動けないまま、呆然とそちらを眺める。
「――シュンって本当に…可愛いね」
扉に手をかけて振り返る白石さんの顔は逆光で表情が分からない。
けれどその唇がニッと持ち上がった気がした。
「でも、私以外の人には絶対騙されちゃ駄目だからね」
それだけを言い残して、部屋から去っていった。
薄暗闇の中に一人、俺だけが取り残された。