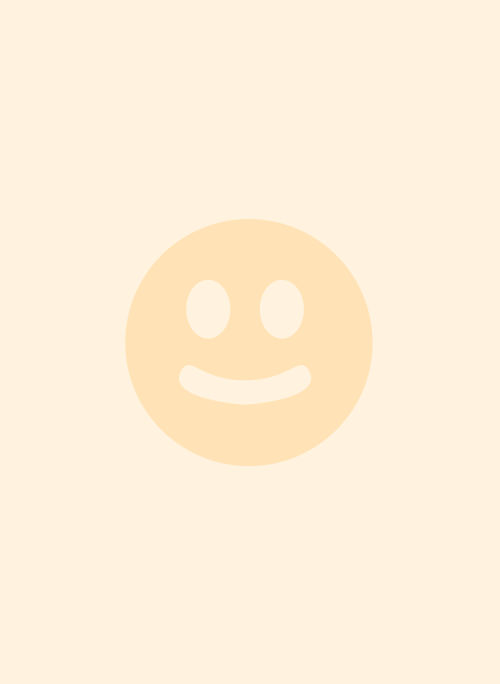*
その光景を目にして、これは夢なのだと分かった。
目線が今よりうんと低い。
これは幼い頃の記憶なのだろうか…。
辺りを見回す。
青く生い茂った木々。
蝉の声がわんわんと天高くまで響き、耳の奥に残響がまとわりつく。
季節は真夏。
じりじりと照りつける太陽の下、白銀の長い髪が陽光に煌めいてた。
「――ねぇ、冴月(サエヅキ)。
なんでそんなところに居るの。こっちにおいでよ」
広い日本家屋の縁側。
小さな体をした自分がなぜだかそこに立っていて、庭に立つその白銀の髪の女性に声を掛けていた。
その女の人の名前は冴月というらしい。
冴月は不思議な色の光を宿す金色の瞳をしていた。
「すいかがあるんだよ。一緒に食べようよ」
そう声を掛けるも、冴月というその人は首を横に振った。
「いえ、私はここでいいのです」
「…えーっ。なんで?」
「ここに居て、貴方様方を見守ることこそ私の役目と心得ております」
抑揚に乏しい声でそう答えてくる。
が、俺は首を傾げた。
「うーん。でもそこに居て暑くない?」
「いいえ。心頭滅却すれば火もまた涼し、なのです」
冴月は頑固にそう言い張って動こうとしない。
「――冴月」
俺の居る背後。縁側の奥の部屋の中から人が現れた。
振り返る。
そこに立つ人物を確認し、俺は「あ」と声を上げ、走り寄ってその足元に抱きついた。
そして――、
「――父上ー」
嬉しそうに、幼い俺は確かにそう呼んだのだ…。
そしてその大きく暖かな手が優しく俺の頭を撫でた。