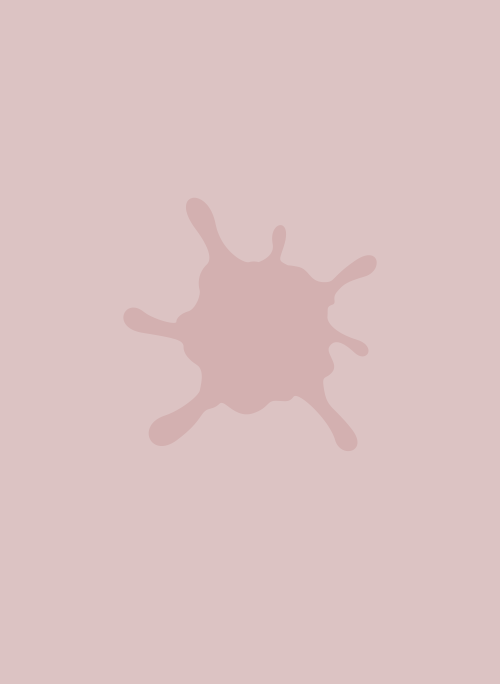結婚。
その言葉を聞くと、誰しも素晴らしく幸福なものをイメージするだろう。
たくさんの愛と幸福に溢れ、祝福され、自分の選んだパートナーと新たな人生に踏み出す、大きな一歩。
それはとても幸せなもので、誰にとっても憧れのイベント。
…だが、俺に言わせれば、そんなものは幻想だ。
所詮幸せな結婚なんてものは、幸せな人間がすることだ。
俺にとって結婚とは、愛に溢れてもいなければ、誰からも祝福されてさえいない。
それは果たすべき義務であり、役目だった。
俺が「結婚」することが決まった日、そのことを俺に告げた母は、泣きながら俺に謝った。
「ごめんなさい、悠理(ゆうり)。ごめんなさい…。本当に、ごめんなさい」
「…」
取り乱し、必死になって謝る母を見て、俺は思わず苦笑してしまった。
母はこんなに狼狽えているのに、当人である俺の方が落ち着いているとは。
こんな日がいつか来るだろうって、ある程度予測していたから。
自分でも驚くほど、意外と冷静だった。
「母さんが悪い訳じゃないだろ?」
「でも…。でも、私に何の力もないばっかりに、あなたにこんな役目を…」
そう、それは役目だった。
果たすべき義務だった。
俺の意志なんて関係ない。この家に生まれてきた以上、避けて通れない運命だった。
「悠理にはこんな思い…絶対にさせたくなかったのに…」
我が子の運命を、他人の手によって勝手に決められてしまった、自らの無力に嘆く母。
そんな母を、これ以上悲しませたくなかった。
だから、俺はこう言った。
「俺は大丈夫だよ、母さん」
本当に大丈夫だと思っていた訳じゃない。
どう考えても、俺の前途は多難だった。
ろくな未来が待っていないことは分かっていた。
だけど、それは…今に始まったことじゃない。
いつかこうなるだろうと思っていた。だから、心の準備はしていた。
いつか自分は…自分の意志に関係なく、見ず知らずの他人と結婚させられることになるのだと。
それが今、ようやく現実になったというだけの話だ。
その言葉を聞くと、誰しも素晴らしく幸福なものをイメージするだろう。
たくさんの愛と幸福に溢れ、祝福され、自分の選んだパートナーと新たな人生に踏み出す、大きな一歩。
それはとても幸せなもので、誰にとっても憧れのイベント。
…だが、俺に言わせれば、そんなものは幻想だ。
所詮幸せな結婚なんてものは、幸せな人間がすることだ。
俺にとって結婚とは、愛に溢れてもいなければ、誰からも祝福されてさえいない。
それは果たすべき義務であり、役目だった。
俺が「結婚」することが決まった日、そのことを俺に告げた母は、泣きながら俺に謝った。
「ごめんなさい、悠理(ゆうり)。ごめんなさい…。本当に、ごめんなさい」
「…」
取り乱し、必死になって謝る母を見て、俺は思わず苦笑してしまった。
母はこんなに狼狽えているのに、当人である俺の方が落ち着いているとは。
こんな日がいつか来るだろうって、ある程度予測していたから。
自分でも驚くほど、意外と冷静だった。
「母さんが悪い訳じゃないだろ?」
「でも…。でも、私に何の力もないばっかりに、あなたにこんな役目を…」
そう、それは役目だった。
果たすべき義務だった。
俺の意志なんて関係ない。この家に生まれてきた以上、避けて通れない運命だった。
「悠理にはこんな思い…絶対にさせたくなかったのに…」
我が子の運命を、他人の手によって勝手に決められてしまった、自らの無力に嘆く母。
そんな母を、これ以上悲しませたくなかった。
だから、俺はこう言った。
「俺は大丈夫だよ、母さん」
本当に大丈夫だと思っていた訳じゃない。
どう考えても、俺の前途は多難だった。
ろくな未来が待っていないことは分かっていた。
だけど、それは…今に始まったことじゃない。
いつかこうなるだろうと思っていた。だから、心の準備はしていた。
いつか自分は…自分の意志に関係なく、見ず知らずの他人と結婚させられることになるのだと。
それが今、ようやく現実になったというだけの話だ。