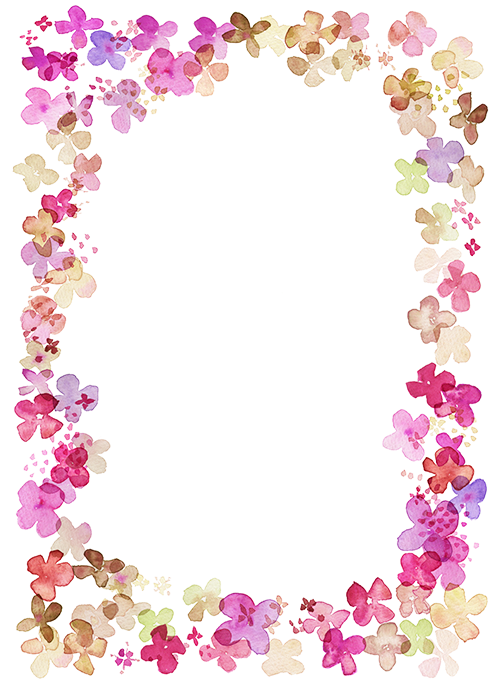2014年 春 現在
Side 紺炉
お互い無言のまま、どれくらい時間が経ったのだろう。
水面の月はさっきの位置から少しだけ動いていた。
お嬢が生まれてから今日までの17年間。
数々の出来事は細部まで、まるで昨日のことのように思い出せた。
それだけ濃密で、かけがえのない時間だった。
お嬢も今、同じようなことを思い出しているのだろうか?
縁側であぐらをかいている俺の上にちょこんと座らせたお嬢の頭に顎を乗せ、お嬢のお腹のあたりに手を回す。
お嬢は俺の手を握ったり触ったりして遊んでいる。
「・・・紺炉はさ、私がその若頭と結婚することになったらお祝いしてくれる?」
「・・・」
「その人との間に子供生まれたら、可愛がってくれる?」
「・・・」
「私が家を出て会えなくなっても平気?」
俺は言葉に詰まった。
そもそも、心の底から祝福なんてできるわけがない。
どこの組か知らねぇが、俺以外の男の隣で笑う顔なんて見たくもない。
子供?そりゃ男でも女でも、間違いなくお嬢に似て可愛いんだろうけど、考えただけで気が狂いそうになる。
そんなの全部、平気・・・・なわけねぇだろ。
しかし、タイムリミットは確実に迫っている。それはお嬢も分かっているはずだ。
だからきっとこれが最後の問答になる。
お嬢は、俺が首を縦に振っていないのに俺を引き合いに出して縁談を断るようなことは絶対にしない。
それが分かっているから、俺がとる選択は1つ——。
「……もしそうなったとしたら、全部、嬉しいに決まってるじゃないですか。早いけど、おめでとうございます。幸せになってくださいね。これで俺も安心です」
もう後戻りはできない、これまでヒビが入ってもなんとか大事に守ってきたガラスが粉々に砕け散ってしまったような、俺の中ではそんな感覚だった。
「・・・そっか。紺炉がそんなにお祝いしてくれるなら私、結婚……するね!」
俺はお嬢の方を向けなかったから、彼女がどんな顔をしながらそれを言ったのかはわからない。
俺は最後までズルい大人で、最低の男だった———。
Side 紺炉
お互い無言のまま、どれくらい時間が経ったのだろう。
水面の月はさっきの位置から少しだけ動いていた。
お嬢が生まれてから今日までの17年間。
数々の出来事は細部まで、まるで昨日のことのように思い出せた。
それだけ濃密で、かけがえのない時間だった。
お嬢も今、同じようなことを思い出しているのだろうか?
縁側であぐらをかいている俺の上にちょこんと座らせたお嬢の頭に顎を乗せ、お嬢のお腹のあたりに手を回す。
お嬢は俺の手を握ったり触ったりして遊んでいる。
「・・・紺炉はさ、私がその若頭と結婚することになったらお祝いしてくれる?」
「・・・」
「その人との間に子供生まれたら、可愛がってくれる?」
「・・・」
「私が家を出て会えなくなっても平気?」
俺は言葉に詰まった。
そもそも、心の底から祝福なんてできるわけがない。
どこの組か知らねぇが、俺以外の男の隣で笑う顔なんて見たくもない。
子供?そりゃ男でも女でも、間違いなくお嬢に似て可愛いんだろうけど、考えただけで気が狂いそうになる。
そんなの全部、平気・・・・なわけねぇだろ。
しかし、タイムリミットは確実に迫っている。それはお嬢も分かっているはずだ。
だからきっとこれが最後の問答になる。
お嬢は、俺が首を縦に振っていないのに俺を引き合いに出して縁談を断るようなことは絶対にしない。
それが分かっているから、俺がとる選択は1つ——。
「……もしそうなったとしたら、全部、嬉しいに決まってるじゃないですか。早いけど、おめでとうございます。幸せになってくださいね。これで俺も安心です」
もう後戻りはできない、これまでヒビが入ってもなんとか大事に守ってきたガラスが粉々に砕け散ってしまったような、俺の中ではそんな感覚だった。
「・・・そっか。紺炉がそんなにお祝いしてくれるなら私、結婚……するね!」
俺はお嬢の方を向けなかったから、彼女がどんな顔をしながらそれを言ったのかはわからない。
俺は最後までズルい大人で、最低の男だった———。