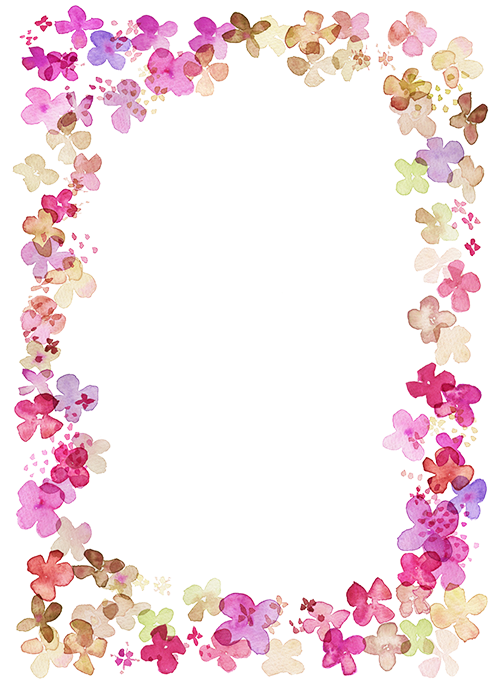Side 愛華
今日はスマホのアラームより先に、紺炉に声をかけられるよりも前に自然と目が覚めた。
昨晩の出来事はボヤーっとしか思い出せない。
けれど、首筋には確かに紺炉が残した印がある。
痛くも痒くもない、ただなんとなく甘い感触が残っている気がしてそっと指でなぞってみる。
どうせなら私も紺炉に付ければよかった。
でも昨日はこんなこと考える余裕がなかったのだ。
廊下の窓から差し込む光に目を細めながら囲炉裏のある居間を覗くと紺炉が窓際の椅子に座って新聞を読んいた。
「あ、おはようございます。早いですね。まだ5時ですよ?」
「紺炉・・・・眼鏡だ!」
「あー……。コンタクト入んなかったんですよ」
紺炉はなぜか恥ずかしそうにして再び新聞に視線を落とした。
私は座布団の上に座ってちゃぶ台に肘をつきながら紺炉の横顔を眺めていた。
「めちゃくちゃ視線を感じるんですけど……」
「だって紺炉が眼鏡かけてるのレアなんだもん」
最近流行りの丸い銀ぶちの眼鏡は、大人っぽい知的な印象だ。
ハッキリとした凹凸のある顔はメガネがとてもよく似合う。
実は紺炉は結構まつ毛が長い。
唇の乾燥を気にしてメントールのリップクリームをこまめに塗っていることも知っているし、サボるとすぐ伸びる髭に手を焼いていることも知っている。
それなのに、私がそんな何気ない仕草に目を奪われていることも、〝お嬢〟と呼ばれるのが好きなことも、紺炉はきっと知らない。
——どうしてこんなに紺炉のことが好きなんだろう。
困らせたいわけじゃないのに私はやっぱりこの気持ちを押し殺してなかったことになんてできない。
それが〝子供だ〟と言われるのなら、私は一生子供のままでいい。
私が大人になれば紺炉と一緒にいられると思っていたけど、話はそう単純じゃないらしい。
私が大人になって紺炉が離れていくのなら、いつまでも子供でいたい。
ふいに昨日おじいちゃんから聞かされた〝縁談の話〟を思い出した。
「何で泣いてるんですか?」
紺炉に言われて、私は涙が溢れていることに気がついた。
何でなんて聞かないでよ。
そんなの私が知りたいんだから——。
私はおじいちゃんから言われた縁談のことを紺炉に話した。
多分心のどこかで引き止めてくれることを期待していた。
だからこそ、あんな答えを返されたのがショックで、逆に怒りが込み上げてしまったのだ。
今日はスマホのアラームより先に、紺炉に声をかけられるよりも前に自然と目が覚めた。
昨晩の出来事はボヤーっとしか思い出せない。
けれど、首筋には確かに紺炉が残した印がある。
痛くも痒くもない、ただなんとなく甘い感触が残っている気がしてそっと指でなぞってみる。
どうせなら私も紺炉に付ければよかった。
でも昨日はこんなこと考える余裕がなかったのだ。
廊下の窓から差し込む光に目を細めながら囲炉裏のある居間を覗くと紺炉が窓際の椅子に座って新聞を読んいた。
「あ、おはようございます。早いですね。まだ5時ですよ?」
「紺炉・・・・眼鏡だ!」
「あー……。コンタクト入んなかったんですよ」
紺炉はなぜか恥ずかしそうにして再び新聞に視線を落とした。
私は座布団の上に座ってちゃぶ台に肘をつきながら紺炉の横顔を眺めていた。
「めちゃくちゃ視線を感じるんですけど……」
「だって紺炉が眼鏡かけてるのレアなんだもん」
最近流行りの丸い銀ぶちの眼鏡は、大人っぽい知的な印象だ。
ハッキリとした凹凸のある顔はメガネがとてもよく似合う。
実は紺炉は結構まつ毛が長い。
唇の乾燥を気にしてメントールのリップクリームをこまめに塗っていることも知っているし、サボるとすぐ伸びる髭に手を焼いていることも知っている。
それなのに、私がそんな何気ない仕草に目を奪われていることも、〝お嬢〟と呼ばれるのが好きなことも、紺炉はきっと知らない。
——どうしてこんなに紺炉のことが好きなんだろう。
困らせたいわけじゃないのに私はやっぱりこの気持ちを押し殺してなかったことになんてできない。
それが〝子供だ〟と言われるのなら、私は一生子供のままでいい。
私が大人になれば紺炉と一緒にいられると思っていたけど、話はそう単純じゃないらしい。
私が大人になって紺炉が離れていくのなら、いつまでも子供でいたい。
ふいに昨日おじいちゃんから聞かされた〝縁談の話〟を思い出した。
「何で泣いてるんですか?」
紺炉に言われて、私は涙が溢れていることに気がついた。
何でなんて聞かないでよ。
そんなの私が知りたいんだから——。
私はおじいちゃんから言われた縁談のことを紺炉に話した。
多分心のどこかで引き止めてくれることを期待していた。
だからこそ、あんな答えを返されたのがショックで、逆に怒りが込み上げてしまったのだ。