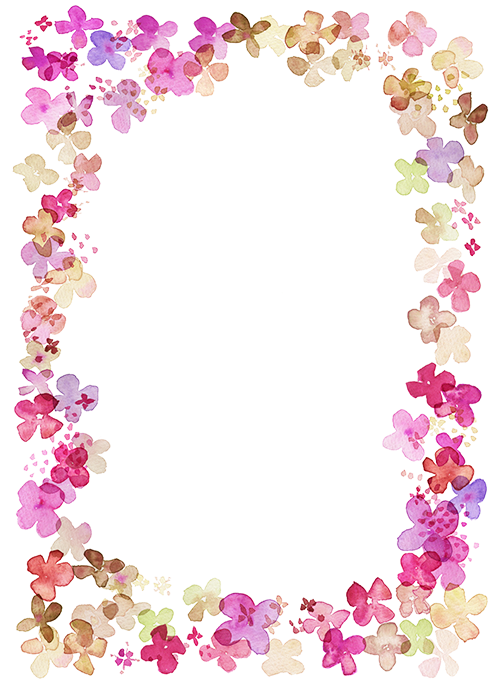東雲さんが連れてきてくれたのは飲み物で1000円近くするようなオシャレなカフェだった。
お店の前のメニューを見ると料理はどれも美味しそうだったけれど、さすがにバイトもしていない高校生が気軽に入ることのできる値段ではなかった。
もう少し安めのところで、なんて言うのも違う気がして、どうにか別のお店に誘導できないかあれこれ考えていると。
「お金は後で要に請求するから……というのは冗談だけど、ここはもちろん僕にご馳走させて?」
東雲さんはそう言って、人数を確認しに来たウェイターに2人だと伝えてしまっていた。
「ぶっちゃけさ、要と愛華ちゃんってデキてるの?」
「ゴホォッエホッオホッ」
「ごめんごめん驚かせたね(笑)」
席で注文を終えて水を飲んでいると、東雲さんがいきなり踏み込んだ話を振ってきた。
液体が気管に入ってしまうと、死すら感じるほど苦しい時間がしばらく続く。
咳込みを我慢しようとすれば余計に苦しそうな咳になるし、かと言って我慢しないとひたすらに続いてしまう。
やっと落ち着いたところで私はきちんと否定した。
「デキてなんていません!」
「そうなの?てっきりお祖父さんの目を盗んで2人で乳繰り合ってるのかと思ってた!」
「ちッ!?乳繰りあってはいません!!」
「〝乳繰りあっては〟ってことは、何かしらはあるってことかな・・・?」
東雲さんは記者のようにジリジリと攻めてくる。
絶対に私の反応を楽しんでいた。
「別に何も……」
「でもキスくらいはしたでしょ?」
「・・・黙秘します!」
自分でもボロが出ている自覚はあった。
東雲さんも「それはもう肯定でしょ」と笑っていた。
「……僕たちって特殊な家だからさ。大切な人と一緒にいることで、その人を巻き込むことになるのが怖いんだよね」
東雲さんはティーカップの揺れる水面を見つめながら切そうに言った。
まるで誰かを思い浮かべているようだ。
紺炉に迷惑はかけたくないと思ってはいるけれど、私たちはお互い五十嵐組の人間だから、そんなことは考えたこともなかった。
東雲さんの想い人は、極道の世界とは関係のない人なのかもしれない。
同じ一筋縄ではいかない恋をしている者として、勝手に親近感を抱いた。
お店の前のメニューを見ると料理はどれも美味しそうだったけれど、さすがにバイトもしていない高校生が気軽に入ることのできる値段ではなかった。
もう少し安めのところで、なんて言うのも違う気がして、どうにか別のお店に誘導できないかあれこれ考えていると。
「お金は後で要に請求するから……というのは冗談だけど、ここはもちろん僕にご馳走させて?」
東雲さんはそう言って、人数を確認しに来たウェイターに2人だと伝えてしまっていた。
「ぶっちゃけさ、要と愛華ちゃんってデキてるの?」
「ゴホォッエホッオホッ」
「ごめんごめん驚かせたね(笑)」
席で注文を終えて水を飲んでいると、東雲さんがいきなり踏み込んだ話を振ってきた。
液体が気管に入ってしまうと、死すら感じるほど苦しい時間がしばらく続く。
咳込みを我慢しようとすれば余計に苦しそうな咳になるし、かと言って我慢しないとひたすらに続いてしまう。
やっと落ち着いたところで私はきちんと否定した。
「デキてなんていません!」
「そうなの?てっきりお祖父さんの目を盗んで2人で乳繰り合ってるのかと思ってた!」
「ちッ!?乳繰りあってはいません!!」
「〝乳繰りあっては〟ってことは、何かしらはあるってことかな・・・?」
東雲さんは記者のようにジリジリと攻めてくる。
絶対に私の反応を楽しんでいた。
「別に何も……」
「でもキスくらいはしたでしょ?」
「・・・黙秘します!」
自分でもボロが出ている自覚はあった。
東雲さんも「それはもう肯定でしょ」と笑っていた。
「……僕たちって特殊な家だからさ。大切な人と一緒にいることで、その人を巻き込むことになるのが怖いんだよね」
東雲さんはティーカップの揺れる水面を見つめながら切そうに言った。
まるで誰かを思い浮かべているようだ。
紺炉に迷惑はかけたくないと思ってはいるけれど、私たちはお互い五十嵐組の人間だから、そんなことは考えたこともなかった。
東雲さんの想い人は、極道の世界とは関係のない人なのかもしれない。
同じ一筋縄ではいかない恋をしている者として、勝手に親近感を抱いた。