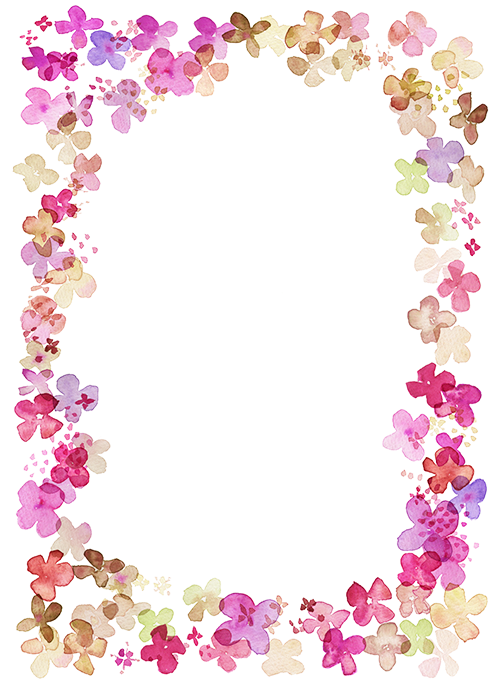2013年 秋
Side 愛華
理数系科目がすこぶる苦手な私は、伊藤くんに教えてもらった参考書を買いに大きな本屋さんに来ていた。
目当ての本はすぐに見つかったけれど、下の階から順に店内をあちこち見て回ることにした。
普段本はあまり読まないし、雑誌は美容院に行った時にめくるくらい。
漫画は犬飼が買っているジャソプを組のみんなで読ませてもらったり、友達に貸してもらった少女漫画を読む程度。
そんな私でも気分が上がる圧巻の品揃えだった。
気づけば時刻は12時を回っていて、私は本屋を後にした。
せっかく東京駅まで来たのだから何か食べて帰るつもりだった。
ところが、周りは家族や友達やカップル連ればかりだし、どこもお洒落なお店ばかりで女子高生一人で入れるようなお店はなさそうだ。
それなのに私のお腹は空く一方。
もう諦めて家に帰ろうかと思っていた時だった。
「愛華ちゃん?」
聞き覚えのある声に振り向くと、そこには紺炉が〝匠〟と呼んでいた、あの雨の日の若頭さんが立っていた——。
「あ、あの時の・・・!」
「東雲匠だよ。よかったー!今回は覚えてもらってた(笑)」
悪戯っぽく笑う彼に、昔会ったことがあったという紺炉の話を思い出した。
「紺炉に聞きました。前に会ったことあるって!すみません気がつかなくて……」
「まだ小さかったから仕方ないよ。僕は一目で分かったけどね。でもまさかこんな素敵な女性になるなんて……僕も歳をとるわけだ」
いやいや十分お若いです、と心の中で大きくツッコミを入れた。
知的で紳士で落ち着いていて、その上ユーモアもあって。
こんな人が極道の若頭だなんて未だに信じられない。
彼と出会って、私の中の若頭イメージに革命が起こった。
「要はいないの?1人?」
「あ、はい!ちょっと1人で買い物に……」
ぐぅぅぅぅ〜
その時、なかったことにはできないほど盛大に私のお腹が鳴った。
とっさにお腹を押さえて彼を見ると、口に手を添えて控えめにくすくす笑っている。
でもそれは決して馬鹿にするような笑いではなくて、嫌な気はしなかった。
ただ、ひたすらに恥ずかしい……。
「良かったらお昼一緒に食べない?俺もお腹減ってるし!」
この前紺炉に言われたことなんてすっかり忘れて、私は二つ返事で東雲さんに付いて行った。
誰だって空腹には敵わない。
Side 愛華
理数系科目がすこぶる苦手な私は、伊藤くんに教えてもらった参考書を買いに大きな本屋さんに来ていた。
目当ての本はすぐに見つかったけれど、下の階から順に店内をあちこち見て回ることにした。
普段本はあまり読まないし、雑誌は美容院に行った時にめくるくらい。
漫画は犬飼が買っているジャソプを組のみんなで読ませてもらったり、友達に貸してもらった少女漫画を読む程度。
そんな私でも気分が上がる圧巻の品揃えだった。
気づけば時刻は12時を回っていて、私は本屋を後にした。
せっかく東京駅まで来たのだから何か食べて帰るつもりだった。
ところが、周りは家族や友達やカップル連ればかりだし、どこもお洒落なお店ばかりで女子高生一人で入れるようなお店はなさそうだ。
それなのに私のお腹は空く一方。
もう諦めて家に帰ろうかと思っていた時だった。
「愛華ちゃん?」
聞き覚えのある声に振り向くと、そこには紺炉が〝匠〟と呼んでいた、あの雨の日の若頭さんが立っていた——。
「あ、あの時の・・・!」
「東雲匠だよ。よかったー!今回は覚えてもらってた(笑)」
悪戯っぽく笑う彼に、昔会ったことがあったという紺炉の話を思い出した。
「紺炉に聞きました。前に会ったことあるって!すみません気がつかなくて……」
「まだ小さかったから仕方ないよ。僕は一目で分かったけどね。でもまさかこんな素敵な女性になるなんて……僕も歳をとるわけだ」
いやいや十分お若いです、と心の中で大きくツッコミを入れた。
知的で紳士で落ち着いていて、その上ユーモアもあって。
こんな人が極道の若頭だなんて未だに信じられない。
彼と出会って、私の中の若頭イメージに革命が起こった。
「要はいないの?1人?」
「あ、はい!ちょっと1人で買い物に……」
ぐぅぅぅぅ〜
その時、なかったことにはできないほど盛大に私のお腹が鳴った。
とっさにお腹を押さえて彼を見ると、口に手を添えて控えめにくすくす笑っている。
でもそれは決して馬鹿にするような笑いではなくて、嫌な気はしなかった。
ただ、ひたすらに恥ずかしい……。
「良かったらお昼一緒に食べない?俺もお腹減ってるし!」
この前紺炉に言われたことなんてすっかり忘れて、私は二つ返事で東雲さんに付いて行った。
誰だって空腹には敵わない。