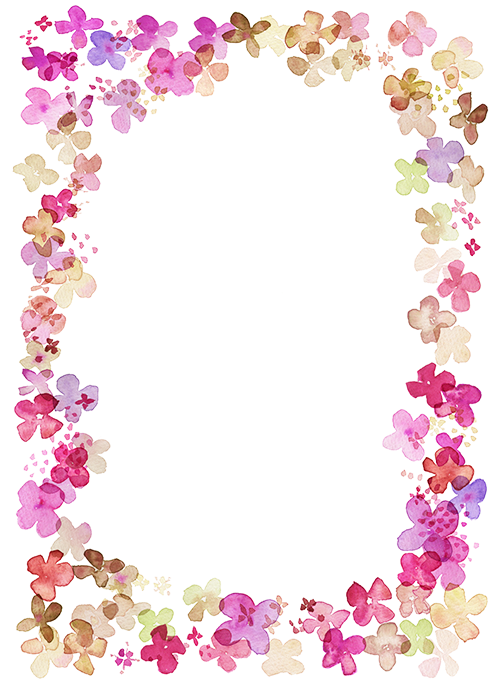2013年 夏
Side 紺炉
遠藤との約束の日。
俺たちは昼過ぎくらいに落ち合って商業施設の中を2人でぶらぶらした後、陽が傾きかけたくらいで遠藤が行きたがっていたイタリアンバルに入った。
いま遠藤は新卒で入社した総合商社でバリバリ働いているそうだ。
俺らの同級生の中には結婚をして子供がいるやつも多いらしく、改めて自分がそういう年齢なんだと実感した。
常にお嬢のことを考えてきたあっという間の17年。
夢も目標も特にない俺からお嬢をとったら一体何が残るだろか。
お嬢とプールに行った日から、いつか訪れる別れが頭を過ることが多くなった。
せめて今くらいは忘れていたくて、流し込むようにワインを飲みながら遠藤の話を聞く。
たらふく食べて飲んで喋ってから店を出ると、ちょうど花火が打ち上がっていた。
「そっか、今日花火大会あるんだよね!」
遠藤は明らかにテンションが上がっていた。
確か犬飼がお嬢と庭で花火をすると言っていた気がする。
空の花火を眺めながら手持ち花火をするらしい。
お嬢といい遠藤といい、女子は花火が好きだ。
「紺炉くん良かったら近くまで見に行かない……?」
せっかくの遠藤の誘いだったが、人混みが苦手な身としては家でしっぽり花火を楽しみたい気持ちだった。
「あー悪い、今日はちょっと……」
歯切れの悪い反応しかできず申し訳なさはもちろん感じていた。
さすがの遠藤も気分を害しただろうと顔色を窺うと、俺の目の前まで距離を縮めてきた。
「ねぇ、紺炉くん。キスしていい?」
なんとなく、なんとなく感じてはいたのだ。
単なる俺の自惚れかもしれないが、もしかしたらと。
だから「遠藤が俺のことを?」なんて驚きはなかった。
それにしても、行動に移る前にちゃんと聞いてくるところに遠藤らしさが表れている。
どこまでも素直で真面目で、そして気遣い屋だ。
「俺にとって遠藤はさ、俺的にこれからもずっと付き合っていきたい大事な大事な存在なんだよな。だからその質問の答えはノーだ。ごめん……けどありがとう」
遠藤は自分の足元を見ながら「そっか」と呟いた。
「彼女はいないんだよ……ね?」
「いない。でも好きな人は……いる。大事にしたいコが」
言葉にすると結構恥ずかしいものだった。
誰がとは言っていないが、遠藤は全て分かっている、そういう目をしていた。
「あーー紺炉くんほんとズルい!この前も、心配だから帰ったら連絡してとか言ってくるし。私は大事な友達だとか。ほんとズルイ!女たらし!最高だけど最低男!」
お嬢だけでなく遠藤にも最低男認定されるとは思わなかった。
苦笑いが止まらない。
「《《彼女》》とのこと、応援してるからね!」
やっぱりバレていた。
こんな〝最低男〟にも優しい言葉をかけてくれる遠藤に、俺は一生頭が上がらないだろう。
Side 紺炉
遠藤との約束の日。
俺たちは昼過ぎくらいに落ち合って商業施設の中を2人でぶらぶらした後、陽が傾きかけたくらいで遠藤が行きたがっていたイタリアンバルに入った。
いま遠藤は新卒で入社した総合商社でバリバリ働いているそうだ。
俺らの同級生の中には結婚をして子供がいるやつも多いらしく、改めて自分がそういう年齢なんだと実感した。
常にお嬢のことを考えてきたあっという間の17年。
夢も目標も特にない俺からお嬢をとったら一体何が残るだろか。
お嬢とプールに行った日から、いつか訪れる別れが頭を過ることが多くなった。
せめて今くらいは忘れていたくて、流し込むようにワインを飲みながら遠藤の話を聞く。
たらふく食べて飲んで喋ってから店を出ると、ちょうど花火が打ち上がっていた。
「そっか、今日花火大会あるんだよね!」
遠藤は明らかにテンションが上がっていた。
確か犬飼がお嬢と庭で花火をすると言っていた気がする。
空の花火を眺めながら手持ち花火をするらしい。
お嬢といい遠藤といい、女子は花火が好きだ。
「紺炉くん良かったら近くまで見に行かない……?」
せっかくの遠藤の誘いだったが、人混みが苦手な身としては家でしっぽり花火を楽しみたい気持ちだった。
「あー悪い、今日はちょっと……」
歯切れの悪い反応しかできず申し訳なさはもちろん感じていた。
さすがの遠藤も気分を害しただろうと顔色を窺うと、俺の目の前まで距離を縮めてきた。
「ねぇ、紺炉くん。キスしていい?」
なんとなく、なんとなく感じてはいたのだ。
単なる俺の自惚れかもしれないが、もしかしたらと。
だから「遠藤が俺のことを?」なんて驚きはなかった。
それにしても、行動に移る前にちゃんと聞いてくるところに遠藤らしさが表れている。
どこまでも素直で真面目で、そして気遣い屋だ。
「俺にとって遠藤はさ、俺的にこれからもずっと付き合っていきたい大事な大事な存在なんだよな。だからその質問の答えはノーだ。ごめん……けどありがとう」
遠藤は自分の足元を見ながら「そっか」と呟いた。
「彼女はいないんだよ……ね?」
「いない。でも好きな人は……いる。大事にしたいコが」
言葉にすると結構恥ずかしいものだった。
誰がとは言っていないが、遠藤は全て分かっている、そういう目をしていた。
「あーー紺炉くんほんとズルい!この前も、心配だから帰ったら連絡してとか言ってくるし。私は大事な友達だとか。ほんとズルイ!女たらし!最高だけど最低男!」
お嬢だけでなく遠藤にも最低男認定されるとは思わなかった。
苦笑いが止まらない。
「《《彼女》》とのこと、応援してるからね!」
やっぱりバレていた。
こんな〝最低男〟にも優しい言葉をかけてくれる遠藤に、俺は一生頭が上がらないだろう。