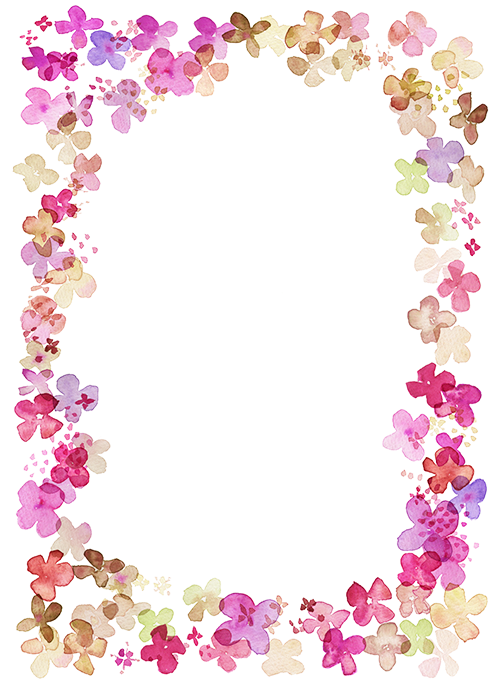2013年 夏
Side 愛華
この日は、私の帰宅時間に合わせて最寄り駅まで迎えに来てくれた紺炉と、商店街で夕飯の買い物をしていた。
長ネギが突き出たエコバッグやトイレットペーパーを抱えて家の方に向かっていると、後ろから声をかけられた。
「もしかして、紺炉くん?」
眩しい夕日に目を細めながら声の方を振り返ると、今どきのオフィスカジュアルな格好をした小柄で可愛らしい女の人が立っていた。
紺炉の身近な女性といえば、セクシーで派手めの人が多い。私には見覚えのない人だった。
「・・・遠藤?」
あぁ紺炉の知り合いなのか、と落ち込む自分がいた。
紺炉の名前を呼んだんだから知り合いに決まっているけど。
彼女は紺炉に会えたことがよほど嬉しかったようで、目をキラキラさせていた。
紺炉は驚きの方が大きそうだけど、懐かしむような優しい眼差しで彼女を見ていた。
2人は「久しぶり」とぎこちなく言葉を交わす。
ナニコレ?訳ありな仲なの?
「もしかして、妹さん?」
「あ、いや世話になってる家の子で……」
話題に困ったのか、彼女は急に私を巻き込んできた。
嫌味とかではなくただ純粋に疑問に思って聞いている感じにモヤっとしたし、紺炉のハッキリしない物言いにカチンときた。
久しぶりに2人水入らずで話したいという雰囲気が彼女からも紺炉からもぷんぷんして息が詰まりそうだ。
どうせ私がいたら邪魔なんでしょ?さっさと退散しますよ。
「私犬飼呼ぶから2人で話せば?じゃ!」
スマホを耳に当てて「あ、もしもし犬飼?」と電話したフリまでして私はスタスタ歩いた。
Side 愛華
この日は、私の帰宅時間に合わせて最寄り駅まで迎えに来てくれた紺炉と、商店街で夕飯の買い物をしていた。
長ネギが突き出たエコバッグやトイレットペーパーを抱えて家の方に向かっていると、後ろから声をかけられた。
「もしかして、紺炉くん?」
眩しい夕日に目を細めながら声の方を振り返ると、今どきのオフィスカジュアルな格好をした小柄で可愛らしい女の人が立っていた。
紺炉の身近な女性といえば、セクシーで派手めの人が多い。私には見覚えのない人だった。
「・・・遠藤?」
あぁ紺炉の知り合いなのか、と落ち込む自分がいた。
紺炉の名前を呼んだんだから知り合いに決まっているけど。
彼女は紺炉に会えたことがよほど嬉しかったようで、目をキラキラさせていた。
紺炉は驚きの方が大きそうだけど、懐かしむような優しい眼差しで彼女を見ていた。
2人は「久しぶり」とぎこちなく言葉を交わす。
ナニコレ?訳ありな仲なの?
「もしかして、妹さん?」
「あ、いや世話になってる家の子で……」
話題に困ったのか、彼女は急に私を巻き込んできた。
嫌味とかではなくただ純粋に疑問に思って聞いている感じにモヤっとしたし、紺炉のハッキリしない物言いにカチンときた。
久しぶりに2人水入らずで話したいという雰囲気が彼女からも紺炉からもぷんぷんして息が詰まりそうだ。
どうせ私がいたら邪魔なんでしょ?さっさと退散しますよ。
「私犬飼呼ぶから2人で話せば?じゃ!」
スマホを耳に当てて「あ、もしもし犬飼?」と電話したフリまでして私はスタスタ歩いた。