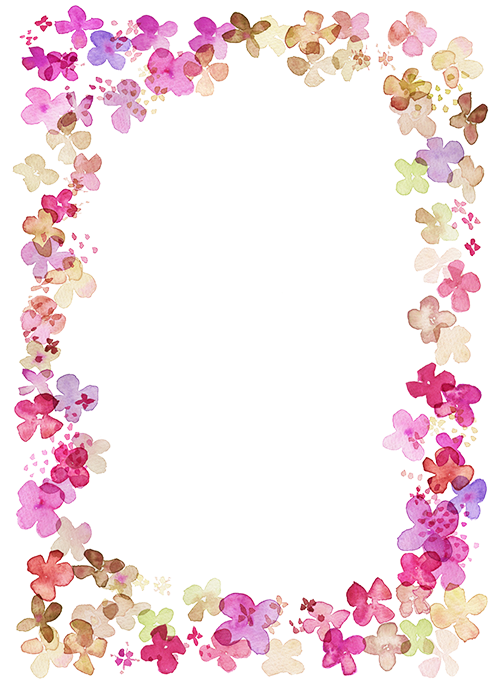2人並んで座って帰りの電車に乗っていると向かいには子連れの家族が座っていた。
母親の膝の上で眠る子供とそれを撫でる父親の様子が微笑ましい。
「ねぇ、紺炉は子供欲しいとか思ったりする?」
どうやらお嬢も前の家族を見ていたらしい。
まさか藪から棒にこんな質問をされるとは思わなかった。
「そうですねぇ、ああいうの見ると憧れはしますね」
「紺炉意外と子供の相手上手いもんね。いいお父さんになりそう」
「意外とは余計です。お嬢は口うるさいお母さんになりそうですね」
「紺炉は甘やかしそう。特に女の子には絶対メロメロだよ」
「確かにそれは否定できないかもしれないです」
ただひたすら前を見続けながら、ポツリポツリと言葉を交わす。
会話だけ聞くと、未来の話に花を咲かせる仲睦まじいカップルかもしれない。
まさか俺たちが、結ばれる運命にないただの主人とその世話係とは誰も思わないだろう。
「今日は楽しかったですか?」
「うん!」
「また来たいですね」とは言わなかった。
なぜなら、お嬢とこうして2人きりでプールに来ることなんてもうこの先ないと思ったから。
これから先、たくさんの出会いの中でいつかお嬢も恋をして、あんな風に自分の家庭を築くことになる。
お嬢がいなくなった五十嵐家なんて想像もつかないが、もう既にそのカウントダウンは始まっているのだ。
最後の最後で、遠くないうちに訪れるであろうお嬢との別れを考え気分が沈む。
本人は俺の肩に頭を預けて気持ちよさそうに眠っていた。
寄り添うように俺もお嬢の方に頭を傾けさせてもらう。
これくらいは大目に見てほしい。
どうかこのかけがえのない日常が少しでも長く続きますように——。
母親の膝の上で眠る子供とそれを撫でる父親の様子が微笑ましい。
「ねぇ、紺炉は子供欲しいとか思ったりする?」
どうやらお嬢も前の家族を見ていたらしい。
まさか藪から棒にこんな質問をされるとは思わなかった。
「そうですねぇ、ああいうの見ると憧れはしますね」
「紺炉意外と子供の相手上手いもんね。いいお父さんになりそう」
「意外とは余計です。お嬢は口うるさいお母さんになりそうですね」
「紺炉は甘やかしそう。特に女の子には絶対メロメロだよ」
「確かにそれは否定できないかもしれないです」
ただひたすら前を見続けながら、ポツリポツリと言葉を交わす。
会話だけ聞くと、未来の話に花を咲かせる仲睦まじいカップルかもしれない。
まさか俺たちが、結ばれる運命にないただの主人とその世話係とは誰も思わないだろう。
「今日は楽しかったですか?」
「うん!」
「また来たいですね」とは言わなかった。
なぜなら、お嬢とこうして2人きりでプールに来ることなんてもうこの先ないと思ったから。
これから先、たくさんの出会いの中でいつかお嬢も恋をして、あんな風に自分の家庭を築くことになる。
お嬢がいなくなった五十嵐家なんて想像もつかないが、もう既にそのカウントダウンは始まっているのだ。
最後の最後で、遠くないうちに訪れるであろうお嬢との別れを考え気分が沈む。
本人は俺の肩に頭を預けて気持ちよさそうに眠っていた。
寄り添うように俺もお嬢の方に頭を傾けさせてもらう。
これくらいは大目に見てほしい。
どうかこのかけがえのない日常が少しでも長く続きますように——。