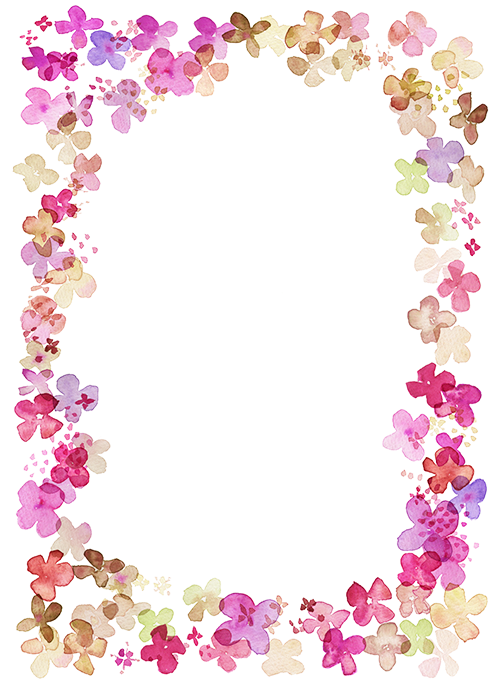2012年 冬
Side 紺炉
「ここまで耐えている俺を、誰か褒めてくれ・・・」
俺は烏龍茶を流し込みながら切実に訴えた。
ここクラブARIAは五十嵐組が懇意にしている高級クラブで、長年用心棒として定期的に組の人間が訪れている。
俺がしばらくお嬢の世話係を降りてホテル暮らししていたあの誕生日の日。
部屋に呼んで例の演技を依頼したあの女性は、ここのオーナーでありママだ。
「何が『ここまで耐えている〜』よ。話聞く限り、もうガッツリ手出してるじゃない」
彼女の言葉が胸にグサリと突き刺さる。
物怖じせずにズバズバ言ってくるこの性格が客からも人気で、こうしてトップにまで昇りつめたのだ。
同い年ということもあってか、俺にはかなり当たりが強い気もするが……。
「それより、あの時の貸し、返してくれるんでしょ?」
「あーーまぁ、はい。御礼させてイタダキマス」
そういえばあの時、お嬢に見せるための〝行為中〟の演技をしてもらったかわりに、女の子たちにシャンパンを入れる約束だった。
「みんな〜紺炉がアルマンド入れてくれるって〜」
「はぁっ!?アルマッ!?ちょっ、まっ!」
声かけによって、さっきまでママしかいなかった俺の席には女の子が次々と駆け寄ってくる。
もちろん全員顔馴染みだ。
「やったー!」
「紺炉さん男前♡」
「何かいいことでもあったの?」
普段は俺の扱いなんて雑なくせに、こういう時は手のひらを返したように俺を持ち上げる。
こんなところをお嬢に見られたら、今度こそ口を聞いてもらえなさそうだ。
考えただけで恐ろしい。
「これよこれ!」
そう言って小指をピコピコと動かすママを見て、黄色い声があがる。
が、次のひと言でそれは軽蔑の声に変わった。
「でも、その相手がよりによって自分とこのお嬢様なのよ……」
「え、お嬢様って確かまだ未成年だよね?」
「うわぁ、紺炉さんやっちゃってるね……」
「またイジリがいのあるネタ♡」
それからは、俺の弁解など全く無視され、ひたすら酒を飲まされた。
弱いどころか、どちらかと言うと強いはずなのだが、しこたま飲まされてさすがの俺も酔っ払った。
一人では歩くこともままならない状態で、犬飼の肩を借りながらなんとか車に乗り込み帰宅する。
Side 紺炉
「ここまで耐えている俺を、誰か褒めてくれ・・・」
俺は烏龍茶を流し込みながら切実に訴えた。
ここクラブARIAは五十嵐組が懇意にしている高級クラブで、長年用心棒として定期的に組の人間が訪れている。
俺がしばらくお嬢の世話係を降りてホテル暮らししていたあの誕生日の日。
部屋に呼んで例の演技を依頼したあの女性は、ここのオーナーでありママだ。
「何が『ここまで耐えている〜』よ。話聞く限り、もうガッツリ手出してるじゃない」
彼女の言葉が胸にグサリと突き刺さる。
物怖じせずにズバズバ言ってくるこの性格が客からも人気で、こうしてトップにまで昇りつめたのだ。
同い年ということもあってか、俺にはかなり当たりが強い気もするが……。
「それより、あの時の貸し、返してくれるんでしょ?」
「あーーまぁ、はい。御礼させてイタダキマス」
そういえばあの時、お嬢に見せるための〝行為中〟の演技をしてもらったかわりに、女の子たちにシャンパンを入れる約束だった。
「みんな〜紺炉がアルマンド入れてくれるって〜」
「はぁっ!?アルマッ!?ちょっ、まっ!」
声かけによって、さっきまでママしかいなかった俺の席には女の子が次々と駆け寄ってくる。
もちろん全員顔馴染みだ。
「やったー!」
「紺炉さん男前♡」
「何かいいことでもあったの?」
普段は俺の扱いなんて雑なくせに、こういう時は手のひらを返したように俺を持ち上げる。
こんなところをお嬢に見られたら、今度こそ口を聞いてもらえなさそうだ。
考えただけで恐ろしい。
「これよこれ!」
そう言って小指をピコピコと動かすママを見て、黄色い声があがる。
が、次のひと言でそれは軽蔑の声に変わった。
「でも、その相手がよりによって自分とこのお嬢様なのよ……」
「え、お嬢様って確かまだ未成年だよね?」
「うわぁ、紺炉さんやっちゃってるね……」
「またイジリがいのあるネタ♡」
それからは、俺の弁解など全く無視され、ひたすら酒を飲まされた。
弱いどころか、どちらかと言うと強いはずなのだが、しこたま飲まされてさすがの俺も酔っ払った。
一人では歩くこともままならない状態で、犬飼の肩を借りながらなんとか車に乗り込み帰宅する。