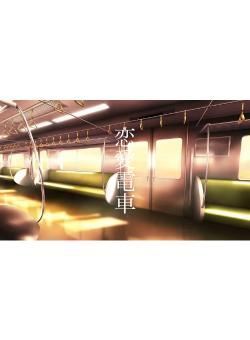「先生、写真撮りませんか!」
「南さんじゃん!いいよ。撮ろ。」
季節は秋の初め頃。
まだ夏の名残があり、暑さが続いている。本当に秋か疑うほどに暑かったが、地面に落ちているセミの死骸が、秋を告げていた。
今日は待ちに待った運動会。この日のためにダイエットを頑張って、太もも痩せに成功することができた。私には、そこまでしてまで想い合いたい好きな人がいる。
同級生でも、先輩でも後輩でもない。
先生だった。その綺麗な顔と包み込むように穏やかな性格に、私はどんどん漬け込まれていった。
藤山先生はいつも、私の無茶な頼み事でも引き受けてくれる。勉強でもそうだった。どんなに忙しくても、そんなのは後回しにして私を優先して時間を作ってくれるのだ。
そんな先生が、世界で1番大好きだ。
「あれ、スボンに砂ついてない?転けたの?」
先生は、少し心配そうな目つきで言った。
「そうなんです。さっきの競技で転けちゃって笑」
「怪我はなかった?大丈夫?」
「ちょっと膝打ちました笑」
出場した競技でつまづいてしまい、地面に膝を打った。先程までは少し痛い程度であったが、ほんの数十分で内側から叩きつけられているような痛みに変わっていた。
本当は今すぐにでも泣いてしまいたいほどの痛みだったが、先生の前で弱い姿を見せたくなかった。いや、というよりかは、先生に余計な迷惑をかけたくなかったのだ。
「大丈夫?ボーッとして。」
優しい、心配したような目つきで先生は私の顔を覗き込んだ。
痛みのせいか、先生の優しい声のせいか、いつの間にか私は膝を抱えながら蹲って涙をこぼしていた。
「大丈夫!!?痛い?そこ、養護テントあるから、俺着いてくよ。」
先生は、泣きじゃくる私をテントまで連れて行ってくれた。膝を保健の先生にアイシングしてもらっている間も、ずっと隣に座ってくれていた。
私が椅子に座って休憩している間、熱中症の疑いのある体調不良の生徒や、競技中に怪我をした生徒たちが次々とやって来ていた。保健の先生と保健委員の生徒がなんとか仕事を分担して対応していたものの、かなり忙しそうであった。
「先生、クラス戻らなくていいんですか?」
私はふと、先生のクラスのことが気になった。
「大丈夫大丈夫。副担の先生いるから。」
先生は、両手を後ろでつき、リラックスした格好でそう答えた。先生のいつもの癖だ。
貴方は優しすぎるんです。そう思いながら私は、運動場を走り回る生徒の姿をボーっと眺めていた。
たまにチラ見して見る先生は、「あっつ」と呟きながら服をパタパタとさせていた。私は、ふと思いつき、手に持っていたミニ扇風機を1番強い風に設定して、先生へ向けた。
「わ、涼し〜」
先生のフワフワな髪の毛が揺れた。
火照って少し赤く、汗ばんだ顔。
思わず見とれてしまいそうになる腕の血管。
「ん?どした?膝痛い?」
「……え、あ、いえ!!あ、痛いけど、その、大丈夫です!」
先生のおかげか、少し膝の痛みも和らいだ気がした。
アイシングに使用した氷は、もうすっかり溶けて水になっている。
それくらい時間が経ったのか、ただ暑いだけなのか。いや、案外どちらでもあるのかもしれない。その証拠として、午前中の競技は終盤に差し掛かり、養護テントの温度計は30℃をゆうに超えていた。
その後、膝が少し楽になってきたので、湿布を貼ってしばらく自分のクラスのテントで様子を見ることになった。
それを聞いた先生は、「良かった。良くなって。」とだけ言って先生のクラスへ戻って行った。
先生の後ろ姿は、少し寂しげに見えた。
きっと気のせいだろう。
そんなこんなで、いつの間にか午前中の競技が終了していた。
膝の痛みもだいぶ引いてきたようだ。きっと、藤山先生のおかげだ。
持ってきた飴を食べながら、私は先生のことを頭に巡らせていた。
「おーいユキ。死んでる?大丈夫?」
同じクラスの友人のサラが話しかけてきた。
サラもどうやら何か食べているらしく、時折口をもごもごさせていた。
「あー大丈夫大丈夫。」
「どーせ藤山先生のこと考えてたんでしょ?」
サラはそう言うと、私の手のひらにクッキーを置いた。チョコの部分が少し溶けて、内側の袋についていた。
「え!ありがとう!でもさ、暑いのにチョコ持ってくるのはアホじゃない?」
私は、サラに貰ったクッキーを口に入れた。
私のその問いかけに、サラは「アホじゃないし〜」と答えた。
サラとそんな会話をしていると、運動場内にアナウンスが響いた。
どうやらこれから昼休憩らしい。
食べ過ぎるとお腹が膨らんでしまうため、少量のパンとゼリーを持ってきた。
サラは、私のパンとゼリーを見て、「美味しそー」と呟いていた。
昼ごはんを早めに食べ終わると、私はサラに言って、そそくさとテントを離れた。
目的はただ1つ。先生に先程のお礼の飴をプレゼントするためだ。全ては先生の元へ行く口実を作るためにあるのだ。
先生は、コンビニ弁当を食べていた。
1人で黙々と食べている姿は、なんだか可愛く見えた。先生の食事中に話しかけるのも迷惑だろうと考えて、しばらく売店を見て回ることにした。
(売店かー、売店といえば屋台、夏祭り、)
今年の夏祭りも花火も、夏らしいことは出来ていない。好きな人と一緒に夏祭りなど、夢のまた夢のように感じる。
周りの友達は、どんどん恋を実らせて幸せそうにしている。私は笑顔で祝福するも、やはり複雑な気持ちになってしまう。
私はため息をついた。
と、そんな私の気を引こうとするかのように、1つの売店に目が釘付けになった。
_雑貨屋_
運動会の売店で雑貨を売るなんて中々個性的だなと思ったが、売られている商品は全て綺麗で惹かれるものばかりだった。数個の商品は既に売れたのか、所々に間が空いていた。
「あの、すみません。」
商品の後ろにいたお爺さんに声をかけた。
お爺さんは身じろぎをして、私の方へ目をやると、シワだらけの目尻をキュッと上げて笑った。
「いらっしゃい。好きな物はあるかな?最近の若者には少し古臭いかもしれんがな。」
そう言うと、お爺さんは高らかに笑った。
と、1つの商品に目が止まった。
ピンク色をした月が大きく描かれているストラップ。
「お前さん、それが欲しいのかい?」
お爺さんは、私の心を覗き込むかのようにそう聞いた。
「はい、とても綺麗なので。」
「ありがとさん。定価の半額で売るよ。」
お爺さんはそう言うと、コンコンと咳払いをした。
「え!!そんなのいいんですか?」
「その代わり、大切にしてあげてくれ。ピンク色の月は、お前さんの恋が上手くいくという意味があるしのう。」
私はギクリとした。このお爺さんは、私が恋をしていることを知っている?いや、ただの偶然だろう。
私はお爺さんにお礼を言うと、ストラップを持って先生のテントへ向かった。
そろそろ先生もご飯を食べ終わった頃だろう。先生にあげる飴は、ずっと握っていたせいで溶けかけていた。
テントに着くと、先生はまだベンチに座っていた。暇そうに遠くを眺めている。よし。今が絶好のチャンス。そう思い、一歩踏み出す。
「先生ーー!写真とりましょーー!」
横から声が聞こえてきた。私は思わず足を止めてそちらを見た。3年生の数名の女子生徒だった。私はムッとしながらも、少し遠くへ移動して、次のチャンスを伺った。
先生はその先輩と、とても楽しそうに話していた。こんな状況でも、先生の笑顔が輝いて、かっこよかった。
先輩は先生に何かを手渡していた。
私はそれを見てハッとした。
「さっき、私があの雑貨屋で買ったストラップ、、。」
先程、雑貨屋で購入したストロベリームーンが描かれたストラップを、先輩は先生に渡していた。胸がギュッと締まった。
しばらくしても、先生とその先輩は話一向に別れる気配が無かった。
むしろ、話は盛り上がってきている。
このままここに居ては完全に不審者扱いをされそうだ。それに、ずっと近辺をうろうろしていたためか、少し膝に来ていた。
私はしぶしぶ、クラスのテントへ引き返すことにした。
テントへ向かう途中、何人かの用務員がゴミを回収していた。私は先生にあげるはずだった飴を用務員が持っていたゴミ袋へ捨てた。
「はいはい、私の負けですよ。」
私は、小さな声でそう呟いた。
頭に、あのお爺さんの顔が浮かぶ。
あのお爺さんには、どこか不思議なオーラがあったように感じた。お爺さんと話している時、何故か、占いをされているような神秘的な感覚があったからだ。
_ お前さんの恋が上手くいくという意味があるしのう。_
何が、恋が上手くいくよ。こんな状態なのに叶うって?私は心の中で、ついお爺さんを責めてしまった。
私はその後、自分のクラスのテントへ戻った。手に握りしめていた飴はもう無い。私は、今更になって勿体なかったなと後悔した。
思ったよりも早く帰ってきたのに驚いたのか、サラが近づいてきた。
「あれ、ユキ。先生と話せたの?飴あげた?」
興味津々に聞いてくるサラに、気持ちの余裕が無い私は、不覚にも苛立ちを覚えてしまった。
「ううん。他の人と話してたから帰ってきた。膝も痛いし。」
「そっか。でも大丈夫だよ!また後で行けばいいし!」
いつもは救われるはずのサラの前向きな言葉も、素直に受け止めることが出来なかった。
少しのことで揺らぐ感情。私はもう、そんな自分に懲り懲りだ。
あの場を離れる時、一瞬聞こえた先輩の名前。茨田春子。
春子先輩は、その可愛い名前にピッタリなフワフワした見た目だった。
私よりも細くて、髪もサラサラで可愛い。
何もかも私に勝っている。
私は妙に納得してしまっていた。
サラはその後も、私が落ち込んでいるのを見て、必死に慰めてくれていた。
今は貴方の言葉、響かないや。ごめん。
私を励ますつもりなのか、煽るつもりなのか、手に持っていたミニ扇風機は、変わらず私に風を送り続けていた。
「南さんじゃん!いいよ。撮ろ。」
季節は秋の初め頃。
まだ夏の名残があり、暑さが続いている。本当に秋か疑うほどに暑かったが、地面に落ちているセミの死骸が、秋を告げていた。
今日は待ちに待った運動会。この日のためにダイエットを頑張って、太もも痩せに成功することができた。私には、そこまでしてまで想い合いたい好きな人がいる。
同級生でも、先輩でも後輩でもない。
先生だった。その綺麗な顔と包み込むように穏やかな性格に、私はどんどん漬け込まれていった。
藤山先生はいつも、私の無茶な頼み事でも引き受けてくれる。勉強でもそうだった。どんなに忙しくても、そんなのは後回しにして私を優先して時間を作ってくれるのだ。
そんな先生が、世界で1番大好きだ。
「あれ、スボンに砂ついてない?転けたの?」
先生は、少し心配そうな目つきで言った。
「そうなんです。さっきの競技で転けちゃって笑」
「怪我はなかった?大丈夫?」
「ちょっと膝打ちました笑」
出場した競技でつまづいてしまい、地面に膝を打った。先程までは少し痛い程度であったが、ほんの数十分で内側から叩きつけられているような痛みに変わっていた。
本当は今すぐにでも泣いてしまいたいほどの痛みだったが、先生の前で弱い姿を見せたくなかった。いや、というよりかは、先生に余計な迷惑をかけたくなかったのだ。
「大丈夫?ボーッとして。」
優しい、心配したような目つきで先生は私の顔を覗き込んだ。
痛みのせいか、先生の優しい声のせいか、いつの間にか私は膝を抱えながら蹲って涙をこぼしていた。
「大丈夫!!?痛い?そこ、養護テントあるから、俺着いてくよ。」
先生は、泣きじゃくる私をテントまで連れて行ってくれた。膝を保健の先生にアイシングしてもらっている間も、ずっと隣に座ってくれていた。
私が椅子に座って休憩している間、熱中症の疑いのある体調不良の生徒や、競技中に怪我をした生徒たちが次々とやって来ていた。保健の先生と保健委員の生徒がなんとか仕事を分担して対応していたものの、かなり忙しそうであった。
「先生、クラス戻らなくていいんですか?」
私はふと、先生のクラスのことが気になった。
「大丈夫大丈夫。副担の先生いるから。」
先生は、両手を後ろでつき、リラックスした格好でそう答えた。先生のいつもの癖だ。
貴方は優しすぎるんです。そう思いながら私は、運動場を走り回る生徒の姿をボーっと眺めていた。
たまにチラ見して見る先生は、「あっつ」と呟きながら服をパタパタとさせていた。私は、ふと思いつき、手に持っていたミニ扇風機を1番強い風に設定して、先生へ向けた。
「わ、涼し〜」
先生のフワフワな髪の毛が揺れた。
火照って少し赤く、汗ばんだ顔。
思わず見とれてしまいそうになる腕の血管。
「ん?どした?膝痛い?」
「……え、あ、いえ!!あ、痛いけど、その、大丈夫です!」
先生のおかげか、少し膝の痛みも和らいだ気がした。
アイシングに使用した氷は、もうすっかり溶けて水になっている。
それくらい時間が経ったのか、ただ暑いだけなのか。いや、案外どちらでもあるのかもしれない。その証拠として、午前中の競技は終盤に差し掛かり、養護テントの温度計は30℃をゆうに超えていた。
その後、膝が少し楽になってきたので、湿布を貼ってしばらく自分のクラスのテントで様子を見ることになった。
それを聞いた先生は、「良かった。良くなって。」とだけ言って先生のクラスへ戻って行った。
先生の後ろ姿は、少し寂しげに見えた。
きっと気のせいだろう。
そんなこんなで、いつの間にか午前中の競技が終了していた。
膝の痛みもだいぶ引いてきたようだ。きっと、藤山先生のおかげだ。
持ってきた飴を食べながら、私は先生のことを頭に巡らせていた。
「おーいユキ。死んでる?大丈夫?」
同じクラスの友人のサラが話しかけてきた。
サラもどうやら何か食べているらしく、時折口をもごもごさせていた。
「あー大丈夫大丈夫。」
「どーせ藤山先生のこと考えてたんでしょ?」
サラはそう言うと、私の手のひらにクッキーを置いた。チョコの部分が少し溶けて、内側の袋についていた。
「え!ありがとう!でもさ、暑いのにチョコ持ってくるのはアホじゃない?」
私は、サラに貰ったクッキーを口に入れた。
私のその問いかけに、サラは「アホじゃないし〜」と答えた。
サラとそんな会話をしていると、運動場内にアナウンスが響いた。
どうやらこれから昼休憩らしい。
食べ過ぎるとお腹が膨らんでしまうため、少量のパンとゼリーを持ってきた。
サラは、私のパンとゼリーを見て、「美味しそー」と呟いていた。
昼ごはんを早めに食べ終わると、私はサラに言って、そそくさとテントを離れた。
目的はただ1つ。先生に先程のお礼の飴をプレゼントするためだ。全ては先生の元へ行く口実を作るためにあるのだ。
先生は、コンビニ弁当を食べていた。
1人で黙々と食べている姿は、なんだか可愛く見えた。先生の食事中に話しかけるのも迷惑だろうと考えて、しばらく売店を見て回ることにした。
(売店かー、売店といえば屋台、夏祭り、)
今年の夏祭りも花火も、夏らしいことは出来ていない。好きな人と一緒に夏祭りなど、夢のまた夢のように感じる。
周りの友達は、どんどん恋を実らせて幸せそうにしている。私は笑顔で祝福するも、やはり複雑な気持ちになってしまう。
私はため息をついた。
と、そんな私の気を引こうとするかのように、1つの売店に目が釘付けになった。
_雑貨屋_
運動会の売店で雑貨を売るなんて中々個性的だなと思ったが、売られている商品は全て綺麗で惹かれるものばかりだった。数個の商品は既に売れたのか、所々に間が空いていた。
「あの、すみません。」
商品の後ろにいたお爺さんに声をかけた。
お爺さんは身じろぎをして、私の方へ目をやると、シワだらけの目尻をキュッと上げて笑った。
「いらっしゃい。好きな物はあるかな?最近の若者には少し古臭いかもしれんがな。」
そう言うと、お爺さんは高らかに笑った。
と、1つの商品に目が止まった。
ピンク色をした月が大きく描かれているストラップ。
「お前さん、それが欲しいのかい?」
お爺さんは、私の心を覗き込むかのようにそう聞いた。
「はい、とても綺麗なので。」
「ありがとさん。定価の半額で売るよ。」
お爺さんはそう言うと、コンコンと咳払いをした。
「え!!そんなのいいんですか?」
「その代わり、大切にしてあげてくれ。ピンク色の月は、お前さんの恋が上手くいくという意味があるしのう。」
私はギクリとした。このお爺さんは、私が恋をしていることを知っている?いや、ただの偶然だろう。
私はお爺さんにお礼を言うと、ストラップを持って先生のテントへ向かった。
そろそろ先生もご飯を食べ終わった頃だろう。先生にあげる飴は、ずっと握っていたせいで溶けかけていた。
テントに着くと、先生はまだベンチに座っていた。暇そうに遠くを眺めている。よし。今が絶好のチャンス。そう思い、一歩踏み出す。
「先生ーー!写真とりましょーー!」
横から声が聞こえてきた。私は思わず足を止めてそちらを見た。3年生の数名の女子生徒だった。私はムッとしながらも、少し遠くへ移動して、次のチャンスを伺った。
先生はその先輩と、とても楽しそうに話していた。こんな状況でも、先生の笑顔が輝いて、かっこよかった。
先輩は先生に何かを手渡していた。
私はそれを見てハッとした。
「さっき、私があの雑貨屋で買ったストラップ、、。」
先程、雑貨屋で購入したストロベリームーンが描かれたストラップを、先輩は先生に渡していた。胸がギュッと締まった。
しばらくしても、先生とその先輩は話一向に別れる気配が無かった。
むしろ、話は盛り上がってきている。
このままここに居ては完全に不審者扱いをされそうだ。それに、ずっと近辺をうろうろしていたためか、少し膝に来ていた。
私はしぶしぶ、クラスのテントへ引き返すことにした。
テントへ向かう途中、何人かの用務員がゴミを回収していた。私は先生にあげるはずだった飴を用務員が持っていたゴミ袋へ捨てた。
「はいはい、私の負けですよ。」
私は、小さな声でそう呟いた。
頭に、あのお爺さんの顔が浮かぶ。
あのお爺さんには、どこか不思議なオーラがあったように感じた。お爺さんと話している時、何故か、占いをされているような神秘的な感覚があったからだ。
_ お前さんの恋が上手くいくという意味があるしのう。_
何が、恋が上手くいくよ。こんな状態なのに叶うって?私は心の中で、ついお爺さんを責めてしまった。
私はその後、自分のクラスのテントへ戻った。手に握りしめていた飴はもう無い。私は、今更になって勿体なかったなと後悔した。
思ったよりも早く帰ってきたのに驚いたのか、サラが近づいてきた。
「あれ、ユキ。先生と話せたの?飴あげた?」
興味津々に聞いてくるサラに、気持ちの余裕が無い私は、不覚にも苛立ちを覚えてしまった。
「ううん。他の人と話してたから帰ってきた。膝も痛いし。」
「そっか。でも大丈夫だよ!また後で行けばいいし!」
いつもは救われるはずのサラの前向きな言葉も、素直に受け止めることが出来なかった。
少しのことで揺らぐ感情。私はもう、そんな自分に懲り懲りだ。
あの場を離れる時、一瞬聞こえた先輩の名前。茨田春子。
春子先輩は、その可愛い名前にピッタリなフワフワした見た目だった。
私よりも細くて、髪もサラサラで可愛い。
何もかも私に勝っている。
私は妙に納得してしまっていた。
サラはその後も、私が落ち込んでいるのを見て、必死に慰めてくれていた。
今は貴方の言葉、響かないや。ごめん。
私を励ますつもりなのか、煽るつもりなのか、手に持っていたミニ扇風機は、変わらず私に風を送り続けていた。