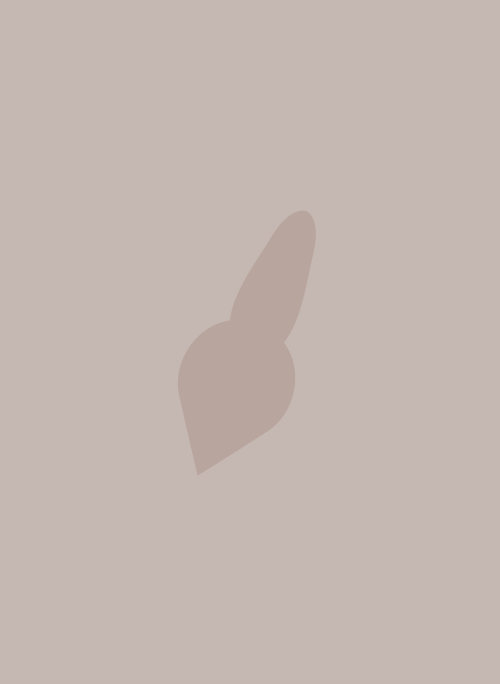ここから逃げ出しさえすればいい。
個人情報は名前しか知らせてないし
探せるわけない。
そうまでするとは思わないけど、とにかく消えなくちゃ――
どうやってこの場を乗り切ろうか考えていると、
「分かった」
涼さんの声が聞こえた。
え?
顔を上げると、優しい表情に戻った涼さんが微笑んでいた。
「もう、いいよ。
ごめんなミナトくん」
近づいてきた涼さんが、癖になってしまったかのように大きな手を僕の頭に乗せた。
そのままヨシヨシと撫でられる。
どうして……
どうして悲しい気持ちになるんだろう。
もういいと、言われて見限られたような
見放されたような
こんな勝手な気持ちが出てくるんだろう。
だって
本当は、涼さんの気持ちに応えたくて。
涼さんは一言も
僕にヴォーカルをやって欲しいとは言ってないけど。
もしマネージャーさんの言うように、僕にそれを望んでくれたなら
こんな光栄なことは無い。
これでサヨナラで
もう二度と会うことは無くて
また
イチ芸能人とファンで
関わることは無い。
それが僕の望みなのに。
.