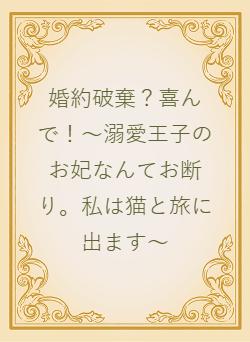「氷の魔術、とても美しかったです。見せてくれてありがとう。みんなが驚く式典になってよかったね」
彼女は大輪の花のように、満面の笑みを浮かべた。
自分が起こしたハプニングに対して「ありがとう」と言われたのは初めてだった。
あっという間に氷を溶かした魔力とコントロール力。なにが起こっても冷静で落ち着いている。人への配慮をおこたらないやさしい女の子で、立派な魔女。
――この人に、教わりたい。
「クレアさま。僕の、師匠になって下さい!」
溢れるままに想いを伝えると、彼女は一瞬目を見開いた。
「僕もクレアさまのように、魔術を使えるようになりたい。だから、教えてください!」
必死に思いを伝えると、クレアはふわりと笑った。
「わかりました。では、次私を呼ぶときは『師匠』って呼んでね。弟子のリアム」
「……はい、師匠!」
春を運ぶ風が二人に届く。彼女の眩しい笑顔がリアムの瞼に焼きつく。胸は、いつまでも高鳴り続けた。
*・*・*
リアムは瞼をそっと開けた。
――夢か。
夜明け前で室内は静寂に包まれていた。まどろみ誘われ目を閉じたまま寝返りを打つ。
やわらかな温もりに腕が触れて、もう一度目を見開いた。
夕焼け空のような、不思議な色の髪がすぐ傍にあった。朱に近い朱鷺色の髪の彼女が、ドレスを着たままリアムの腕の中に収まっている。
旅の移動でよっぽど疲れていたのか、ミーシャからすーすーと寝息が聞こえてくる。リアムは彼女が起きないようにそっと、寝台から離れた。
ぐっすりと眠れたのは久しぶりだった。彼女のおかげで、凍化病がやわらいでいると実感できる。
ハンガーラックには白と黒の外套が掛けかけられていた。二つともミーシャに渡したものだ。リアムは黒い外套をつかむと、外に向かった。