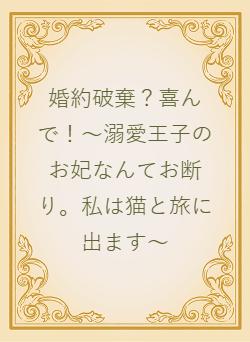* リアム・二十年前の記憶 *
銀色の世界がすべてだった。
先日七歳になったグレシャー帝国の皇子『リアム・クロフォード』は、外に向かって何度も息を吹きかけた。
「見て。僕の息が白くならない。凍らなくなった!」
視線を馬車の外ではなく、対面に座るオリバー・クロフォードへ向けた。
「国境を越え、フルラ国に入ったからだ」
叔父のオリバーは目を細めると、視線を外に向けた。遠くの山々はまだ雪化粧だ。
子どものリアムがグレシャー帝国の氷の宮殿から出るのは、今回が初めてだった。
年中白い景色ばかりの自国とは違い、フルラ国の空は青く晴れ、大地を覆う雪は溶けて芽吹きはじめている。目に映るものなにもかもが珍しかった。
豪華な箱形馬車と、護衛の騎馬隊や侍従およそ百数十人は森の中のあぜ道を行く。数日かけて太陽を追いかけるように南下してきた。国から離れるほどに気温が上がるのを肌で感じる。
この先にはどんな景色が広がっているのだろうかと、胸は期待でいっぱいだった。
「フルラ国のお城の地下には『炎の鳥』がいるんだよね。見てみたいな」
「炎の鳥は、フルラ国の魔女しか操れない。会ったら見せてもらうといい」
期待で膨らんでいたリアムの胸は一気に萎んだ。代わりに頬を膨らませて横を向く。
「……魔女なんてきらいだ」
オリバーは目を大きくさせた。
「リアム。この国でそんなことを言ってはならない」
「絵本に描いてあったよ。魔女は恐ろしくて、悪いやつだって。フルラの魔女はグレシャー帝国を燃やす化け物で悪魔だって、乳母のリルも侍女のメリッサも言ってた」
図書館にはたくさんの本があった。どの物語でも、出てくる魔女は全身を黒衣で包み肌を隠していた。フードから覗く顔はしわしわの怖い老婆。美人の魔女もいたが、目つきは鋭く、意地悪だった。
「本を読むことは大事だ。侍女たちが言ったことも事実だよ。だが、グレシャー帝国とフルラ国は今、仲良しなんだ。……覚えておきなさい。与えられるものだけが、すべてではない」
「どういうこと?」
「物事を一辺倒に見ていては、本質を見抜くことはできないってことだ」
「いっぺんとう? ほんしつ?……ぜんぜん、わかんない」
最近東洋から入ってきた金平糖なら知ってるけど、と答えるとオリバーは苦笑いを浮かべた。