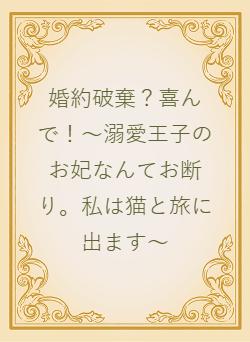「え?」と驚き、言葉を飲みこんだ。
来賓の中にも炎の鳥に家を焼かれた者はいるはずで、きっと今でも恐れ、憎んでいる。
負わせた心の傷をえぐるようなことはしたくない。
不安に思い躊躇していると、彼はミーシャの手を取った。
「大丈夫だ。俺を信じろ」
迷いのない瞳を見せてから彼は、人々に視線を向けた。
「炎の鳥は聖なる精霊獣だ。天の意思を伝える特別な存在。炎の鳥がこの地を燃やしたのは魔女ではなく、天の意思だ。堅い種子に覆われた植物の中には、大地が燃えたことで新しく芽吹くものがある。炎の鳥の聖火は、他者を傷つけるために火を使う人とは違う」
リアムは右手に氷の剣を作ると、高くかざした。
「それでも不安に思う、ご来賓のかたがたもいると思う。だが、心配はいらない。私は雪と氷を操れる。天の意思で炎の鳥が舞い降りても、天に授けられたこの私の力で、みなさまがたを守ろう」
会場内に白い雪が、静かに降りだした。誰もが上を向き、雪を眺める。
「きれい……」
ミーシャも天を仰ぎ、きらきらと舞う粉雪を目で追いかけながら頬をゆるめた。
「令嬢。雪に見とれている場合じゃない。今のうちに炎の鳥を呼んで」
リアムの声にはっとなった。彼の碧い瞳を見つめる。
氷の妖精皇子だった彼は、もう立派な氷の皇帝だ。説得力のある演説をこなし、人を引き付ける魅力であふれていた。
――リアムを信じよう。
ミーシャは頷くと、手を高くかざした。
「炎の鳥よ」
呼びかけると、会場を照らす燭台の灯がゆらりと揺れた。
雪を見て緊張をゆるめはじめていた人たちから悲鳴があがった。
「恐れるな。私がついている」
リアムは声を張ると、ミーシャの腰に手を回し、ぐっと引き寄せた。
――近い!
来賓の中にも炎の鳥に家を焼かれた者はいるはずで、きっと今でも恐れ、憎んでいる。
負わせた心の傷をえぐるようなことはしたくない。
不安に思い躊躇していると、彼はミーシャの手を取った。
「大丈夫だ。俺を信じろ」
迷いのない瞳を見せてから彼は、人々に視線を向けた。
「炎の鳥は聖なる精霊獣だ。天の意思を伝える特別な存在。炎の鳥がこの地を燃やしたのは魔女ではなく、天の意思だ。堅い種子に覆われた植物の中には、大地が燃えたことで新しく芽吹くものがある。炎の鳥の聖火は、他者を傷つけるために火を使う人とは違う」
リアムは右手に氷の剣を作ると、高くかざした。
「それでも不安に思う、ご来賓のかたがたもいると思う。だが、心配はいらない。私は雪と氷を操れる。天の意思で炎の鳥が舞い降りても、天に授けられたこの私の力で、みなさまがたを守ろう」
会場内に白い雪が、静かに降りだした。誰もが上を向き、雪を眺める。
「きれい……」
ミーシャも天を仰ぎ、きらきらと舞う粉雪を目で追いかけながら頬をゆるめた。
「令嬢。雪に見とれている場合じゃない。今のうちに炎の鳥を呼んで」
リアムの声にはっとなった。彼の碧い瞳を見つめる。
氷の妖精皇子だった彼は、もう立派な氷の皇帝だ。説得力のある演説をこなし、人を引き付ける魅力であふれていた。
――リアムを信じよう。
ミーシャは頷くと、手を高くかざした。
「炎の鳥よ」
呼びかけると、会場を照らす燭台の灯がゆらりと揺れた。
雪を見て緊張をゆるめはじめていた人たちから悲鳴があがった。
「恐れるな。私がついている」
リアムは声を張ると、ミーシャの腰に手を回し、ぐっと引き寄せた。
――近い!