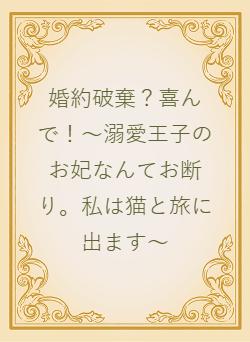「ごめんなさい。みんなを助けるためとはいえ、人々に怖い思いをさせた」
下を向き、拳をきつく握った。
「リアムは、魔女を悪く言う本が広まらないようにしてくれたり、私のお披露目パーティーを開いたりしてくれたけれど、そのすべてを台無しにした。本当に、ごめ……」
最後まで言い切る前にミーシャは抱きしめられた。
「ごめんはたくさん貰ったからいらない。謝るな」
ずっと張っていた気がゆるみ、涙がこみあげてきた。泣かないように唇の端を噛む。呼吸を落ち着かせてから口を開いた。
「人が助かるなら、どう思われようとかまわなかったの。これからも私は、困っている人を見かけたら助けてしまうと思う。だけど、それだけじゃ足りない」
ミーシャは、彼の腰に手をまわし抱きしめると、顔をあげた。
「心臓が止まるとき、強く思った。リアムのことが好き。離れたくないって。これからも傍にいたいから、あなたのために私は悪い魔女ではなく皇帝にふさわしい魔女として、みんなに認めてもらえるように努力する。今度こそ、あなたの隣に立つ妃として、がんばりたい。ううん、がんばる」
リアムは真剣な顔で見つめてきた。
「大丈夫、心配ない。俺はこの国の皇帝だ。誰を妃にするのか、それは俺が決めるし、誰の指図も受けない。好きな人と一緒になるのに、民や、周りの賛成は必要ない」
ミーシャは首を横に振った。
「あなたは人々を導く希望よ。民や周りの意見を無下にしてはだめ。そんなことをしたら……オリバー大公殿下と同じ。また、悲劇を繰りかえす」
「無下にはしないし、悲劇は繰りかえさない。俺には頼れる臣下がいるし、ミーシャがいる。時間はかかるかもしれないが、みんな、きっとわかってくれる」
リアムが大丈夫というのなら本当にいつか、魔女を認めてもらえる日が訪れるかもしれないと、淡い期待が胸を過ぎった。
「リアムのおかげで元気が出てきた。だけど、それでも全員の理解を得るのは無理だと思う。そうなったときは……」
「皇帝を辞めればいい」
「……え?」
目を見張った。「身を引くとか言うなよ」と、先に釘を刺し、リアムはミーシャの額に自分の額を重ねた。
下を向き、拳をきつく握った。
「リアムは、魔女を悪く言う本が広まらないようにしてくれたり、私のお披露目パーティーを開いたりしてくれたけれど、そのすべてを台無しにした。本当に、ごめ……」
最後まで言い切る前にミーシャは抱きしめられた。
「ごめんはたくさん貰ったからいらない。謝るな」
ずっと張っていた気がゆるみ、涙がこみあげてきた。泣かないように唇の端を噛む。呼吸を落ち着かせてから口を開いた。
「人が助かるなら、どう思われようとかまわなかったの。これからも私は、困っている人を見かけたら助けてしまうと思う。だけど、それだけじゃ足りない」
ミーシャは、彼の腰に手をまわし抱きしめると、顔をあげた。
「心臓が止まるとき、強く思った。リアムのことが好き。離れたくないって。これからも傍にいたいから、あなたのために私は悪い魔女ではなく皇帝にふさわしい魔女として、みんなに認めてもらえるように努力する。今度こそ、あなたの隣に立つ妃として、がんばりたい。ううん、がんばる」
リアムは真剣な顔で見つめてきた。
「大丈夫、心配ない。俺はこの国の皇帝だ。誰を妃にするのか、それは俺が決めるし、誰の指図も受けない。好きな人と一緒になるのに、民や、周りの賛成は必要ない」
ミーシャは首を横に振った。
「あなたは人々を導く希望よ。民や周りの意見を無下にしてはだめ。そんなことをしたら……オリバー大公殿下と同じ。また、悲劇を繰りかえす」
「無下にはしないし、悲劇は繰りかえさない。俺には頼れる臣下がいるし、ミーシャがいる。時間はかかるかもしれないが、みんな、きっとわかってくれる」
リアムが大丈夫というのなら本当にいつか、魔女を認めてもらえる日が訪れるかもしれないと、淡い期待が胸を過ぎった。
「リアムのおかげで元気が出てきた。だけど、それでも全員の理解を得るのは無理だと思う。そうなったときは……」
「皇帝を辞めればいい」
「……え?」
目を見張った。「身を引くとか言うなよ」と、先に釘を刺し、リアムはミーシャの額に自分の額を重ねた。