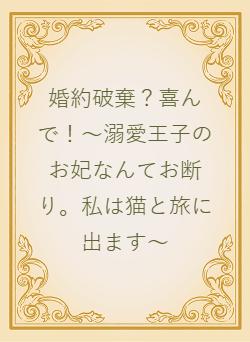「令嬢は、何度手紙を出しても断ってきた。だから、ちょうど良かったんだ。妃候補を探していると体裁さえ整えば、側近たちはそれ以上騒がないから」
ミーシャは眉をひそめた。
「つまり、婚約は私が断る前提だったということですか?」
「そうだ。だから、今回も断っていい」
リアムは深々と頭をさげた。
「体裁のためにガーネット家を利用したことは、直接会って謝りたかった。謝罪と説明が遅くなって、すまない」
王族で生まれながらに尊い存在の彼だが、幼いころから自分に非があれば、すぐに悔い改め詫びることができた。皇帝になった今もそこは変わっていなかった。
「謝罪はいりません。説明もできないほどに、陛下を避けて会わないようにしていたのは私です。こちらこそ、申し訳ございません」
手紙の差出人はリアムでも、実際、婚姻の打診をしていたのは宰相のジーンだった。本人は妃を持つ気がないと聞いていたが、そのとおりのようだ。
政略結婚は王家や貴族ではあたりまえ。そこに気持ちがないのは承知している。
ミーシャは表舞台に出たがらない、引きこもり令嬢。婚約を断ってくれる相手がよかったから選ばれたのだろう。その理由に納得したが、しかし、リアムは本当にそれでいいのだろうかと疑問に思った。
「どうして、ですか?」
リアムはもうすぐ二十六歳。一般男性なら適齢期だが、短命の王族としてはあまり悠長にしていられない歳だ。しかも、魔力の使いすぎによる害が身体に出ている。
「お言葉が過ぎるかもしれませんが、……妃を迎え、子を成すのは王家の務めかと」
グレシャー帝国は極寒の国。王族は魔力によって自然に干渉し、人が住めるように天候を操作してきた歴史がある。国を維持するためにも血は絶えてはならないはずだ。
「王族の存続なら問題ない。まだ幼いが、亡き兄の遺児がいる。少し不安定だが魔力もある皇子だ。だから、俺は皇子が大きくなって王位を継ぐまでの繋ぎ。血の繋がった息子はいなくてもいい」
「陛下は、繋ぐだけで終わってはだめです」
ミーシャは首を横に振ると、リアムに近づいた。
「先代から受け継いだものを、次世代に渡すことは大事です。でも、それだけでいいんですか?」
ミーシャは眉をひそめた。
「つまり、婚約は私が断る前提だったということですか?」
「そうだ。だから、今回も断っていい」
リアムは深々と頭をさげた。
「体裁のためにガーネット家を利用したことは、直接会って謝りたかった。謝罪と説明が遅くなって、すまない」
王族で生まれながらに尊い存在の彼だが、幼いころから自分に非があれば、すぐに悔い改め詫びることができた。皇帝になった今もそこは変わっていなかった。
「謝罪はいりません。説明もできないほどに、陛下を避けて会わないようにしていたのは私です。こちらこそ、申し訳ございません」
手紙の差出人はリアムでも、実際、婚姻の打診をしていたのは宰相のジーンだった。本人は妃を持つ気がないと聞いていたが、そのとおりのようだ。
政略結婚は王家や貴族ではあたりまえ。そこに気持ちがないのは承知している。
ミーシャは表舞台に出たがらない、引きこもり令嬢。婚約を断ってくれる相手がよかったから選ばれたのだろう。その理由に納得したが、しかし、リアムは本当にそれでいいのだろうかと疑問に思った。
「どうして、ですか?」
リアムはもうすぐ二十六歳。一般男性なら適齢期だが、短命の王族としてはあまり悠長にしていられない歳だ。しかも、魔力の使いすぎによる害が身体に出ている。
「お言葉が過ぎるかもしれませんが、……妃を迎え、子を成すのは王家の務めかと」
グレシャー帝国は極寒の国。王族は魔力によって自然に干渉し、人が住めるように天候を操作してきた歴史がある。国を維持するためにも血は絶えてはならないはずだ。
「王族の存続なら問題ない。まだ幼いが、亡き兄の遺児がいる。少し不安定だが魔力もある皇子だ。だから、俺は皇子が大きくなって王位を継ぐまでの繋ぎ。血の繋がった息子はいなくてもいい」
「陛下は、繋ぐだけで終わってはだめです」
ミーシャは首を横に振ると、リアムに近づいた。
「先代から受け継いだものを、次世代に渡すことは大事です。でも、それだけでいいんですか?」