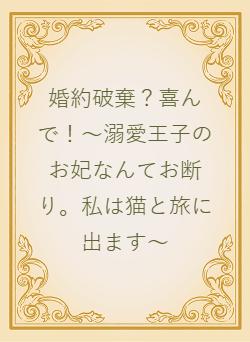「あなたが、オリバーが憎いのはね……、彼を、愛しているからよ」
リアムが身体を強張らせたのがわかった。
「憎いに決まっている。ミーシャを傷つけた。何度も、裏切られた」
「《《大好きな叔父さん》》が、私を、傷つけたから……でしょ?」
「違う!」
――手を伸ばし、彼の髪に触れたい。大丈夫だよって頭を撫でてあげたい。
どんなに願っても身体のすべてが重く、指一つ動かせない。
「仲直り、して欲しくて、ここまで来たの」
「……無理だろ」
ミーシャは「無理じゃない」と彼にほほえみかけた。
早く、オリバーを追ってもらいたい。
そう思う気持ちの反面、あと少し、一秒でも長く彼と一緒にいたかった。
「やっぱり私は、あなたの迷惑になることしか、できなかった」
「そんなことない。心配はかけさせられるが、迷惑だと思ったことはないよ」
リアムのやさしさはきっと特別製だ。
――一方の私は、勝手に飛び出して、勝手に傷ついて、大事な人を悲しませている。なんて、最低なんだろう。
……悪い魔女だから、しかたないか。
リアムを見つめ、声を絞りだして伝えた。
「悪魔女は、もう終わり。次に目を覚ましたら、あなたのためだけに生きるわ」
リアムは目を見張ったあと、切なそうに笑みを浮かべた。
「ミーシャ。もうしゃべるな。休め」
小さく、首を横に振った。
「……リアム。顔を、もっと近く」
青い魔鉱石の力で激しく降る雪に、命の炎が掻き消されていく。
――最後の瞬間まで、あなたの碧い瞳を見ていたい。
「リアム、大好き。……愛してる」
彼の瞳から、きれいな雫が産まれ、体温を失ったミーシャの頬をあたためる。
「俺は、ミーシャしか愛せない」
重ねた唇から温もりを分けてもらう。氷の皇帝が与えるものはすべてがやさしくあたたかいと思うと、ミーシャの目尻からも涙がこぼれ落ちた。
――……生きたい。死にたくない。幸せになる約束を破りたくない。この人を置いていけない。悲しませたくない。私は、死ねない……!
吹雪に負けそうな小さな火を必死に守る。抗う気持ちとは裏腹に、胸の奥で、命を刻む音が止んだ。
「……炎の魔女は、死なない」
雪降る真夜中に突然現れたオリバーは、出会った当初からミーシャを殺そうとしていた。それをわかっていて、飛びこんだ。
――これは自分が招いた結果。悪いのは全部私。だから、リアム。私が死んでも、自分を責めないで。信じて待っていて。
また必ずあなたの元へ、舞い戻るから。
リアムが身体を強張らせたのがわかった。
「憎いに決まっている。ミーシャを傷つけた。何度も、裏切られた」
「《《大好きな叔父さん》》が、私を、傷つけたから……でしょ?」
「違う!」
――手を伸ばし、彼の髪に触れたい。大丈夫だよって頭を撫でてあげたい。
どんなに願っても身体のすべてが重く、指一つ動かせない。
「仲直り、して欲しくて、ここまで来たの」
「……無理だろ」
ミーシャは「無理じゃない」と彼にほほえみかけた。
早く、オリバーを追ってもらいたい。
そう思う気持ちの反面、あと少し、一秒でも長く彼と一緒にいたかった。
「やっぱり私は、あなたの迷惑になることしか、できなかった」
「そんなことない。心配はかけさせられるが、迷惑だと思ったことはないよ」
リアムのやさしさはきっと特別製だ。
――一方の私は、勝手に飛び出して、勝手に傷ついて、大事な人を悲しませている。なんて、最低なんだろう。
……悪い魔女だから、しかたないか。
リアムを見つめ、声を絞りだして伝えた。
「悪魔女は、もう終わり。次に目を覚ましたら、あなたのためだけに生きるわ」
リアムは目を見張ったあと、切なそうに笑みを浮かべた。
「ミーシャ。もうしゃべるな。休め」
小さく、首を横に振った。
「……リアム。顔を、もっと近く」
青い魔鉱石の力で激しく降る雪に、命の炎が掻き消されていく。
――最後の瞬間まで、あなたの碧い瞳を見ていたい。
「リアム、大好き。……愛してる」
彼の瞳から、きれいな雫が産まれ、体温を失ったミーシャの頬をあたためる。
「俺は、ミーシャしか愛せない」
重ねた唇から温もりを分けてもらう。氷の皇帝が与えるものはすべてがやさしくあたたかいと思うと、ミーシャの目尻からも涙がこぼれ落ちた。
――……生きたい。死にたくない。幸せになる約束を破りたくない。この人を置いていけない。悲しませたくない。私は、死ねない……!
吹雪に負けそうな小さな火を必死に守る。抗う気持ちとは裏腹に、胸の奥で、命を刻む音が止んだ。
「……炎の魔女は、死なない」
雪降る真夜中に突然現れたオリバーは、出会った当初からミーシャを殺そうとしていた。それをわかっていて、飛びこんだ。
――これは自分が招いた結果。悪いのは全部私。だから、リアム。私が死んでも、自分を責めないで。信じて待っていて。
また必ずあなたの元へ、舞い戻るから。