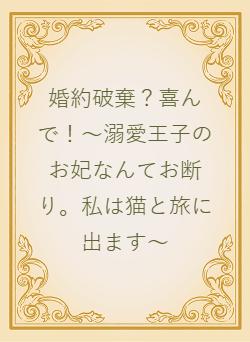「大丈夫、安心して。オリバーはとめる。ミーシャも、必ず救うから」
ミーシャを抱きしめていたリアムは、その手をゆっくりと離した。
いつもの落ち着いた声に戻っていると、ほっとしたのは一瞬だった。
白く滑らかな彼の頬に、雫の跡を見つけた。
――リアム、ごめんね。
「ナイフは、手当てが充分にできるところに移動してから抜く」
――……悲しませてばかりで、ごめん。
「……ミーシャの肌に、霜が降りている」
リアムは、ミーシャの両頬を手で包んだ。いつもと逆だ。彼の手があたたかい。
「冷たすぎる。この症状、凍化だ。どうしてミーシャが?」
彼は冷たいと言うが、もう、寒さの感覚がなかった。
凍化病がこんなにもつらく、怖く、寂しいのかと驚いた。
長くこの病に苦しんできたリアムや王族のことを思って、胸が締めつけられる。
喉がひりひりと痛い。吐く息は白く、きらきらと凍っていく。まるで、氷の魔女になった気分だと、こんなときなのに小さく笑った。
リアムはミーシャの背中を見た。
「サファイア魔鉱石が原因? 待ってろ、すぐにとめる」
やさしく抱きしめながら、彼は背中のナイフに触れた。
「イライジャが手紙を寄こした。俺はサファイア魔鉱石を操れるらしい。ミーシャが凍るのを止められないか試してみたかったが、魔鉱石の部分が体内に埋没している……」
――つまり、触れないということだろうか?
ミーシャには氷への耐性がない。魔鉱石は奪われ、魔力も尽きた。凍化を今すぐに止められなければもう……。
重たい瞼を閉じた。すると、銀色の世界が浮かんだ。まるで、リアムの髪の色のようだ。
美しい雪の上に舞い降りた、炎の鳥の朱い灯火がゆっくりと、小さくなっていく。
「リアム、聞いて……」
――二度も、残していく駄目な師匠でごめん。許してなんて言わない。
その代わりに、ちゃんと彼に伝えたい。
ミーシャを抱きしめていたリアムは、その手をゆっくりと離した。
いつもの落ち着いた声に戻っていると、ほっとしたのは一瞬だった。
白く滑らかな彼の頬に、雫の跡を見つけた。
――リアム、ごめんね。
「ナイフは、手当てが充分にできるところに移動してから抜く」
――……悲しませてばかりで、ごめん。
「……ミーシャの肌に、霜が降りている」
リアムは、ミーシャの両頬を手で包んだ。いつもと逆だ。彼の手があたたかい。
「冷たすぎる。この症状、凍化だ。どうしてミーシャが?」
彼は冷たいと言うが、もう、寒さの感覚がなかった。
凍化病がこんなにもつらく、怖く、寂しいのかと驚いた。
長くこの病に苦しんできたリアムや王族のことを思って、胸が締めつけられる。
喉がひりひりと痛い。吐く息は白く、きらきらと凍っていく。まるで、氷の魔女になった気分だと、こんなときなのに小さく笑った。
リアムはミーシャの背中を見た。
「サファイア魔鉱石が原因? 待ってろ、すぐにとめる」
やさしく抱きしめながら、彼は背中のナイフに触れた。
「イライジャが手紙を寄こした。俺はサファイア魔鉱石を操れるらしい。ミーシャが凍るのを止められないか試してみたかったが、魔鉱石の部分が体内に埋没している……」
――つまり、触れないということだろうか?
ミーシャには氷への耐性がない。魔鉱石は奪われ、魔力も尽きた。凍化を今すぐに止められなければもう……。
重たい瞼を閉じた。すると、銀色の世界が浮かんだ。まるで、リアムの髪の色のようだ。
美しい雪の上に舞い降りた、炎の鳥の朱い灯火がゆっくりと、小さくなっていく。
「リアム、聞いて……」
――二度も、残していく駄目な師匠でごめん。許してなんて言わない。
その代わりに、ちゃんと彼に伝えたい。