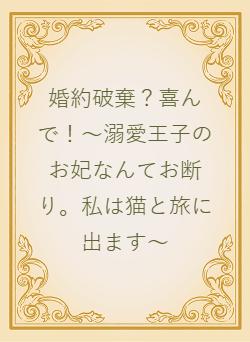「このままなんて、私は絶対、嫌!」
ミーシャはリアムの頭を両手で持つと、自分の肩から彼を引き離した。そのまま彼の唇を自分の唇で塞ぐと、魔力を吹き込んだ。
虚ろだった彼の瞳に光が戻る。
「リアム。お互い相手のためにって、がまんするのはもう、やめましょう」
ミーシャは冷たいリアムの左手を掴み、自分の頬に触れさせた。
「触れたければ触れていい。湯たんぽ代わり、喜んで引き受ける。もう、離してなんて言わない。拒否したりしない。だからお願い」
リアムはじっとミーシャを見たあと、手の中にある魔鉱石に視線を移した。彼の肩に手を置いて、説得を続ける。
「あなたのために作ったんだよ、大丈夫。もし、暴走しても私が止めてあげる。受けとめるから心配しなくてい……ちょっと、リアム。なんで笑ってる? 人が真剣に話しているのに!」
下を向いたまま彼は、肩を微かに揺らし、笑い声を堪えていた。
「ごめん。必死なミーシャが愛しいと思って」
「……一生懸命な人を見て笑っていいなんて、私、弟子に教えてないわよ」
リアムは楽しそうに「ごめん」と謝ったあと、自分の左手の甲をミーシャに見せた。
「見て。霜がなくなった」
「本当。消えてる……」
初めて会ったときは、しばらく触れてもなかなか温まらず、暖炉に火を入れて、炎の鳥を呼んでやっと霜は溶け、体温が戻った。今回は短い時間で消えて驚いた。
「俺のために、魔鉱石を作ってくれてありがとう。だが、やはり俺には必要ない。どうやらミーシャがいれば、凍化の進行は止まるみたいだ」
「どういうこと……?」
「今度は俺が『大丈夫』って言う番だね。信じて。本当に今、心も身体も温かくて、満たされている」
リアムは「確かめてみて」と言って、ミーシャの手を自分の胸に当てた。以前触れたときよりも体温は高く、鼓動もしっかりと伝わってきた。
「ここには火も、炎の鳥もいない。ミーシャが俺に気持ちをくれたことで、……ミーシャを想うことで凍化が止まった。これまでなにがあっても熱くならなかった心が、きみを、ミーシャを愛しいと思うたびに胸を熱くする」
ミーシャはリアムを見た。