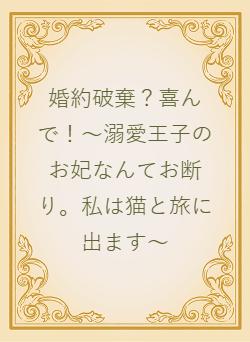した。
ミーシャはすぐに、炎の鳥を呼び寄せた。水を飲んでしまったらしく咽せる彼の背に手を当てる。
「その髪色……」
リアムは、濡れたままのミーシャの髪に触れた。
「クレアと同じ、朱い、ガーネット色だ」
もう、隠す必要もない。彼にほほえみかけると、告白した。
「私。実は、クレアの生まれ変わりなの。前世の記憶があるってことをね、打ち明けようと、思ってた」
ミーシャは震える手で、服の中に隠していた魔鉱石をリアムに見せた。
「だけど全然魔力はなくて。リアムがオリバー大公を追いかけて行ったあと、白狼くんがあらわれて、私にくれたの。魔鉱石に触れたら、髪色も、魔力もすべて元に戻った」
なぜかはわからないけれど、と説明を続けようとしたら、リアムはミーシャの肩を掴んだ。
「本当に、師匠なのか?」
事実かどうか見極めようと、碧い瞳がじっと自分を見つめてくる。
ミーシャは答える代わりに、彼と自分の髪や服を瞬時に乾かした。そのあと、彼に向かって頭をさげた。
「今まで黙っていて、ごめんなさい」
「なぜ、もっと早く打ち明けてくれなかった?」
彼の切羽詰まった低い声に、息を吞む。
つらそうに歪めるリアムの顔を見て、ミーシャの胸は張り裂けそうなほど痛んだ。
「クレアの存在は、あなたの足枷になると、思っていたからです」
「足枷?」
ミーシャはこくりと頷いた。
「私は悪い魔女だか……、」
「師匠は悪い魔女じゃない!」
リアムの力が暴走し、二人の周りに氷塊が発生した。
「俺が! どれだけ師匠に会いたくて、失ったことが悔しくて悲しかったか……!」
リアムの言葉が胸に刺さる。ミーシャはもう一度、深く頭をさげるしかできなかった。
「魔力がない師匠では、あなたになにもしてあげられない。それどころか、悪い魔女の私を庇って、リアムは立場を悪くすると思ったの。前世クレアを恥じていたし、罪の意識に捕らわれ、償うことしか考えていなかった。負担をかけたくない。そればっかりで、あなたの気持ちをくみ取る余裕が、なかったの」
ごめんなさい。と伝えると涙がこみあげてきたが、自分に泣く資格はないとミーシャは歯を食いしばった。
立ちあがると、リアムから離れ、周りの氷を溶かした。
魔鉱石を高くかざし、炎の精霊獣を呼び寄せる。自分より大きな炎の鳥にミーシャは頬をすり寄せると、目を見て伝えた。
「炎の鳥。お願い。この石に宿り、私の愛しい人を温め続けて」
炎の鳥は朱く燃える翼を一度大きく広げ羽ばたくと、そのまま姿形を歪め、魔鉱石の中に吸いこまれるように溶けていった。
ミーシャは魔鉱石にキスをすると、リアムに向きなおった。
真っ赤に炎のような輝きを放つ宝石を、ミーシャは差しだした。
「リアム。氷を操る要領よ。炎の鳥を呼び出してみて」
魔鉱石を握らせながら、昔、言った台詞を口にした。
彼の顔が切なく歪む。魔鉱石をぎゅっと握ったあと、リアムはミーシャを抱きしめた。
「……本当に、師匠なんだ」
「うん。私のかわいいリアム」
囁くように伝えると、自分の背に回されているリアムの手が微かに震えた。
リアムは息を吐くと、言葉を紡ぎはじめた。
「ずっと、師匠を守れなかったことを後悔していた。何度も何度も夢の中であやまった。だけど足りなくて、苦しくて、寂しくて悲しかった。師匠……ごめん。そして、あのとき助けてくれて、ありがとう」
リアムの気持ちが痛いほど伝わってくる。ミーシャはリアムの背に手を回し、ぎゅっと抱きしめかえした。
涙で歪む、彼の肩越しに見あげた空はもう、白みはじめていた。
長い夜だった。そう思いながら、師匠として最後の言葉を彼に伝えた。
「私はリアムを傷つけたかったんじゃない。あなたを生かすことに必死だったの。守れたらそれでいいって。自分のことはどうでもよかった。一人残されるリアムが、どれだけ悲しみを抱えるのか、想像できなかった。つらい思いをさせて、ごめんなさい。……私の願いを叶えてくれて、今まで、生きてくれて……本当に、ありがとう」
魔鉱石を手放し、髪色がいつもの朱鷺色に戻ったミーシャは、リアムにほほえみかけた。
ミーシャはすぐに、炎の鳥を呼び寄せた。水を飲んでしまったらしく咽せる彼の背に手を当てる。
「その髪色……」
リアムは、濡れたままのミーシャの髪に触れた。
「クレアと同じ、朱い、ガーネット色だ」
もう、隠す必要もない。彼にほほえみかけると、告白した。
「私。実は、クレアの生まれ変わりなの。前世の記憶があるってことをね、打ち明けようと、思ってた」
ミーシャは震える手で、服の中に隠していた魔鉱石をリアムに見せた。
「だけど全然魔力はなくて。リアムがオリバー大公を追いかけて行ったあと、白狼くんがあらわれて、私にくれたの。魔鉱石に触れたら、髪色も、魔力もすべて元に戻った」
なぜかはわからないけれど、と説明を続けようとしたら、リアムはミーシャの肩を掴んだ。
「本当に、師匠なのか?」
事実かどうか見極めようと、碧い瞳がじっと自分を見つめてくる。
ミーシャは答える代わりに、彼と自分の髪や服を瞬時に乾かした。そのあと、彼に向かって頭をさげた。
「今まで黙っていて、ごめんなさい」
「なぜ、もっと早く打ち明けてくれなかった?」
彼の切羽詰まった低い声に、息を吞む。
つらそうに歪めるリアムの顔を見て、ミーシャの胸は張り裂けそうなほど痛んだ。
「クレアの存在は、あなたの足枷になると、思っていたからです」
「足枷?」
ミーシャはこくりと頷いた。
「私は悪い魔女だか……、」
「師匠は悪い魔女じゃない!」
リアムの力が暴走し、二人の周りに氷塊が発生した。
「俺が! どれだけ師匠に会いたくて、失ったことが悔しくて悲しかったか……!」
リアムの言葉が胸に刺さる。ミーシャはもう一度、深く頭をさげるしかできなかった。
「魔力がない師匠では、あなたになにもしてあげられない。それどころか、悪い魔女の私を庇って、リアムは立場を悪くすると思ったの。前世クレアを恥じていたし、罪の意識に捕らわれ、償うことしか考えていなかった。負担をかけたくない。そればっかりで、あなたの気持ちをくみ取る余裕が、なかったの」
ごめんなさい。と伝えると涙がこみあげてきたが、自分に泣く資格はないとミーシャは歯を食いしばった。
立ちあがると、リアムから離れ、周りの氷を溶かした。
魔鉱石を高くかざし、炎の精霊獣を呼び寄せる。自分より大きな炎の鳥にミーシャは頬をすり寄せると、目を見て伝えた。
「炎の鳥。お願い。この石に宿り、私の愛しい人を温め続けて」
炎の鳥は朱く燃える翼を一度大きく広げ羽ばたくと、そのまま姿形を歪め、魔鉱石の中に吸いこまれるように溶けていった。
ミーシャは魔鉱石にキスをすると、リアムに向きなおった。
真っ赤に炎のような輝きを放つ宝石を、ミーシャは差しだした。
「リアム。氷を操る要領よ。炎の鳥を呼び出してみて」
魔鉱石を握らせながら、昔、言った台詞を口にした。
彼の顔が切なく歪む。魔鉱石をぎゅっと握ったあと、リアムはミーシャを抱きしめた。
「……本当に、師匠なんだ」
「うん。私のかわいいリアム」
囁くように伝えると、自分の背に回されているリアムの手が微かに震えた。
リアムは息を吐くと、言葉を紡ぎはじめた。
「ずっと、師匠を守れなかったことを後悔していた。何度も何度も夢の中であやまった。だけど足りなくて、苦しくて、寂しくて悲しかった。師匠……ごめん。そして、あのとき助けてくれて、ありがとう」
リアムの気持ちが痛いほど伝わってくる。ミーシャはリアムの背に手を回し、ぎゅっと抱きしめかえした。
涙で歪む、彼の肩越しに見あげた空はもう、白みはじめていた。
長い夜だった。そう思いながら、師匠として最後の言葉を彼に伝えた。
「私はリアムを傷つけたかったんじゃない。あなたを生かすことに必死だったの。守れたらそれでいいって。自分のことはどうでもよかった。一人残されるリアムが、どれだけ悲しみを抱えるのか、想像できなかった。つらい思いをさせて、ごめんなさい。……私の願いを叶えてくれて、今まで、生きてくれて……本当に、ありがとう」
魔鉱石を手放し、髪色がいつもの朱鷺色に戻ったミーシャは、リアムにほほえみかけた。