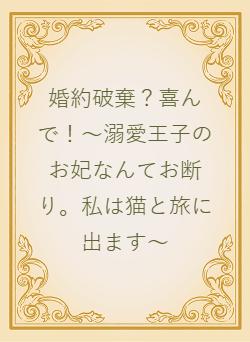「私は師匠失格です。とても、弟子の前には出られない。彼の病が完治すれば、国に帰ろうと最初から決めていました」
「国に帰るつもりだというお考えは、陛下は、ご存じですの?」
「もちろん。そういう契約、条件で私はこの国に参りましたので」
ナタリーは押し黙ってしばらく考え込んだあと、顔をあげた。
「ミーシャさまは、師匠の立場とリアムさまの幸せ、どちらが大事ですか?」
今度はミーシャが黙った。
「リアムさまのことを、どう思っていらっしゃるのですか? 今も、かわいい弟子ですか?」
首を横に振る。
「陛下は人柄もとても立派になられました。弟子だとは思っていません。誰よりも尊敬している、大切な人です」
そう答えると、ナタリーは表情を和らげた。
「よかった。弟子だと思っていらっしゃるのなら、私、あなたさまの正体を陛下にお伝えするところでしたわ。……ミーシャさまも陛下がお好きなのですね」
『陛下が好き』に反応して、勝手に顔が熱くなった。それを見たナタリーはくすっと笑い、そして、悲しそうにほほえんだ。
「わたくし以前、陛下の心を占める人はクレアさまだけと申しました。けれど、どうやら違ったようです。いえ、変わったんだと思います。陛下は、ミーシャさまを求めています。正妃にならないと申さず、どうか、求めに答えて受け止めて差しあげてくださいませ」
ミーシャは彼女から視線を逸らし、自分の手を見つめた。
「この手は、血に染まっています。私はずっと、クレアの存在を消して欲しいと願っていました。忘れさせ、他に目を向けさせることが彼の幸せに繋がると、疑いもしなかった」
師匠として迎えた最後の瞬間、血塗られた手で、彼に触れてはいけない。穢してはならないと思った。
手を固く握ると、ライリーがそっと、手を重ねた。
「ミーシャさま。それは違います。この手は、人を想い、がんばる手です。血に染まってなどいません。あるのは、希望です。陛下を幸せにして差しあげられる人は、ミーシャさましかいませんよ」
「ライリー……」
――呪いではなく、祝福を。
フルラを発つとき、エレノアにかけられた言葉が浮かんだ。
「国に帰るつもりだというお考えは、陛下は、ご存じですの?」
「もちろん。そういう契約、条件で私はこの国に参りましたので」
ナタリーは押し黙ってしばらく考え込んだあと、顔をあげた。
「ミーシャさまは、師匠の立場とリアムさまの幸せ、どちらが大事ですか?」
今度はミーシャが黙った。
「リアムさまのことを、どう思っていらっしゃるのですか? 今も、かわいい弟子ですか?」
首を横に振る。
「陛下は人柄もとても立派になられました。弟子だとは思っていません。誰よりも尊敬している、大切な人です」
そう答えると、ナタリーは表情を和らげた。
「よかった。弟子だと思っていらっしゃるのなら、私、あなたさまの正体を陛下にお伝えするところでしたわ。……ミーシャさまも陛下がお好きなのですね」
『陛下が好き』に反応して、勝手に顔が熱くなった。それを見たナタリーはくすっと笑い、そして、悲しそうにほほえんだ。
「わたくし以前、陛下の心を占める人はクレアさまだけと申しました。けれど、どうやら違ったようです。いえ、変わったんだと思います。陛下は、ミーシャさまを求めています。正妃にならないと申さず、どうか、求めに答えて受け止めて差しあげてくださいませ」
ミーシャは彼女から視線を逸らし、自分の手を見つめた。
「この手は、血に染まっています。私はずっと、クレアの存在を消して欲しいと願っていました。忘れさせ、他に目を向けさせることが彼の幸せに繋がると、疑いもしなかった」
師匠として迎えた最後の瞬間、血塗られた手で、彼に触れてはいけない。穢してはならないと思った。
手を固く握ると、ライリーがそっと、手を重ねた。
「ミーシャさま。それは違います。この手は、人を想い、がんばる手です。血に染まってなどいません。あるのは、希望です。陛下を幸せにして差しあげられる人は、ミーシャさましかいませんよ」
「ライリー……」
――呪いではなく、祝福を。
フルラを発つとき、エレノアにかけられた言葉が浮かんだ。