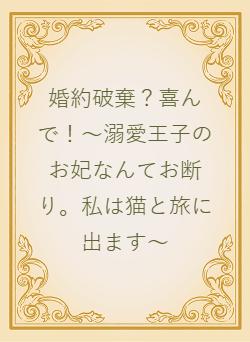「わたくしは、幼いころから将来は陛下を支える妃になると聞かされて育ち、わたくし自身もそうなりたいと望んで、生きてきました」
「ナタリー、でも俺は……、」
「陛下の心にクレアさまがいるのは知っています。それでも私はかまいません……傍で、陛下を支えることがわたくしの幸せですから」
ジーンは、ミーシャを求めてしまう感情を恋だという。
相手を想う気持ちがわかるからこそ、ナタリーの言葉がリアムの胸を締め付ける。
「ナタリー。きみの気持ちはわかった。だが、どれだけ俺を想ってくれても、その気持ちに応えることはできない」
ナタリーは息を吞むと、下を向いた。
「俺は、誰かに支えて欲しいんじゃない。大切な人たちを支えたいと思っている。守るだけじゃなく、みんなを、できるだけ幸せにしたい。もちろんナタリーのことも。だけど、ごめん。きみの望む幸せは、叶えてあげられない」
想いを伝えるのは、とても勇気がいる。
だからこそ、最大限の敬意を示すべきだ。淡い期待を持たせるような中途半端な返答はしたくなかった。
「俺がこの手で幸せにしたいと思うのは、ミーシャだけだ。この命続く限り、彼女に俺の傍にいて欲しい。いつも、笑っていて欲しいと願っている」
ナタリーは、一度深く息をはくと、顔をあげた。
「陛下。……クレアさまのことは、忘れられそうですか?」
「それは、無理だろうね」
「それでも、彼女を選ぶと」
「ミーシャが嫌じゃなければ」
ナタリーはふっと、肩の力を抜いた。
「陛下、勝手ですね」
「きみの兄曰く、恋とは自分勝手でいいそうだ」
一瞬驚いたあと、彼女は小さく笑った。
「正直、薄々と、わかっておりました。陛下の言葉で言っていただけて、すっきりしましたわ。……ありがとうございます」
ゆっくりと長く、ナタリーは頭をさげた。
「気持ちは、簡単には吹っ切れませんが、陛下への忠誠心は、かわりません。わがアルベルト家が力になれることがあれば、なんなりと申してくださいませ」
「ありがとう。恩にきる」
顔をあげた彼女の頬はぬれていた。
「陛下。近々、カルディアに赴くと兄から聞きました。差しでがましいことを申しますが、陛下が留守の間、ミーシャさまをアルベルトの者にも守らせていただけませんか?」
「きみの心づかいは感謝する。だが、それには及ばない。ミーシャは、一緒に連れて行く」
ナタリーは目を見張った。
「彼女が、魔女だからですか?」
「魔女だから連れて行くと言うより、ここに置いていっても危険だからだ」
ナタリーは、下を向いて逡巡したあともう一度リアムを見た。
「陛下、ミーシャさまにお会いする許可をいただいてもよろしいでしょうか? カルディアに向かう前に、お話をしておきたいと思います」
「許可しよう。ただ、彼女は部屋にいないかもしれない」
「自分で探しますから、大丈夫ですわ」
ナタリーはカーテシーをすると、もう一度リアムを見た。
「リアムさま。どうか、……幸せになってくださいね」
にこりとほほえみを残し背を向けた彼女を、リアムは黙って見送った。