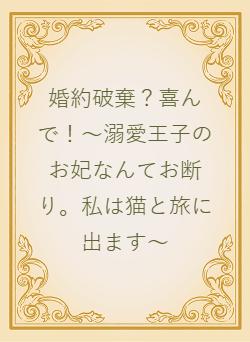「そうですか? 私はあなたさまの護衛として、幾日か仕えさせていただきました。侍女含め、少々浮かれているようにお見受けいたします」
言葉の刃が返ってきて、ミーシャはその場から動けなくなった。
「陛下は恋愛に興味がなく、本来、女性を口説くようなかたではありません。では、なぜパーティーなどの公衆の面前で、ミーシさまを寵姫と言ったのか、おわかりになりますか?」
「魔女の私をおそれるな、危害を加えるな。という意思表示。私を、心配してのことです」
イライジャは頷いた。
「陛下から寵愛を受けている者に、誰も手を出せない。政略結婚で、今はミーシャさまが陛下の妃ですが、本来ならナタリーさまこそふさわしい。白い結婚期間が終わり、陛下に必要とされなくなったとき、つらいのはあなたさま自身です」
ミーシャは一度、冷たい空気を深く吸った。手をぎゅっと握ると、顔をあげた。
「イライジャさまの仰るとおりです。陛下にはナタリーさまがお似合いです。私は、もとより陛下の特別な存在になるつもりはありません」
そもそも、今のミーシャは魔力も少ない小娘。朱鷺色の髪はよく褒められ、気に入られているがそれだけ。いくらきれいに着飾ろうと、リアムの目に留まることはない。
「本物の寵姫になるつもりがないのなら、けっこうです。陛下の言葉は、あなたを守るためのもの。そこに、気持ちがあるわけではないのですから」
リアムとの関係は仮初め。彼の寵姫発言は、『魔女の評判をよくする』と、契約を交わしたから。だけど……。
「陛下の言葉は、私を守るためのものですが、そこに気持ちが、まったくないとは思いません」
ミーシャは姿勢を正すとイライジャをまっすぐ見つめた。
「陛下は誰よりもやさしい。自分のことは後まわしにして民や私のことを考えてくださっている。だからこそ、あの人が私を必要としてくれるのなら、全力で応えたいと思っています」
傍にいてくれたらそれでいいと、リアムは言った。彼の放つ言葉に偽りなどあるはずがない。
イライジャは目を見開いていた。視線を泳がせてからミーシャを見つめた。
「……傷つくことになっても知りませんよ」
「覚悟の上です」
「陛下を、万が一傷つけるようなことがあれば、私はあなたを許しません」
「心に留めておきます」
にこりとほほえむと、彼に背を向けた。
「イライジャさま。もうすぐ日が暮れます。雪かきを急ぎましょう」
しゃがんで、震える手でそっと、雪に触れた。
――冷たい。
リアムは心にもないことは口にしたり、人を騙したり、利用するために嘘をついたりしない。
まっすぐな人だと知っているからこそ、ミーシャは、もらった甘い言葉に動揺した。
ただ、彼からもらった言葉は、雪結晶のようなもので、美しいが儚い。いずれ溶けて消える幻だ。
――それでいい。彼の胸にも自分の胸にも、想いは残してはだめだから。
下を向いたまま雪を手でかき分ける。
顔をあげて、もう一度バルコニーを見る勇気は、ミーシャにはなかった。
言葉の刃が返ってきて、ミーシャはその場から動けなくなった。
「陛下は恋愛に興味がなく、本来、女性を口説くようなかたではありません。では、なぜパーティーなどの公衆の面前で、ミーシさまを寵姫と言ったのか、おわかりになりますか?」
「魔女の私をおそれるな、危害を加えるな。という意思表示。私を、心配してのことです」
イライジャは頷いた。
「陛下から寵愛を受けている者に、誰も手を出せない。政略結婚で、今はミーシャさまが陛下の妃ですが、本来ならナタリーさまこそふさわしい。白い結婚期間が終わり、陛下に必要とされなくなったとき、つらいのはあなたさま自身です」
ミーシャは一度、冷たい空気を深く吸った。手をぎゅっと握ると、顔をあげた。
「イライジャさまの仰るとおりです。陛下にはナタリーさまがお似合いです。私は、もとより陛下の特別な存在になるつもりはありません」
そもそも、今のミーシャは魔力も少ない小娘。朱鷺色の髪はよく褒められ、気に入られているがそれだけ。いくらきれいに着飾ろうと、リアムの目に留まることはない。
「本物の寵姫になるつもりがないのなら、けっこうです。陛下の言葉は、あなたを守るためのもの。そこに、気持ちがあるわけではないのですから」
リアムとの関係は仮初め。彼の寵姫発言は、『魔女の評判をよくする』と、契約を交わしたから。だけど……。
「陛下の言葉は、私を守るためのものですが、そこに気持ちが、まったくないとは思いません」
ミーシャは姿勢を正すとイライジャをまっすぐ見つめた。
「陛下は誰よりもやさしい。自分のことは後まわしにして民や私のことを考えてくださっている。だからこそ、あの人が私を必要としてくれるのなら、全力で応えたいと思っています」
傍にいてくれたらそれでいいと、リアムは言った。彼の放つ言葉に偽りなどあるはずがない。
イライジャは目を見開いていた。視線を泳がせてからミーシャを見つめた。
「……傷つくことになっても知りませんよ」
「覚悟の上です」
「陛下を、万が一傷つけるようなことがあれば、私はあなたを許しません」
「心に留めておきます」
にこりとほほえむと、彼に背を向けた。
「イライジャさま。もうすぐ日が暮れます。雪かきを急ぎましょう」
しゃがんで、震える手でそっと、雪に触れた。
――冷たい。
リアムは心にもないことは口にしたり、人を騙したり、利用するために嘘をついたりしない。
まっすぐな人だと知っているからこそ、ミーシャは、もらった甘い言葉に動揺した。
ただ、彼からもらった言葉は、雪結晶のようなもので、美しいが儚い。いずれ溶けて消える幻だ。
――それでいい。彼の胸にも自分の胸にも、想いは残してはだめだから。
下を向いたまま雪を手でかき分ける。
顔をあげて、もう一度バルコニーを見る勇気は、ミーシャにはなかった。