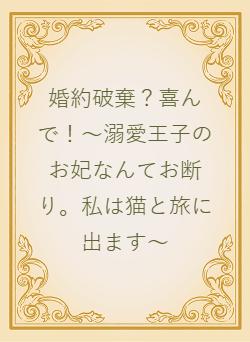「い、偉大なる皇帝陛下、ごきげん麗しゅうございます。拝謁、誠に……」
「格式張った礼は抜きでいい、アルベルト夫人。突然の訪問、こちらこそお許しを」
彼女は最初、いきなり現われた息子と陛下に驚いていたが、今は弱々しく笑っている。
「わざわざお越しいただき、誠にありがとうございます」
アルベルト夫人は深く頭をさげた。
「エルビィス先生は?」
「ずっと、意識がないままですわ」
ベッドの傍に近寄り、眠っている恩師の顔を見る。
エルビィスとの付き合いも長い。幼少期、フルラ国に留学という『人質』になる前からだ。
クレア師匠がこの世を去り、国に戻ってからは学問を中心に帝王学について彼からたくさんのことを教わった。失いたくない大事な人だ。
呼吸は安定しているが、目はくぼみ、顔色はよくない。壮健だったころの彼の笑顔を思い出した瞬間、目頭が熱くなった。
「会話は、無理そうですね」
「最近は寝ていることが多くなりました。ですが、ずいぶん前に陛下への言伝は承っております」
「……母上、僕には?」
ジーンが割って入って訊いた。
「あなたには『陛下を支えよ。息災でがんばれ』だけですわね」
ジーンは「それだけ?」と言って、肩を落とした。
「……まあ、親父らしいけどね」
「それだけおまえを信じているんだろ」
肩に手を置いて励ますと、下を向いていたジーンは顔をあげた。
「……陛下との会話を中断して誠に失礼いたしました」
ジーンは父を前にした息子ではなく臣下の顔に戻ると、一礼のあと後ろへさがった。リアムもベッドから離れ、夫人が勧めてくれた椅子に座る。
「エルビィス先生の伝言を聞こう」
「はい。主人は、『親友オリバーを止められず、すまない』と謝っておりました」
「格式張った礼は抜きでいい、アルベルト夫人。突然の訪問、こちらこそお許しを」
彼女は最初、いきなり現われた息子と陛下に驚いていたが、今は弱々しく笑っている。
「わざわざお越しいただき、誠にありがとうございます」
アルベルト夫人は深く頭をさげた。
「エルビィス先生は?」
「ずっと、意識がないままですわ」
ベッドの傍に近寄り、眠っている恩師の顔を見る。
エルビィスとの付き合いも長い。幼少期、フルラ国に留学という『人質』になる前からだ。
クレア師匠がこの世を去り、国に戻ってからは学問を中心に帝王学について彼からたくさんのことを教わった。失いたくない大事な人だ。
呼吸は安定しているが、目はくぼみ、顔色はよくない。壮健だったころの彼の笑顔を思い出した瞬間、目頭が熱くなった。
「会話は、無理そうですね」
「最近は寝ていることが多くなりました。ですが、ずいぶん前に陛下への言伝は承っております」
「……母上、僕には?」
ジーンが割って入って訊いた。
「あなたには『陛下を支えよ。息災でがんばれ』だけですわね」
ジーンは「それだけ?」と言って、肩を落とした。
「……まあ、親父らしいけどね」
「それだけおまえを信じているんだろ」
肩に手を置いて励ますと、下を向いていたジーンは顔をあげた。
「……陛下との会話を中断して誠に失礼いたしました」
ジーンは父を前にした息子ではなく臣下の顔に戻ると、一礼のあと後ろへさがった。リアムもベッドから離れ、夫人が勧めてくれた椅子に座る。
「エルビィス先生の伝言を聞こう」
「はい。主人は、『親友オリバーを止められず、すまない』と謝っておりました」