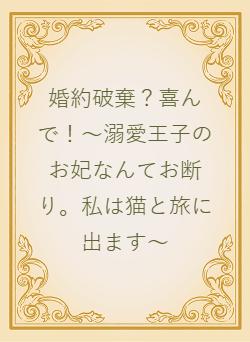「ジーン。おまえもついてこい」
単独行動すると前回のようにまた怒られるため、ジーンを誘った。彼は真剣な顔で「昼過ぎまでには帰りますよ」と答え、出かける準備をはじめた。
宮殿の外へ行くには雪降る庭を突っ切ると近道だ。足早に歩いていたリアムはふと、止まった。
粉雪が舞う先、自室の二階のバルコニーに、侍女と笑い合っているミーシャの姿があった。
彼女の手には、昨夜贈ったスノードームがある。振ったり空にかざしたりして、にこにこしている。
『陛下からの雪のプレゼント、とても嬉しいです』
満面の笑顔で喜んでいるミーシャの姿が脳裏に浮かんだ。
『リアム。魔力をコントロールしたければ、自分を否定してはいけません。力は抑えようとせずに、外へ。自分のためではなく人のために使うといいですよ。そしたらきっと、あなたは……――』
楽しそうにしている彼女を見て、クレア師匠の言葉を思い出した。
王位も、結婚も、自身の幸せについても興味がない。
今生きているのは、師匠の教えがあるからだ。なりたくなかった皇帝という立場と、もとから授かった魔力は人のために使う。
リアムは流氷の結界を張って人々を守った結果、身体が内側から凍り滅んでも、かまわなかった。
突然、頭上から羽音が聞こえてリアムは振り向き、仰ぎ見た。
白い曇天の空を、赤く燃えながら飛んできたのは炎の鳥だ。手を高くかざすと、ふわりと留まった。
単独行動すると前回のようにまた怒られるため、ジーンを誘った。彼は真剣な顔で「昼過ぎまでには帰りますよ」と答え、出かける準備をはじめた。
宮殿の外へ行くには雪降る庭を突っ切ると近道だ。足早に歩いていたリアムはふと、止まった。
粉雪が舞う先、自室の二階のバルコニーに、侍女と笑い合っているミーシャの姿があった。
彼女の手には、昨夜贈ったスノードームがある。振ったり空にかざしたりして、にこにこしている。
『陛下からの雪のプレゼント、とても嬉しいです』
満面の笑顔で喜んでいるミーシャの姿が脳裏に浮かんだ。
『リアム。魔力をコントロールしたければ、自分を否定してはいけません。力は抑えようとせずに、外へ。自分のためではなく人のために使うといいですよ。そしたらきっと、あなたは……――』
楽しそうにしている彼女を見て、クレア師匠の言葉を思い出した。
王位も、結婚も、自身の幸せについても興味がない。
今生きているのは、師匠の教えがあるからだ。なりたくなかった皇帝という立場と、もとから授かった魔力は人のために使う。
リアムは流氷の結界を張って人々を守った結果、身体が内側から凍り滅んでも、かまわなかった。
突然、頭上から羽音が聞こえてリアムは振り向き、仰ぎ見た。
白い曇天の空を、赤く燃えながら飛んできたのは炎の鳥だ。手を高くかざすと、ふわりと留まった。