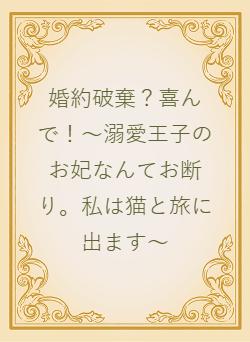「怖い夢でも見たのか?」
思考の海に沈んでいたミーシャは声をかけられ、ぱっと顔をあげた。目を覚ましたリアムと目が合って、また、心臓がかってに跳ねた。
「陛下、おはようございます」
「難しい顔をしていた」
「……寝坊したと思っていたんです」
「俺も寝坊だ。温かくて、起きられない」
「まだ寝ててください。そのほうが身体は回復します」
リアムはミーシャに手を伸ばした。なんだろうと前屈みになると、首の後ろを手がまわり、引き寄せられた。
「ちょっ、陛下?」
「その台詞、そっくりきみに返す。魔力を使いすぎているだろう。休め」
近すぎる。離れようと手で彼の胸を押したが、びくともしない。猫を相手しているみたいに、リアムの大きな手が頭をよしよしと撫でている。
「私は、炎の鳥から魔力をもらえるんです。だから、大丈夫です!」
「だったら、炎の鳥で俺を温めて」
そんなことを言われたら断れない。ミーシャは抵抗するのをやめて、リアムの腕の中に大人しく収まった。
「わかりました。いいですよ。私、陛下のぬいぐるみですし。これからは懐炉にもなります」
「懐炉か。たしかに温かくて、手放せなくなりそうだ」
いままでは、同じ寝台を使ってもただの添い寝だったが、オリバー大公殿下が生きていたとわかってからは、ミーシャを抱きしめることに躊躇がなくなった。
おかげで心臓は朝から全力稼働だ。これは治療、自分は人間懐炉だと、何度も言い聞かせる。
おだやかな声で話すリアムとは違い、ミーシャはいつまでもこの状況に慣れないでいた。
――治療に前向きになったというよりは、私を、クレアと重ねているのかも。
よくないな。と思いながらも彼を拒むことはできないし、したくない。
「いつも言っているが、なにか不便があれば遠慮はいらないから」
「ありがとうございます」
とくとくと彼の心音が聞こえる。
昨夜のリアムは無茶しそうで心配だったが、今は落ち着いている。ひとまず安堵した。
思考の海に沈んでいたミーシャは声をかけられ、ぱっと顔をあげた。目を覚ましたリアムと目が合って、また、心臓がかってに跳ねた。
「陛下、おはようございます」
「難しい顔をしていた」
「……寝坊したと思っていたんです」
「俺も寝坊だ。温かくて、起きられない」
「まだ寝ててください。そのほうが身体は回復します」
リアムはミーシャに手を伸ばした。なんだろうと前屈みになると、首の後ろを手がまわり、引き寄せられた。
「ちょっ、陛下?」
「その台詞、そっくりきみに返す。魔力を使いすぎているだろう。休め」
近すぎる。離れようと手で彼の胸を押したが、びくともしない。猫を相手しているみたいに、リアムの大きな手が頭をよしよしと撫でている。
「私は、炎の鳥から魔力をもらえるんです。だから、大丈夫です!」
「だったら、炎の鳥で俺を温めて」
そんなことを言われたら断れない。ミーシャは抵抗するのをやめて、リアムの腕の中に大人しく収まった。
「わかりました。いいですよ。私、陛下のぬいぐるみですし。これからは懐炉にもなります」
「懐炉か。たしかに温かくて、手放せなくなりそうだ」
いままでは、同じ寝台を使ってもただの添い寝だったが、オリバー大公殿下が生きていたとわかってからは、ミーシャを抱きしめることに躊躇がなくなった。
おかげで心臓は朝から全力稼働だ。これは治療、自分は人間懐炉だと、何度も言い聞かせる。
おだやかな声で話すリアムとは違い、ミーシャはいつまでもこの状況に慣れないでいた。
――治療に前向きになったというよりは、私を、クレアと重ねているのかも。
よくないな。と思いながらも彼を拒むことはできないし、したくない。
「いつも言っているが、なにか不便があれば遠慮はいらないから」
「ありがとうございます」
とくとくと彼の心音が聞こえる。
昨夜のリアムは無茶しそうで心配だったが、今は落ち着いている。ひとまず安堵した。