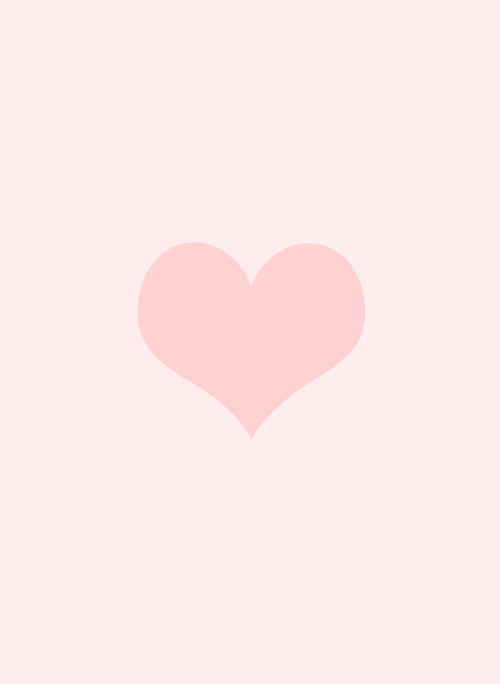ーーー私は一体、何をしているのか。
こんな、誰も来る気配がない空き教室で、甘い雰囲気のなかで。
「……っ、」
「痛いね、ごめんね」
「っべ、つに、いたくない…ですもん…」
「ふっ……かわいい」
ちら、と私の首に顔をうずめている彼に視線を寄越すと、ちょうどその琥珀色の瞳と目が合った。
ギラリと効果音が付きそうなその瞳は、まるで満月のように輝きを帯びている。
視線が交わった瞬間、その妖艶さを孕んだ瞳に囚われた気がした。
ーーーなんで、こんなことになったんだっけ。
本当、何しているんだろう私は。この前まで、普通に学園で過ごしていただけなのに。
なんで今、私はこんなことをしてしまっているんだろう。
「……っん、」
そんな考えは、鎖骨に感じた彼の唇と、鋭い八重歯の感触であっという間にどこかへ行ってしまって。