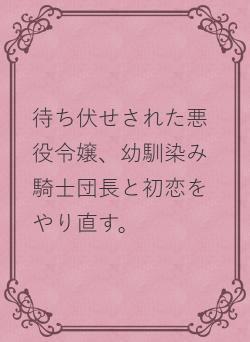幼馴染みで仲の良い彼女と、こんなにも話さなかったのは、人生で初めてだったかもしれない。
「ありがとう。ジャスティナ。私も不義理をしていて、ごめんなさい」
「良いのよ。貴女は新婚で、新しく転居もしたばかり。私も来てくれるかしらと思いつつ、招待していたのだけど、こうして会えて良かったわ……そう。私、フィオナにどうしても言わなければならないことがあって」
いつも快活なジャスティナがこんな風に言葉をにごすなんて、とても珍しい。もしかしたら、とても言い難いことなのかもしれない。
「……? 何かしら」
「あの……エミリオ・ヴェルデのことよ。貴女、前に彼に好意があると言っていたことがあったでしょう?」
私はそれを聞いて、エミリオ様とジャスティナの二人が、親密そうに談笑しているところを思い出してしまった。
けれど、何故なのだろうか。そういうことがあったわと思うだけで、特に怒ったり辛かったりなんて、思わなかった。
「ええ? ……そうだったわね。そんな時もあったわ」
彼女の言いづらい理由を察した私は、敢えて平然とした表情に見えるように装ったつもり。
「ありがとう。ジャスティナ。私も不義理をしていて、ごめんなさい」
「良いのよ。貴女は新婚で、新しく転居もしたばかり。私も来てくれるかしらと思いつつ、招待していたのだけど、こうして会えて良かったわ……そう。私、フィオナにどうしても言わなければならないことがあって」
いつも快活なジャスティナがこんな風に言葉をにごすなんて、とても珍しい。もしかしたら、とても言い難いことなのかもしれない。
「……? 何かしら」
「あの……エミリオ・ヴェルデのことよ。貴女、前に彼に好意があると言っていたことがあったでしょう?」
私はそれを聞いて、エミリオ様とジャスティナの二人が、親密そうに談笑しているところを思い出してしまった。
けれど、何故なのだろうか。そういうことがあったわと思うだけで、特に怒ったり辛かったりなんて、思わなかった。
「ええ? ……そうだったわね。そんな時もあったわ」
彼女の言いづらい理由を察した私は、敢えて平然とした表情に見えるように装ったつもり。