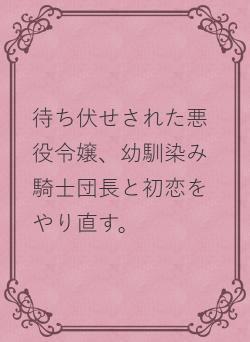自然と涙がこぼれて来て、こんなことになると思っていなかったらしいルーンさんはいきなり泣き出した私に驚き息をのんでいた。
「……そんなこと、ないだろ。現にシリルは、結婚相手に君を選んでるし……」
「それはっ……! 私があの時に困っていた彼の求める存在で、ちょうど良かったからですよね? 私なんて……それだけの、何の価値もない存在なんです。自分が一番、わかっているんですっ」
ルーンさんは私がグスグスと泣いているのを見て本当に困っている様子だったけど、流石に泣いている女の子を放ってどこかに行こうとはしなかった。
「……ごめん。ハンカチ持ってない」
「っ……良いです。ごめんなさい」
ルーンさんは一旦私に近づいて来て、そしてなぜか離れてから隣の席へと座って、私が泣きやむのをずっと待ってくれていた。
◇◆◇
「フィオナ。良かったわね……幸せそうで、私も一安心したわ」
ジャスティナ主催のエリュトルン伯爵家のお茶会に出席し、その後で私は久しぶりに彼女と二人でゆっくり話すことが出来た。
「……そんなこと、ないだろ。現にシリルは、結婚相手に君を選んでるし……」
「それはっ……! 私があの時に困っていた彼の求める存在で、ちょうど良かったからですよね? 私なんて……それだけの、何の価値もない存在なんです。自分が一番、わかっているんですっ」
ルーンさんは私がグスグスと泣いているのを見て本当に困っている様子だったけど、流石に泣いている女の子を放ってどこかに行こうとはしなかった。
「……ごめん。ハンカチ持ってない」
「っ……良いです。ごめんなさい」
ルーンさんは一旦私に近づいて来て、そしてなぜか離れてから隣の席へと座って、私が泣きやむのをずっと待ってくれていた。
◇◆◇
「フィオナ。良かったわね……幸せそうで、私も一安心したわ」
ジャスティナ主催のエリュトルン伯爵家のお茶会に出席し、その後で私は久しぶりに彼女と二人でゆっくり話すことが出来た。