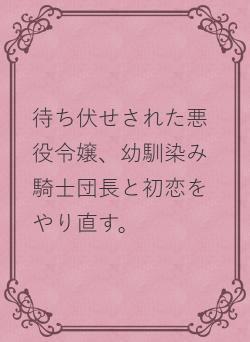この地下室の中、どんな惨状があったとしても。それはエミリオ・ヴェルデ本人の悪意が、そのまま彼に返って来ただけ。
「ルーン。ごめん。助けに来るの遅れた」
悪気のない笑顔でシリルはにこにこ笑って、私の体を入ってきた扉の方向へと向けると肩を抱いて歩き始めた。
反対側の私の隣を歩くルーンさんは魔力を吸い取られて気だるそうではあるけど、足取りもフラついていないし見たところは怪我もなさそう。
彼を助けられて、本当に良かった。
「チッ。遅れて来て、良いとこ取りかよ。こっちは嫌な役やらされたわ。魔力もほぼない。お前、大丈夫なの。ベアトリスの張っていた国全体の結界を、肩代わりするとか」
そういえば、ルーンさんが入っていた結界を彼が内側から壊してしまうと、聖女の張る国全体を覆っている結界にもほころびが出来るから、国民に被害を与えたくない彼はずっと出るのを我慢していたって言っていた。
「……うーん。俺にもやってやれない事はないと思っていたけど、想像以上にキツい。ルーンの魔力って、これ手伝えるくらいまでどの程度で回復する?」
「ルーン。ごめん。助けに来るの遅れた」
悪気のない笑顔でシリルはにこにこ笑って、私の体を入ってきた扉の方向へと向けると肩を抱いて歩き始めた。
反対側の私の隣を歩くルーンさんは魔力を吸い取られて気だるそうではあるけど、足取りもフラついていないし見たところは怪我もなさそう。
彼を助けられて、本当に良かった。
「チッ。遅れて来て、良いとこ取りかよ。こっちは嫌な役やらされたわ。魔力もほぼない。お前、大丈夫なの。ベアトリスの張っていた国全体の結界を、肩代わりするとか」
そういえば、ルーンさんが入っていた結界を彼が内側から壊してしまうと、聖女の張る国全体を覆っている結界にもほころびが出来るから、国民に被害を与えたくない彼はずっと出るのを我慢していたって言っていた。
「……うーん。俺にもやってやれない事はないと思っていたけど、想像以上にキツい。ルーンの魔力って、これ手伝えるくらいまでどの程度で回復する?」