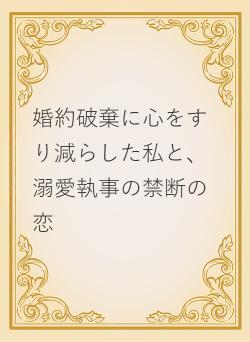◇◆◇
馬車に乗ることも二回目といった様子であったため、コルネリアはもの珍しそうに流れていく景色を眺める。
まるで子供のようにじっと窓に張り付いて外の景色を見ているので、レオンハルトはなんとも微笑ましくなってほんわかしてしまう。
「すみません、子供っぽかったですよね……」
「いいや、そんな君も僕は好きだよ」
さらっと『好き』なんて言葉を言うものだから、さすがにコルネリアの心臓も少しドキリとする。
コルネリアが離婚したい、とレオンハルトに言い出した日から徐々に彼女の感情が戻り始めており、おおよそ人並みの驚きや嬉しさを素直に感じて表現するようになっていた。
そんな大きな変化がレオンハルトにはとても嬉しく、毎日静かに彼女のことを見守っていた。
馬車の中で話をしていると、あっという間に王都の街の入り口に着き、二人は馬車を降りてある場所へと向かった。
「オーナー、いるだろうか」
「レオンハルト様、ようこそ、いらっしゃいました」
深々とお辞儀をするその男性は絵にかいたような紳士であり、白髪が綺麗でスーツを着こなす60代ほどの男性であった。
馬車に乗ることも二回目といった様子であったため、コルネリアはもの珍しそうに流れていく景色を眺める。
まるで子供のようにじっと窓に張り付いて外の景色を見ているので、レオンハルトはなんとも微笑ましくなってほんわかしてしまう。
「すみません、子供っぽかったですよね……」
「いいや、そんな君も僕は好きだよ」
さらっと『好き』なんて言葉を言うものだから、さすがにコルネリアの心臓も少しドキリとする。
コルネリアが離婚したい、とレオンハルトに言い出した日から徐々に彼女の感情が戻り始めており、おおよそ人並みの驚きや嬉しさを素直に感じて表現するようになっていた。
そんな大きな変化がレオンハルトにはとても嬉しく、毎日静かに彼女のことを見守っていた。
馬車の中で話をしていると、あっという間に王都の街の入り口に着き、二人は馬車を降りてある場所へと向かった。
「オーナー、いるだろうか」
「レオンハルト様、ようこそ、いらっしゃいました」
深々とお辞儀をするその男性は絵にかいたような紳士であり、白髪が綺麗でスーツを着こなす60代ほどの男性であった。