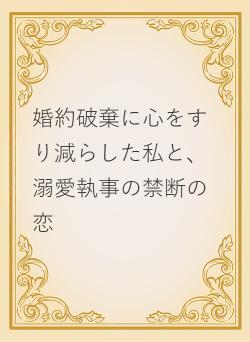ふとレオンハルトは淡い色の髪に隠れた大きくつぶらな瞳から、涙が零れ落ちているのを見て目を丸くする。
「私、どうして、でも、公爵様にご迷惑をかけたくないと、それだけを、思って」
その一言でレオンハルトは全てを悟り、コルネリアの腕を強く引き寄せて自分の胸に彼女をしまい込んだ。
抱きしめられた──
そんな風にコルネリアが気づいたのは少し間が空いた頃で、優しくも力強いレオンハルトの腕の中にいた。
「公爵様──」
「私の自惚れだろうか。君は僕を思ってくれた、僕のためを思って身を引こうとしてくれた、違うかい?」
その問いかけに対してコルネリアは声を発することができずに、こくりと小さく頷く。
顔はうっすらと赤らんでおり、しかしそんな様子は抱きしめているレオンハルトには見えていない──
「なんてバカなことを……なんて失礼だね。まずはありがとうと伝えるべきかな。僕のことを案じてくれて」
そう言いながら大きく角ばった手を淡いピンク色の髪で彩られた頭に乗せてなぞり、愛しい思いをぶつけるようにふんわりとした髪を撫でる。
「私、どうして、でも、公爵様にご迷惑をかけたくないと、それだけを、思って」
その一言でレオンハルトは全てを悟り、コルネリアの腕を強く引き寄せて自分の胸に彼女をしまい込んだ。
抱きしめられた──
そんな風にコルネリアが気づいたのは少し間が空いた頃で、優しくも力強いレオンハルトの腕の中にいた。
「公爵様──」
「私の自惚れだろうか。君は僕を思ってくれた、僕のためを思って身を引こうとしてくれた、違うかい?」
その問いかけに対してコルネリアは声を発することができずに、こくりと小さく頷く。
顔はうっすらと赤らんでおり、しかしそんな様子は抱きしめているレオンハルトには見えていない──
「なんてバカなことを……なんて失礼だね。まずはありがとうと伝えるべきかな。僕のことを案じてくれて」
そう言いながら大きく角ばった手を淡いピンク色の髪で彩られた頭に乗せてなぞり、愛しい思いをぶつけるようにふんわりとした髪を撫でる。