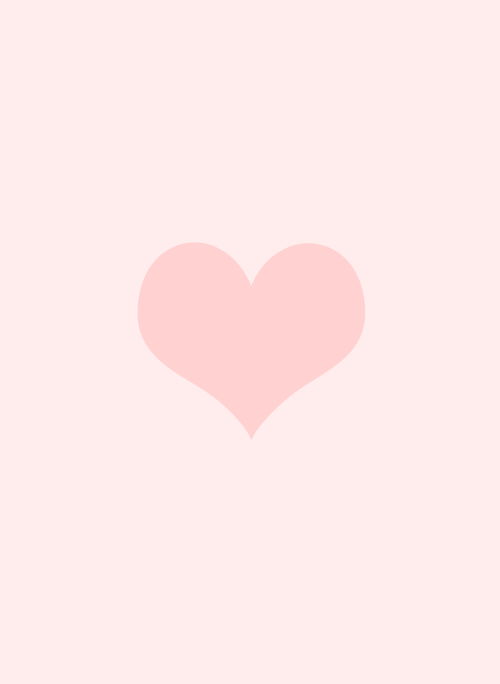「水族館とは陰キャのクセにやりますわね」
「陰キャは余計だと思うんですけど」
「ふふふふ、それではエスコートをしっかりお願いね」
どこか楽しんでいるようにも見える。
表情は普段と変わらない仮面のような顔。
本心がどこにあるのか──誠也にはまったく分からず、偽りのデートが始まろうとしていた。
休日ともあって親子連れやカップルの姿が目立つ。
全員が手を繋ぎ楽しそうそうな声が聞こえてくる。
この中で手を繋いでいないのは誠也と瑞希だけ。浮いているような感覚に襲われ、周りの視線を意識してしまう。
カップルというものは手を繋ぐ義務でもあるのか。そんなのは恥ずかしすぎて無理に決まっている。
水族館の入口で呆然と佇み、ふたりだけの時間が止まってしまう。
手を繋ぐべきか、このまま行くべきか──重たい空気の中、最初に口を開いたのは瑞希であった。
「ねぇ、誠也、その……手、繋ごっか」
「えっ……」
「か、勘違いしないでよばかっ。ここで手を繋がないと恋人に見えないでしょっ! それに……もしクラスメイトや学校の人が見てたら恋人じゃないかもって思われるかもしれないし……」
恥ずかしさが体の内側から込み上げてくる。
冷徹な顔が熱を帯びて赤一色になった。
異性と手を繋ぐのはまだ2回目。1回目はついさっき誠也に掴まれたとき。この日、瑞希は異性と肉体的接触をする、という初めての経験は偽りの恋人とだった。
「そ、それくらい分かってるって」
「それならいいわよ。この私と手を繋げるんだからありがたく思いなさい」
「う、うん……。それで恋人に見える繋ぎ方ってどうすればいいのかな?」
「そんなこと、私だって知るわけないしゃないっ」
恋にまったく興味がなかった誠也にとって、この問題は難攻不落の城を攻めるみたいなもの。
そもそも女性と手を繋いだのはいつ以来だろう。
小学生のとき? いや、それより前かもしれない。覚えてないのなら、マンガやラノベを思い出せばいい。
誠也はデートシーンを参考に手を繋ごうとした。
「えっと、それじゃ、恋人繋ぎっていう繋ぎ方があって、それなら恋人っぽく見えると思うよ」
「恋人繋ぎ……?」
「うん、お互いの指を交互に入れて手を繋ぐんだよ。ほら、こうやって──」
イメージでしか知らないことを、初めて実践するのは緊張する。
いや、緊張しているのは誠也だけではない。瑞希もまた不思議な感触によく分からない感情に襲われる。
ドキドキが止まらない。
偽りの恋人で興味すらないのに。
きっとこれは初めての経験だからに違いない。
自分の気持ちを強引に決めつけ、瑞希は誠也と恋人繋ぎで水族館の中へ歩いていった。
「陰キャは余計だと思うんですけど」
「ふふふふ、それではエスコートをしっかりお願いね」
どこか楽しんでいるようにも見える。
表情は普段と変わらない仮面のような顔。
本心がどこにあるのか──誠也にはまったく分からず、偽りのデートが始まろうとしていた。
休日ともあって親子連れやカップルの姿が目立つ。
全員が手を繋ぎ楽しそうそうな声が聞こえてくる。
この中で手を繋いでいないのは誠也と瑞希だけ。浮いているような感覚に襲われ、周りの視線を意識してしまう。
カップルというものは手を繋ぐ義務でもあるのか。そんなのは恥ずかしすぎて無理に決まっている。
水族館の入口で呆然と佇み、ふたりだけの時間が止まってしまう。
手を繋ぐべきか、このまま行くべきか──重たい空気の中、最初に口を開いたのは瑞希であった。
「ねぇ、誠也、その……手、繋ごっか」
「えっ……」
「か、勘違いしないでよばかっ。ここで手を繋がないと恋人に見えないでしょっ! それに……もしクラスメイトや学校の人が見てたら恋人じゃないかもって思われるかもしれないし……」
恥ずかしさが体の内側から込み上げてくる。
冷徹な顔が熱を帯びて赤一色になった。
異性と手を繋ぐのはまだ2回目。1回目はついさっき誠也に掴まれたとき。この日、瑞希は異性と肉体的接触をする、という初めての経験は偽りの恋人とだった。
「そ、それくらい分かってるって」
「それならいいわよ。この私と手を繋げるんだからありがたく思いなさい」
「う、うん……。それで恋人に見える繋ぎ方ってどうすればいいのかな?」
「そんなこと、私だって知るわけないしゃないっ」
恋にまったく興味がなかった誠也にとって、この問題は難攻不落の城を攻めるみたいなもの。
そもそも女性と手を繋いだのはいつ以来だろう。
小学生のとき? いや、それより前かもしれない。覚えてないのなら、マンガやラノベを思い出せばいい。
誠也はデートシーンを参考に手を繋ごうとした。
「えっと、それじゃ、恋人繋ぎっていう繋ぎ方があって、それなら恋人っぽく見えると思うよ」
「恋人繋ぎ……?」
「うん、お互いの指を交互に入れて手を繋ぐんだよ。ほら、こうやって──」
イメージでしか知らないことを、初めて実践するのは緊張する。
いや、緊張しているのは誠也だけではない。瑞希もまた不思議な感触によく分からない感情に襲われる。
ドキドキが止まらない。
偽りの恋人で興味すらないのに。
きっとこれは初めての経験だからに違いない。
自分の気持ちを強引に決めつけ、瑞希は誠也と恋人繋ぎで水族館の中へ歩いていった。