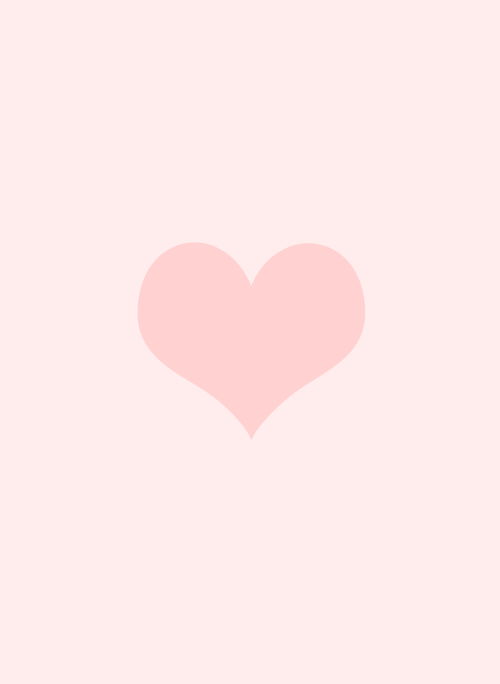「はぅ、しっかり練習して失敗しないようにしないと……」
時間は待ってくれない。
急いでお昼を済ますと、さっそく一人きりになれる場所へと移動する。
そこは人が滅多に来ないことで有名な場所。
だからこそ練習にはうってつけ。
限られた時間の中で迷ってる暇などない。瑠香は恥ずかしさを押し殺しながら、誠也を家に呼ぶ練習を始めた。
「──コホン。あ、あのね、ちょっと話が……あるんだけど、いいかなっ?」
幻の誠也を自ら作り出し、それが本物だと思い話しかける。
その場に何もないのは当たり前で、誰かが見たら変人扱いするのは間違いない。
だがそれでも瑠香は勇気ある一歩を踏み出そうと、なりふり構わず羞恥心を捨てる。
本当はかなり恥ずかしい。
それはひとりで練習していることではなく、幻の誠也を家に誘おうとしていること。
練習の段階ですら、心臓が破裂しそうなくらい大きな音を奏でる。
顔は真っ赤に染まる中、恥じらいながら幻の誠也に話しかけた。
「そ、そんなに時間取らせないから……。ダメ、かな?」
分かっている、今この場に誠也がいないことを。
それでも瑠香の瞳は僅かに潤み、上目遣いで誠也にお願いする。
頭の中はすでに真っ白。
それは何を言えばいいのか忘れてしまうほど。
これではダメ、ちゃんとしっかり伝えないと、このチャンスを不意にしてしまう。
一旦落ち着こう──大きく深呼吸をして冷静さを取り戻し、決め手となる誘い文句を伝えた。
「えっとね、私の両親なんだけど、出張で一晩いないの。それでね……私ひとりだと、その……怖いから、うちに来てくれると嬉しいかな。で、でも、無理にとは言わないよ、誠也がその……イヤじゃなければだけど……」
恥ずかしすぎて真っ赤な顔から湯気が立っている。
緊張で体が小刻みに震え、大地に足がついていない感覚だった。
練習とはいえ、返事を待つ時間はドキドキで気を失いそう。
もしこれで断られたのなら──そんなネガティブ思考に陥るも、幻聴らしき声が耳をかすめ、瑠香はその声の方向へ視線を向けた。
「昔から瑠香は怖がりだもんね。いいよ、僕でよければ一晩くらい付き合うからさ」
いるはずのない誠也の声。
幻であったはずの誠也が実体となって瑠香の前にいる。
これは夢……? それとも妄想?
言葉が出てこないでいると、誠也らしき人物から再び声が聞こえてくる。
「僕じゃやっぱりダメなのかな?」
「あっ、え、えっと、本物の誠也……? どうしてこんなところにいるのよっ」
絞り出した言葉はなぜか否定的。
だけどこれは現実、幻でも妄想でもなく、確かに目の前には誠也の姿があった。
「ちよっと時間潰しで校内を歩いてたんだ。それで、瑠香の家には……行った方がいいのかな?」
「うぅ……。誠也のばかっ」
「なんで僕が怒られるんだよ」
「そ、それは……で、でも、本当にうちに来てくれるの?」
「もちろんさ。大切な幼なじみのピンチなんだから、助けるのは当たり前でしょ」
練習のつもりが、途中で本番にすり変わるという珍事。
ここまでくると吹っ切れるしかない。
瑠香は赤く染まった顔で小さく頷き、誠也の袖をそっと掴んでいた。
時間は待ってくれない。
急いでお昼を済ますと、さっそく一人きりになれる場所へと移動する。
そこは人が滅多に来ないことで有名な場所。
だからこそ練習にはうってつけ。
限られた時間の中で迷ってる暇などない。瑠香は恥ずかしさを押し殺しながら、誠也を家に呼ぶ練習を始めた。
「──コホン。あ、あのね、ちょっと話が……あるんだけど、いいかなっ?」
幻の誠也を自ら作り出し、それが本物だと思い話しかける。
その場に何もないのは当たり前で、誰かが見たら変人扱いするのは間違いない。
だがそれでも瑠香は勇気ある一歩を踏み出そうと、なりふり構わず羞恥心を捨てる。
本当はかなり恥ずかしい。
それはひとりで練習していることではなく、幻の誠也を家に誘おうとしていること。
練習の段階ですら、心臓が破裂しそうなくらい大きな音を奏でる。
顔は真っ赤に染まる中、恥じらいながら幻の誠也に話しかけた。
「そ、そんなに時間取らせないから……。ダメ、かな?」
分かっている、今この場に誠也がいないことを。
それでも瑠香の瞳は僅かに潤み、上目遣いで誠也にお願いする。
頭の中はすでに真っ白。
それは何を言えばいいのか忘れてしまうほど。
これではダメ、ちゃんとしっかり伝えないと、このチャンスを不意にしてしまう。
一旦落ち着こう──大きく深呼吸をして冷静さを取り戻し、決め手となる誘い文句を伝えた。
「えっとね、私の両親なんだけど、出張で一晩いないの。それでね……私ひとりだと、その……怖いから、うちに来てくれると嬉しいかな。で、でも、無理にとは言わないよ、誠也がその……イヤじゃなければだけど……」
恥ずかしすぎて真っ赤な顔から湯気が立っている。
緊張で体が小刻みに震え、大地に足がついていない感覚だった。
練習とはいえ、返事を待つ時間はドキドキで気を失いそう。
もしこれで断られたのなら──そんなネガティブ思考に陥るも、幻聴らしき声が耳をかすめ、瑠香はその声の方向へ視線を向けた。
「昔から瑠香は怖がりだもんね。いいよ、僕でよければ一晩くらい付き合うからさ」
いるはずのない誠也の声。
幻であったはずの誠也が実体となって瑠香の前にいる。
これは夢……? それとも妄想?
言葉が出てこないでいると、誠也らしき人物から再び声が聞こえてくる。
「僕じゃやっぱりダメなのかな?」
「あっ、え、えっと、本物の誠也……? どうしてこんなところにいるのよっ」
絞り出した言葉はなぜか否定的。
だけどこれは現実、幻でも妄想でもなく、確かに目の前には誠也の姿があった。
「ちよっと時間潰しで校内を歩いてたんだ。それで、瑠香の家には……行った方がいいのかな?」
「うぅ……。誠也のばかっ」
「なんで僕が怒られるんだよ」
「そ、それは……で、でも、本当にうちに来てくれるの?」
「もちろんさ。大切な幼なじみのピンチなんだから、助けるのは当たり前でしょ」
練習のつもりが、途中で本番にすり変わるという珍事。
ここまでくると吹っ切れるしかない。
瑠香は赤く染まった顔で小さく頷き、誠也の袖をそっと掴んでいた。