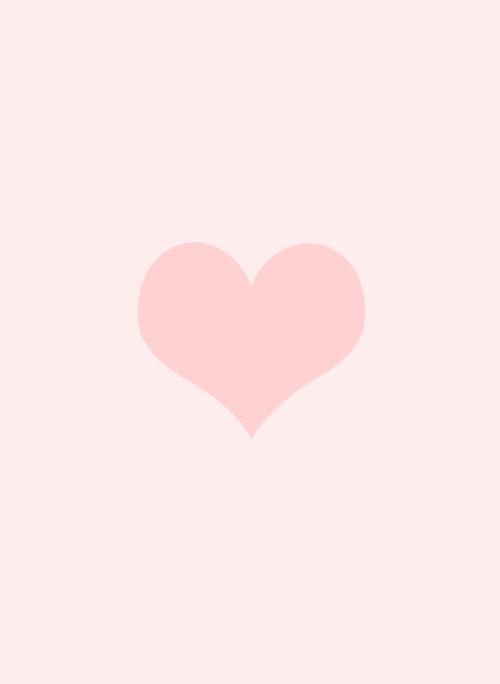キスをするだけ。それも頬っぺたに軽く。
瑞希は鏡の前で自己暗示をかけ、朝から大きくなった鼓動を押さえ込もうとする。
「……よしっ。大丈夫、たかが頬っぺたじゃない。外国じゃ挨拶みたいなものだし」
これは断じて言い訳なんかではない。
意味合いが日本と外国で違うのは事実。
日本にはいるけど、キスする瞬間だけ外国にいると思えばいい。
頬を赤く染めながら瑞希は学校へと向かい始めた。
「誠也、おはよう」
いつものように駅前での待ち合わせ。
誠也が先に待っていて、あとから瑞希が来る。これが朝の日常だった。
「おはよう、瑞希」
「あ、あのね、ちょっとだけお願いがあるんだけど──」
一気に跳ね上がる心音。
誠也を見るだけで、せっかくかけた自己暗示が解けてしまう。
伝えないと伝わらない、そんなことは分かりきった話。
しかしその先の言葉が出てこない。まるで瑞希の意志を拒絶するように、言葉は心の内側に沈んでいった。
「お願い? 僕で出来ることなら聞くよ」
「ううん、やっぱりいいわ。それより早くしないと遅刻するじゃないの」
ただの気まぐれなのか。
誠也は言葉の意味を深く考えず、瑞希の手を優しく握り学校への道を急いだ。
瑞希と付き合ってから──とは言っても偽りではあるが、一週間近くが経とうしている。変わったことといえば、男子から悪意ある眼差しを向けられることぐらい。
仕方がないこととはいえ、やはり精神的には少しだけ堪える。
が……愛のメモリアルノートを全校放送されるよりはまだマシ。
奪い取るにしても隠し場所など分かるはずもなく、女子から強引に奪うなど誠也にはとても無理。
しばらくは偽りの恋人を続けるしかない──悪意ある視線を除けば、今の生活はそこまで嫌いではなかった。
「そういえば、瑞希のこと知らなすぎるかな。いくら偽りとはいえ、少しぐらい興味を持たないとウソだとバレちゃうよね」
能天気なのか、黒歴史の心配より瑞希の心配をする誠也。
もしかしたらお人好しすぎるのかもしれない。
昼休みか、放課後か、少し瑞希に質問しようかと考えていると、朝のことが急に気になり始めた。
瑞希は鏡の前で自己暗示をかけ、朝から大きくなった鼓動を押さえ込もうとする。
「……よしっ。大丈夫、たかが頬っぺたじゃない。外国じゃ挨拶みたいなものだし」
これは断じて言い訳なんかではない。
意味合いが日本と外国で違うのは事実。
日本にはいるけど、キスする瞬間だけ外国にいると思えばいい。
頬を赤く染めながら瑞希は学校へと向かい始めた。
「誠也、おはよう」
いつものように駅前での待ち合わせ。
誠也が先に待っていて、あとから瑞希が来る。これが朝の日常だった。
「おはよう、瑞希」
「あ、あのね、ちょっとだけお願いがあるんだけど──」
一気に跳ね上がる心音。
誠也を見るだけで、せっかくかけた自己暗示が解けてしまう。
伝えないと伝わらない、そんなことは分かりきった話。
しかしその先の言葉が出てこない。まるで瑞希の意志を拒絶するように、言葉は心の内側に沈んでいった。
「お願い? 僕で出来ることなら聞くよ」
「ううん、やっぱりいいわ。それより早くしないと遅刻するじゃないの」
ただの気まぐれなのか。
誠也は言葉の意味を深く考えず、瑞希の手を優しく握り学校への道を急いだ。
瑞希と付き合ってから──とは言っても偽りではあるが、一週間近くが経とうしている。変わったことといえば、男子から悪意ある眼差しを向けられることぐらい。
仕方がないこととはいえ、やはり精神的には少しだけ堪える。
が……愛のメモリアルノートを全校放送されるよりはまだマシ。
奪い取るにしても隠し場所など分かるはずもなく、女子から強引に奪うなど誠也にはとても無理。
しばらくは偽りの恋人を続けるしかない──悪意ある視線を除けば、今の生活はそこまで嫌いではなかった。
「そういえば、瑞希のこと知らなすぎるかな。いくら偽りとはいえ、少しぐらい興味を持たないとウソだとバレちゃうよね」
能天気なのか、黒歴史の心配より瑞希の心配をする誠也。
もしかしたらお人好しすぎるのかもしれない。
昼休みか、放課後か、少し瑞希に質問しようかと考えていると、朝のことが急に気になり始めた。