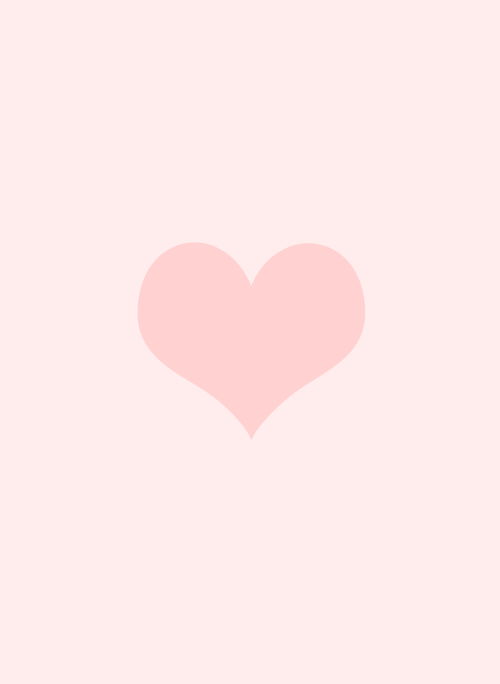誠也が誰と何しようが知ったことじゃない。
所詮は偽りなのだから。
しかし──それを肯定するのが敗北感を味わうようで、瑞希の中で答えがでない。
誠也と瑠香が昔どういう想いだったのかは知らない。
いいや、知りたくもない。きっと知ってしまったら、氷姫でいられる自信がなくなる。
「キス……か」
興味がないわけではない。
だが男相手にキスなど死んでもゴメンなわけで。
よく分からない感情が瑞希の中で湧き上がってきた。
「うぅ……。あー、もぅ、なんで誠也のことばっかり考えなくちゃいけないのよっ」
足をバタバタさせ今ここにいない誠也に八つ当たりする。
イラついている──今までこんなことは一度もなかった。
毎日男どもに告白されていたのは、イラつきというよりウザいと言った方が近い。
分からない、なんでイラついているのか分からなくて、さらにイラつく。
キスというたった二文字の言葉に翻弄されているのか?
それとも、誠也が隠し事していたことが許せないのか?
考えれば考えるほど、思考は出口のない迷宮へと迷い込む。
自分でどの道を進んだらいいのかすら分からない。
完全に迷走し始めてしまい、瑞希はシャワーでも浴びて頭をリセットしようとした。
「ふぅー、サッパリしたー」
水を温めただけのお湯に癒され、瑞希は頭の中が爽快になっていた。今ならイラついている原因が分かるはず。
冷静になった心でその原因がどこにあるのか探り始めた。
「誠也との関係って偽りの恋人なだけよね。うん、そうよ、告白が毎日続く生活が耐えられないから、女性に興味なさそうな誠也を選んだんだし」
原点はそこにあり、愛情なんて微塵もなかった。
好きでも嫌いでもない──道端に落ちてる小石のような存在。だからこそ瑞希は、恋人役に誠也を選んだのだ。
そう、ただの小石だったはず。
無機物だと思っていたから氷姫でいられた。それなのに、小石から変わってしまった原因はどこにあるのだろうか。
思い当たるのはただひとつ。
水族館でのデートで手を繋いだり、事故とはいえ抱きついたりと、初めての経験をしたこと。その日を境にして、誠也を見る目が変わっていったのも事実だった。
「そう、よ。あのデートが原因なだけよ。初めての経験だったから、同様してるだけなんですから。でも──」
気になったのはあの日の行動。
瑠香と沙織の話に誠也が登場したとき。
つい聞き耳を立てその内容をチェックしてしまう。偽りとはいえ恋人の話題なのだからと、自分に言い聞かせてまで。
キスという言葉が飛び出した瞬間、体が勝手に動き出し、気がついたときには瑠香に話しかけていた。この行動が瑞希にとって理解不能で、きっとモヤモヤの原因であると考えた。
所詮は偽りなのだから。
しかし──それを肯定するのが敗北感を味わうようで、瑞希の中で答えがでない。
誠也と瑠香が昔どういう想いだったのかは知らない。
いいや、知りたくもない。きっと知ってしまったら、氷姫でいられる自信がなくなる。
「キス……か」
興味がないわけではない。
だが男相手にキスなど死んでもゴメンなわけで。
よく分からない感情が瑞希の中で湧き上がってきた。
「うぅ……。あー、もぅ、なんで誠也のことばっかり考えなくちゃいけないのよっ」
足をバタバタさせ今ここにいない誠也に八つ当たりする。
イラついている──今までこんなことは一度もなかった。
毎日男どもに告白されていたのは、イラつきというよりウザいと言った方が近い。
分からない、なんでイラついているのか分からなくて、さらにイラつく。
キスというたった二文字の言葉に翻弄されているのか?
それとも、誠也が隠し事していたことが許せないのか?
考えれば考えるほど、思考は出口のない迷宮へと迷い込む。
自分でどの道を進んだらいいのかすら分からない。
完全に迷走し始めてしまい、瑞希はシャワーでも浴びて頭をリセットしようとした。
「ふぅー、サッパリしたー」
水を温めただけのお湯に癒され、瑞希は頭の中が爽快になっていた。今ならイラついている原因が分かるはず。
冷静になった心でその原因がどこにあるのか探り始めた。
「誠也との関係って偽りの恋人なだけよね。うん、そうよ、告白が毎日続く生活が耐えられないから、女性に興味なさそうな誠也を選んだんだし」
原点はそこにあり、愛情なんて微塵もなかった。
好きでも嫌いでもない──道端に落ちてる小石のような存在。だからこそ瑞希は、恋人役に誠也を選んだのだ。
そう、ただの小石だったはず。
無機物だと思っていたから氷姫でいられた。それなのに、小石から変わってしまった原因はどこにあるのだろうか。
思い当たるのはただひとつ。
水族館でのデートで手を繋いだり、事故とはいえ抱きついたりと、初めての経験をしたこと。その日を境にして、誠也を見る目が変わっていったのも事実だった。
「そう、よ。あのデートが原因なだけよ。初めての経験だったから、同様してるだけなんですから。でも──」
気になったのはあの日の行動。
瑠香と沙織の話に誠也が登場したとき。
つい聞き耳を立てその内容をチェックしてしまう。偽りとはいえ恋人の話題なのだからと、自分に言い聞かせてまで。
キスという言葉が飛び出した瞬間、体が勝手に動き出し、気がついたときには瑠香に話しかけていた。この行動が瑞希にとって理解不能で、きっとモヤモヤの原因であると考えた。