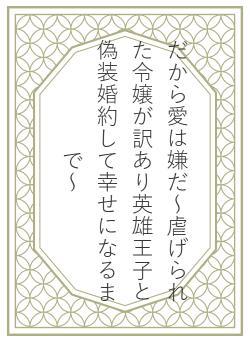馬車の中で、アルデラは伯爵家の借金を解決する方法をブラッドに説明した。
「簡単な話なんだけど、私の実家の公爵家には腐るほどお金があるの」
ブラッドは「そ、そうでしょうね」と戸惑いながら相づちを打つ。
「そうなの。だから、お金は公爵家からもらいましょう」
正確にはお金はもらうのではなく、奪い取るのだけど、そこらへんは省略する。
「もらいましょう、って……」と、戸惑うブラッドにアルデラは微笑みかけた。
「だってほら、クリス様ってば、私を押し付けられたのに、公爵家から持参金すらもらっていないじゃない? 私だって身一つで放り出されたし。だから、私の養育にかかるはずだった費用もしっかりと払ってもらわないとね」
「は、はぁ」
納得していないブラッドにアルデラは一番重要なことを伝えた。
「そういう訳で、貴方は馬車で待っていてね」
「え? どういう訳ですか!?」
驚くブラッドに「だって……付いて来られると困るの」と言葉を濁す。
(これから、ビンに溜め込んだ自分の髪と爪をぶちまけて、高笑いしながらクズ両親を脅迫する姿なんて誰にも見せられないわ。さすがに怖いって)
困ってうつむいていると何を勘違いしたのかブラッドは「アルデラ様がそこまでのご覚悟とは」と、ため息をついた。
「貴女様は、クリス様のために、自分を虐げた両親に頭を下げるつもりなのですね?」
「え?」
ブラッドは「分かっていますよ」と言いながらメガネを指で押し上げた。
「このブラッド、必ずアルデラ様をお守りします!」
そう言いながら忠義に満ちた瞳を向けられる。
(……もう、いっか。何か問題が起こったら、黒魔術でブラッドの記憶を消そう)
少し面倒になり、アルデラはブラッドの説得を早々にあきらめた。
そうしているうちに、馬車はゆっくりと公爵家の領内へと入っていく。
(相変わらずムダに広いわねぇ)
ここら辺全ての山や森が公爵家のものだ。そして、小高い丘の上に見えている城に、公爵家の人々が住んでいる。
実家に戻って来たせいで、アルデラの幼い頃の記憶が断片的によみがえってきたけど、楽しいことが一つもない。過去のアルデラを想うと泣きたくなってくる。
(ううっ、アルデラ! 何か! 何か一つくらい楽しい思い出はなかったの!?)
こめかみを人差し指で押さえながら一生懸命記憶を探ると、一人のお姉さんが思い浮かんだ。公爵家の城で働いている人なのか、そのお姉さんは、ときどきアルデラの前に現れると、いろんなことを教えてくれた。
「歯を磨いたり、身体や服を洗ったりしてキレイにしないと病気になるよ」とか「お腹が空いたときは、この木の実を食べたらいいよ」とか。
(そういえば、アルデラに字を教えてくれたり、絵本を貸してくれたりしたのも、このお姉さんだったような?)
そのお姉さんは、あまりおしゃべりが得意ではないようで、ポツリポツリと言葉に詰まりながら話す姿が印象的だった。
(あのお姉さんがくれたキャンディ……美味しかったなぁ)
一度だけそのお姉さんが棒状のキャンディをくれた。たった一本しかないキャンディをお姉さんはアルデラに「あげる」というので、アルデラは受け取り落ちていた石で半分に割った。そして、水で洗ってからお姉さんに半分返した。
「お姉さんも、いっしょに、食べよ」
(ア、アルデラぁああああ!)
健気な幼いアルデラの記憶に、転生者アルデラの涙腺は崩壊した。急に泣き出したアルデラにブラッドが驚いている。
(許すまじ、公爵家のやつら!)
ちょうど馬車が止まったので、アルデラは勢いよく馬車から下りた。今日、アルデラがここに来ることは、クリスから連絡がいっているはずなのに迎えの姿はどこにもない。
(まぁ、私が相手にされないことは想定済みよ)
勝手に城内に入って行くと、その後ろをブラッドが「お待ちください!」と言いながらついて来る。
(えっと、確かこっちだったかしら?)
記憶を頼りに父の書斎に向かおうとすると、この家の使用人を取り仕切っている白髪の男が現れた。
(この執事っぽいお爺さん、皆に、何て呼ばれていたかしら? 確か『執事』ではないのよね……)
アルデラは貴族社会に詳しくないし、転生者の記憶を使っても貴族の仕組みやルールは分からない。なので、目の前のお爺さんを仮に『執事』と呼ぶことにした。
白髪の執事は、蔑むような冷たい目をこちらに向けている。
執事は「どちら様ですか?」と無作法に聞いて来た。
「公爵に用があるの」
アレを父とは呼びたくないので、あえて公爵と呼んでおく。
「ここに私が来ることは、伯爵家から事前に連絡がいっているはずよ」
「その黒髪……まさか……アルデラ、様?」
「そうよ」
歩き出したアルデラの行く手を執事が阻んだ。
「でしたら、なおさらこの先はお通し出来ません」
丁寧な言葉を使っているがとても高圧的だ。
(うーん、この執事っぽい人がこの家のことを任されているんだから、アルデラをイジメた実行犯のようなものよね。今も伯爵夫人になった私にこの態度だし)
『よし、コイツにも仕返ししよう』と心に決める。
「……そう、残念ね」
アルデラは持っていたバスケットの中から万年筆を入れたビンを取りだした。
「書類に急ぎ公爵のサインが必要だったの。公爵に会えないのなら、貴方が代わりに書いてくれる?」
ニッコリと微笑みながら、ビンのフタを開けて万年筆を執事に差し出すと、執事は迷惑そうに眉間にシワを寄せた。
「公爵家の誰かが書いてくれないと困るのよ」
もちろん、それは全てウソだ。アルデラに早く帰って欲しいのか、執事は渋々万年筆を手に持った。そして、万年筆のフタを開けたとたんに、禍々しい黒いモヤが執事を取り囲む。
「う、ぐっ」
執事は急に真っ青になり苦しそうにうめいた。
ブラッドが「これは、もしかして……」とつぶやいたので、アルデラは「そう、さっきの呪いの万年筆よ」と返す。
「ねぇ、ブラッド、貴方何歳かしら?」
「今年で二十三になります」
「そう。さっきはだいぶ疲れていたようだけど、どのくらい無理をしていたの?」
「三か月ほど、ほとんど寝ていない状態でした」
黒いモヤに包まれた執事はフラフラとよろめき、床に両膝をついた。それを見下ろしてアルデラは笑う。
「ですってよ。健康な二十代男性が三か月ほど寝ていないほどの疲労を、その年で味わう気分はどう?」
執事は苦しそうに「何を、した?」とすごい形相で睨みつけてくる。アルデラはそっと執事に顔を寄せた。
「公爵家には代々伝わる秘術があることを、貴方も知っているでしょう?」
「まさか」と執事は青ざめる。
「その、まさかよ。私は黒魔術を使えるようになったの。さて、貴方の魂を奪うには、どれくらいの代償が必要かしら? 穢れた魂は、求められる代償も軽いから簡単に奪えるのよねぇ」
逆に聖人のように清らかな魂を奪うには、とんでもなく重い代償を要求される。アルデラが悪女らしくニヤリと口端をあげると、執事は「ひぃ」と小さな悲鳴を漏らした。
「まったく、よくも今まで散々アルデラを無視してくれたわね?」
「だ、旦那様の命令で仕方なく!」
ふるえる執事に「その割には、伯爵夫人になった私にもひどい態度だったけど?」と微笑みかけると、執事は床に頭をつけた。
「も、申し訳ありません! 命だけはお助けください!」
「どうしよっかなぁ? 私に貴方の誠実さを見せてくれたら、考えてあげても良いけどぉ?」
自分の黒髪を指でもてあそびながら焦らしていると、執事がハッとなり「お金、お金はいりませんか!?」と叫んだ。
「そうね、お金は必要ね。でも、貴方が私にお金をくれるの?」
「い、いえ! 私は公爵家の帳簿を付けております!」
「へぇ、そこから出してくれるんだ?」
必死に頷く執事にアルデラは「どれくらい?」と聞いた。
「そ、そうですね!」
執事がこの世界での百万円くらいを提示したので、アルデラは笑い飛ばす。
「あらあら、貴方の命、やっすいのねぇ」
バスケットの中からビンを取りだし、貯めていた爪を少し手のひらに出した。
「苦しめ」
そう願うと手のひらの爪は黒い炎で包まれた。執事はうめきながら苦しみ悶える。
「あ、がはっ!? お、お許し、を!」
涙を流して懇願する執事は、しばらくすると床に倒れ込んだ。気は失っておらず、荒い呼吸を繰り返している。
(まぁ、爪ならこの程度か)
起き上がれない執事をアルデラは見下ろした。
「助かりたい?」
執事は涙を流しながら頷いた。
「だったら、公爵家のやつらが一年間に使うお金を十六年分、私に支払いなさい。ああ、あと私が嫁ぐときに、伯爵家に支払われるべきだった持参金もね」
「そ、そんな……」
青ざめる執事に「大丈夫よ」と優しく伝える。
「公爵には、私が直接お会いして『丁寧に』お願いするから。きっと快く了承してくれるわ」
ニコリと微笑みかけると、執事の顔はさらに青ざめふるえ出す。
(自分の命をかけてまで、仕える主人を助ける気はないようね)
アルデラが鼻で笑って歩き出すと、「アルデラ様」と声をかけられた。振り返るとブラッドがいる。
(あ、いるの忘れてた)
仕返しに夢中になり過ぎて、うっかりブラッドの存在を忘れていた。
(黒魔術とか言っちゃったし、執事っぽい人を脅迫した所を見せてしまったわ)
クリスやノアに告げ口されると困るので『よし、記憶を消すか』とバスケットの中に手を入れると、ブラッドは勢い良く床に片膝をついた。
「素晴らしい! まさか本当にアルデラ様のおっしゃった通りになるなんて! このブラッド、感動いたしました!」
「……あ、うん」
『この人、黒魔術とかは、気にならないのかな?』と思ったけど、ブラッドがまるで忠犬のような綺麗な瞳で見つめてくるので、アルデラは気まずくなってそっと視線をそらした。
「簡単な話なんだけど、私の実家の公爵家には腐るほどお金があるの」
ブラッドは「そ、そうでしょうね」と戸惑いながら相づちを打つ。
「そうなの。だから、お金は公爵家からもらいましょう」
正確にはお金はもらうのではなく、奪い取るのだけど、そこらへんは省略する。
「もらいましょう、って……」と、戸惑うブラッドにアルデラは微笑みかけた。
「だってほら、クリス様ってば、私を押し付けられたのに、公爵家から持参金すらもらっていないじゃない? 私だって身一つで放り出されたし。だから、私の養育にかかるはずだった費用もしっかりと払ってもらわないとね」
「は、はぁ」
納得していないブラッドにアルデラは一番重要なことを伝えた。
「そういう訳で、貴方は馬車で待っていてね」
「え? どういう訳ですか!?」
驚くブラッドに「だって……付いて来られると困るの」と言葉を濁す。
(これから、ビンに溜め込んだ自分の髪と爪をぶちまけて、高笑いしながらクズ両親を脅迫する姿なんて誰にも見せられないわ。さすがに怖いって)
困ってうつむいていると何を勘違いしたのかブラッドは「アルデラ様がそこまでのご覚悟とは」と、ため息をついた。
「貴女様は、クリス様のために、自分を虐げた両親に頭を下げるつもりなのですね?」
「え?」
ブラッドは「分かっていますよ」と言いながらメガネを指で押し上げた。
「このブラッド、必ずアルデラ様をお守りします!」
そう言いながら忠義に満ちた瞳を向けられる。
(……もう、いっか。何か問題が起こったら、黒魔術でブラッドの記憶を消そう)
少し面倒になり、アルデラはブラッドの説得を早々にあきらめた。
そうしているうちに、馬車はゆっくりと公爵家の領内へと入っていく。
(相変わらずムダに広いわねぇ)
ここら辺全ての山や森が公爵家のものだ。そして、小高い丘の上に見えている城に、公爵家の人々が住んでいる。
実家に戻って来たせいで、アルデラの幼い頃の記憶が断片的によみがえってきたけど、楽しいことが一つもない。過去のアルデラを想うと泣きたくなってくる。
(ううっ、アルデラ! 何か! 何か一つくらい楽しい思い出はなかったの!?)
こめかみを人差し指で押さえながら一生懸命記憶を探ると、一人のお姉さんが思い浮かんだ。公爵家の城で働いている人なのか、そのお姉さんは、ときどきアルデラの前に現れると、いろんなことを教えてくれた。
「歯を磨いたり、身体や服を洗ったりしてキレイにしないと病気になるよ」とか「お腹が空いたときは、この木の実を食べたらいいよ」とか。
(そういえば、アルデラに字を教えてくれたり、絵本を貸してくれたりしたのも、このお姉さんだったような?)
そのお姉さんは、あまりおしゃべりが得意ではないようで、ポツリポツリと言葉に詰まりながら話す姿が印象的だった。
(あのお姉さんがくれたキャンディ……美味しかったなぁ)
一度だけそのお姉さんが棒状のキャンディをくれた。たった一本しかないキャンディをお姉さんはアルデラに「あげる」というので、アルデラは受け取り落ちていた石で半分に割った。そして、水で洗ってからお姉さんに半分返した。
「お姉さんも、いっしょに、食べよ」
(ア、アルデラぁああああ!)
健気な幼いアルデラの記憶に、転生者アルデラの涙腺は崩壊した。急に泣き出したアルデラにブラッドが驚いている。
(許すまじ、公爵家のやつら!)
ちょうど馬車が止まったので、アルデラは勢いよく馬車から下りた。今日、アルデラがここに来ることは、クリスから連絡がいっているはずなのに迎えの姿はどこにもない。
(まぁ、私が相手にされないことは想定済みよ)
勝手に城内に入って行くと、その後ろをブラッドが「お待ちください!」と言いながらついて来る。
(えっと、確かこっちだったかしら?)
記憶を頼りに父の書斎に向かおうとすると、この家の使用人を取り仕切っている白髪の男が現れた。
(この執事っぽいお爺さん、皆に、何て呼ばれていたかしら? 確か『執事』ではないのよね……)
アルデラは貴族社会に詳しくないし、転生者の記憶を使っても貴族の仕組みやルールは分からない。なので、目の前のお爺さんを仮に『執事』と呼ぶことにした。
白髪の執事は、蔑むような冷たい目をこちらに向けている。
執事は「どちら様ですか?」と無作法に聞いて来た。
「公爵に用があるの」
アレを父とは呼びたくないので、あえて公爵と呼んでおく。
「ここに私が来ることは、伯爵家から事前に連絡がいっているはずよ」
「その黒髪……まさか……アルデラ、様?」
「そうよ」
歩き出したアルデラの行く手を執事が阻んだ。
「でしたら、なおさらこの先はお通し出来ません」
丁寧な言葉を使っているがとても高圧的だ。
(うーん、この執事っぽい人がこの家のことを任されているんだから、アルデラをイジメた実行犯のようなものよね。今も伯爵夫人になった私にこの態度だし)
『よし、コイツにも仕返ししよう』と心に決める。
「……そう、残念ね」
アルデラは持っていたバスケットの中から万年筆を入れたビンを取りだした。
「書類に急ぎ公爵のサインが必要だったの。公爵に会えないのなら、貴方が代わりに書いてくれる?」
ニッコリと微笑みながら、ビンのフタを開けて万年筆を執事に差し出すと、執事は迷惑そうに眉間にシワを寄せた。
「公爵家の誰かが書いてくれないと困るのよ」
もちろん、それは全てウソだ。アルデラに早く帰って欲しいのか、執事は渋々万年筆を手に持った。そして、万年筆のフタを開けたとたんに、禍々しい黒いモヤが執事を取り囲む。
「う、ぐっ」
執事は急に真っ青になり苦しそうにうめいた。
ブラッドが「これは、もしかして……」とつぶやいたので、アルデラは「そう、さっきの呪いの万年筆よ」と返す。
「ねぇ、ブラッド、貴方何歳かしら?」
「今年で二十三になります」
「そう。さっきはだいぶ疲れていたようだけど、どのくらい無理をしていたの?」
「三か月ほど、ほとんど寝ていない状態でした」
黒いモヤに包まれた執事はフラフラとよろめき、床に両膝をついた。それを見下ろしてアルデラは笑う。
「ですってよ。健康な二十代男性が三か月ほど寝ていないほどの疲労を、その年で味わう気分はどう?」
執事は苦しそうに「何を、した?」とすごい形相で睨みつけてくる。アルデラはそっと執事に顔を寄せた。
「公爵家には代々伝わる秘術があることを、貴方も知っているでしょう?」
「まさか」と執事は青ざめる。
「その、まさかよ。私は黒魔術を使えるようになったの。さて、貴方の魂を奪うには、どれくらいの代償が必要かしら? 穢れた魂は、求められる代償も軽いから簡単に奪えるのよねぇ」
逆に聖人のように清らかな魂を奪うには、とんでもなく重い代償を要求される。アルデラが悪女らしくニヤリと口端をあげると、執事は「ひぃ」と小さな悲鳴を漏らした。
「まったく、よくも今まで散々アルデラを無視してくれたわね?」
「だ、旦那様の命令で仕方なく!」
ふるえる執事に「その割には、伯爵夫人になった私にもひどい態度だったけど?」と微笑みかけると、執事は床に頭をつけた。
「も、申し訳ありません! 命だけはお助けください!」
「どうしよっかなぁ? 私に貴方の誠実さを見せてくれたら、考えてあげても良いけどぉ?」
自分の黒髪を指でもてあそびながら焦らしていると、執事がハッとなり「お金、お金はいりませんか!?」と叫んだ。
「そうね、お金は必要ね。でも、貴方が私にお金をくれるの?」
「い、いえ! 私は公爵家の帳簿を付けております!」
「へぇ、そこから出してくれるんだ?」
必死に頷く執事にアルデラは「どれくらい?」と聞いた。
「そ、そうですね!」
執事がこの世界での百万円くらいを提示したので、アルデラは笑い飛ばす。
「あらあら、貴方の命、やっすいのねぇ」
バスケットの中からビンを取りだし、貯めていた爪を少し手のひらに出した。
「苦しめ」
そう願うと手のひらの爪は黒い炎で包まれた。執事はうめきながら苦しみ悶える。
「あ、がはっ!? お、お許し、を!」
涙を流して懇願する執事は、しばらくすると床に倒れ込んだ。気は失っておらず、荒い呼吸を繰り返している。
(まぁ、爪ならこの程度か)
起き上がれない執事をアルデラは見下ろした。
「助かりたい?」
執事は涙を流しながら頷いた。
「だったら、公爵家のやつらが一年間に使うお金を十六年分、私に支払いなさい。ああ、あと私が嫁ぐときに、伯爵家に支払われるべきだった持参金もね」
「そ、そんな……」
青ざめる執事に「大丈夫よ」と優しく伝える。
「公爵には、私が直接お会いして『丁寧に』お願いするから。きっと快く了承してくれるわ」
ニコリと微笑みかけると、執事の顔はさらに青ざめふるえ出す。
(自分の命をかけてまで、仕える主人を助ける気はないようね)
アルデラが鼻で笑って歩き出すと、「アルデラ様」と声をかけられた。振り返るとブラッドがいる。
(あ、いるの忘れてた)
仕返しに夢中になり過ぎて、うっかりブラッドの存在を忘れていた。
(黒魔術とか言っちゃったし、執事っぽい人を脅迫した所を見せてしまったわ)
クリスやノアに告げ口されると困るので『よし、記憶を消すか』とバスケットの中に手を入れると、ブラッドは勢い良く床に片膝をついた。
「素晴らしい! まさか本当にアルデラ様のおっしゃった通りになるなんて! このブラッド、感動いたしました!」
「……あ、うん」
『この人、黒魔術とかは、気にならないのかな?』と思ったけど、ブラッドがまるで忠犬のような綺麗な瞳で見つめてくるので、アルデラは気まずくなってそっと視線をそらした。