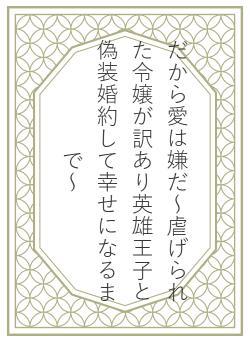王子に剣で切られたはずなのに不思議と痛くなかった。ただ胸の辺りが燃えるように熱い。生きるために必要なものが少しずつ身体の外へと流れ出ていっている。
(これでやっと終われるのね)
キャロルはゆっくりと目を閉じた。もう何も見なくていい。何も聞かなくていい。
物心がついたころから生きるのが辛かった。なんでもできる優秀な姉がいて、いつも姉と比べられていた。父も母も姉ばかりを可愛がった。
――どうして私はお姉様ができることができないの?
――どうして私はお父様やお母様から愛してもらえないの?
暗闇の中で小さなキャロルが泣いている。
「きらい、きらい! みんな大きらい!」
大人になっても、どうしたら幸せになれるのかわからなかった。だから、いつも幸せそうに笑う姉が憎かった
姉が病気にかかって死んだ。
嬉しかった。これでようやく自分が幸せになれると思った。
でも何も変わらなかった。
ある日、姉の代わりにアルデラが現れた。
(そうか、この女のせいで私は幸せになれないのね)
アルデラにおかしな術をかけられた。そのとたんに世界が変わった。それは、心が身体から切り離され少し浮いたところから自分の姿を見ているような不思議な感覚だった。
この状態でやるべきことはたった一つ。
『アルデラ様の命令に従うこと』
これからは、それだけをすればいい。そのことになぜか救われた気分だった。
アルデラの言葉は絶対だった。だから他のことはすべて考えなくても良くなった。
他人が羨ましいとか、憎いとか。
誰にバカにされたとか、自分は不幸だとか。
何も考えずただフワフワと宙に浮いていると、キャロルは心がとても穏やかになっていることに気がついた。そうしていると、今までは見えてこなかったいろんなものが見えてきた。
子どものころからずっと側にいてくれているメイドは、キャロルが結婚した先の子爵家にもついて来てくれた。いつも「キャロル様、大丈夫ですか?」と心配してくれている。
地味で根暗な夫は、私に会うたびに一生懸命、話題を振ろうとしてくれている。
「私のことを気にかけてくれている人もいたのね……」
そんなことには少しも気がつかず、いつもイライラして八つ当たりをしていた。
アルデラの不思議な力のおかげで、今まで味わったことのなくらい平穏な日々が過ぎていった。それでも、小さなキャロルはまだ泣いている。
「この人達じゃダメなの! こんな人達に好かれても意味がないの!」
そう叫びながら泣いている。キャロルは「どうして?」と聞いてみた。
「だって、私のことを好きな人なんて、見る目がないバカばっかりだもの!」
「……そっか、そうよね」
愚かで性格が悪くて嫌われ者のキャロル。そんなキャロルを好きになる人なんてバカに違いない。だから、キャロルは必死にキャロルのことが嫌いな人達に近づいた。その人達こそが真実がわかっている優秀な人達だから。この人達に認められれば、自分も優秀になれると思い込んで。
その結果、キャロルはもっとバカにされた。何度も傷つけられた。
だから、心の中で小さなキャロルがずっと泣いている。大人になったキャロルはそっと彼女の隣に座った。
「……ごめんね。私が間違っていたわ」
無駄な感情から切り離された今ならわかる。
嫌われているなら、その人から離れればいい。
他人をバカにするような人達なんて、そもそも相手にしなくていい。
両親が愛してくれなくてもいい。キャロルを見てキャロルを大切にしてくれる人だけをキャロルも大切にすればいい。
「ごめんね。両親が愛してくれないのなら、私だけでも貴女を愛してあげれば良かった」
キャロルは泣きじゃくる小さなキャロルを抱きしめた。そして、ずっと両親に言ってほしかった言葉を伝えた。
「大好きよ。愛している。貴女は特別だわ。可愛いキャロル」
小さなキャロルは瞳を涙でいっぱいにして「本当?」と聞き返した。
「本当よ。だけど、気がつくのが少し遅かったみたい。ごめんね」
小さなキャロルはニコッと笑ってくれた。とても可愛い笑顔だった。
「貴女を幸せにしてあげられなくてごめんなさい」
――自分を大切にしなくてごめんなさい。
――私を大切にしてくれた人達をバカにしてごめんなさい。
「もう……全部、遅いね」
今さら気がついてももう遅い。なぜなら、キャロルはアルデラを守るために剣の前に立ちふさがってしまった。
アルデラに泣きながら「どうして?」と聞かれたけど、理由はキャロルもわからなかった。命令された訳でもないのに、ただ自然と身体が動いてしまった。
キャロルは小さなキャロルに謝った。
「ごめんね。最後の最後まで、私は私を大切にできなかったわ」
後悔で涙があふれた。いつの間に泣き止んだのか小さなキャロルがこちらを見つめている。
「いいよ。許してあげる」
小さな手で頭をなでてくれた。
「だってカッコ良かったもん。ご主人様を守るために敵の前に出るなんて、絵本の中の騎士様みたいだったよ。……切られちゃったけどね」
「そうね。切られちゃったわね」
フフッと二人で笑い合う。
「今度はもっとうまくやれるよ」
小さなキャロルはニコッと微笑むと、キャロルの中へと消えていった。
「今度……?」
眩い光に包まれてキャロルは目が覚めた。
目の前には見慣れた天井が広がっている。そこはキャロルの部屋のベッドの上だった。左手が温かい。見ると夫がキャロルの手を握りしめながら泣いていた。
「……どうして、泣いているの?」
声をかけると夫は勢い良く顔を上げた。
「キャロル! 気がついたのか? 良かった……」
胸をなでおろす夫の瞳から、またポロポロと涙が流れる。
何がなんだかわからないけど、なんとなく予想はついた。
(アルデラ様が不思議な力で、私を助けてくれたのね……)
終わったと思った人生は、もう少しだけ続くようだ。
(それなら……)
キャロルは握ってくれている夫の手をそっと握り返した。
「今までごめんなさい。心を入れ替えます。だから、だから、もし許されるのなら……」
――これからは貴方の側にいていいですか?
涙を流しながら夫が微笑んだ。
キャロルはその笑顔を『可愛い』と思った。
この日から数年後。子爵家夫妻が『仲の良い理想の夫婦』と憧れられ、『私もああなりたいわ』と国中の女性から羨ましがられる日がくることを彼女はまだ知らない。
(これでやっと終われるのね)
キャロルはゆっくりと目を閉じた。もう何も見なくていい。何も聞かなくていい。
物心がついたころから生きるのが辛かった。なんでもできる優秀な姉がいて、いつも姉と比べられていた。父も母も姉ばかりを可愛がった。
――どうして私はお姉様ができることができないの?
――どうして私はお父様やお母様から愛してもらえないの?
暗闇の中で小さなキャロルが泣いている。
「きらい、きらい! みんな大きらい!」
大人になっても、どうしたら幸せになれるのかわからなかった。だから、いつも幸せそうに笑う姉が憎かった
姉が病気にかかって死んだ。
嬉しかった。これでようやく自分が幸せになれると思った。
でも何も変わらなかった。
ある日、姉の代わりにアルデラが現れた。
(そうか、この女のせいで私は幸せになれないのね)
アルデラにおかしな術をかけられた。そのとたんに世界が変わった。それは、心が身体から切り離され少し浮いたところから自分の姿を見ているような不思議な感覚だった。
この状態でやるべきことはたった一つ。
『アルデラ様の命令に従うこと』
これからは、それだけをすればいい。そのことになぜか救われた気分だった。
アルデラの言葉は絶対だった。だから他のことはすべて考えなくても良くなった。
他人が羨ましいとか、憎いとか。
誰にバカにされたとか、自分は不幸だとか。
何も考えずただフワフワと宙に浮いていると、キャロルは心がとても穏やかになっていることに気がついた。そうしていると、今までは見えてこなかったいろんなものが見えてきた。
子どものころからずっと側にいてくれているメイドは、キャロルが結婚した先の子爵家にもついて来てくれた。いつも「キャロル様、大丈夫ですか?」と心配してくれている。
地味で根暗な夫は、私に会うたびに一生懸命、話題を振ろうとしてくれている。
「私のことを気にかけてくれている人もいたのね……」
そんなことには少しも気がつかず、いつもイライラして八つ当たりをしていた。
アルデラの不思議な力のおかげで、今まで味わったことのなくらい平穏な日々が過ぎていった。それでも、小さなキャロルはまだ泣いている。
「この人達じゃダメなの! こんな人達に好かれても意味がないの!」
そう叫びながら泣いている。キャロルは「どうして?」と聞いてみた。
「だって、私のことを好きな人なんて、見る目がないバカばっかりだもの!」
「……そっか、そうよね」
愚かで性格が悪くて嫌われ者のキャロル。そんなキャロルを好きになる人なんてバカに違いない。だから、キャロルは必死にキャロルのことが嫌いな人達に近づいた。その人達こそが真実がわかっている優秀な人達だから。この人達に認められれば、自分も優秀になれると思い込んで。
その結果、キャロルはもっとバカにされた。何度も傷つけられた。
だから、心の中で小さなキャロルがずっと泣いている。大人になったキャロルはそっと彼女の隣に座った。
「……ごめんね。私が間違っていたわ」
無駄な感情から切り離された今ならわかる。
嫌われているなら、その人から離れればいい。
他人をバカにするような人達なんて、そもそも相手にしなくていい。
両親が愛してくれなくてもいい。キャロルを見てキャロルを大切にしてくれる人だけをキャロルも大切にすればいい。
「ごめんね。両親が愛してくれないのなら、私だけでも貴女を愛してあげれば良かった」
キャロルは泣きじゃくる小さなキャロルを抱きしめた。そして、ずっと両親に言ってほしかった言葉を伝えた。
「大好きよ。愛している。貴女は特別だわ。可愛いキャロル」
小さなキャロルは瞳を涙でいっぱいにして「本当?」と聞き返した。
「本当よ。だけど、気がつくのが少し遅かったみたい。ごめんね」
小さなキャロルはニコッと笑ってくれた。とても可愛い笑顔だった。
「貴女を幸せにしてあげられなくてごめんなさい」
――自分を大切にしなくてごめんなさい。
――私を大切にしてくれた人達をバカにしてごめんなさい。
「もう……全部、遅いね」
今さら気がついてももう遅い。なぜなら、キャロルはアルデラを守るために剣の前に立ちふさがってしまった。
アルデラに泣きながら「どうして?」と聞かれたけど、理由はキャロルもわからなかった。命令された訳でもないのに、ただ自然と身体が動いてしまった。
キャロルは小さなキャロルに謝った。
「ごめんね。最後の最後まで、私は私を大切にできなかったわ」
後悔で涙があふれた。いつの間に泣き止んだのか小さなキャロルがこちらを見つめている。
「いいよ。許してあげる」
小さな手で頭をなでてくれた。
「だってカッコ良かったもん。ご主人様を守るために敵の前に出るなんて、絵本の中の騎士様みたいだったよ。……切られちゃったけどね」
「そうね。切られちゃったわね」
フフッと二人で笑い合う。
「今度はもっとうまくやれるよ」
小さなキャロルはニコッと微笑むと、キャロルの中へと消えていった。
「今度……?」
眩い光に包まれてキャロルは目が覚めた。
目の前には見慣れた天井が広がっている。そこはキャロルの部屋のベッドの上だった。左手が温かい。見ると夫がキャロルの手を握りしめながら泣いていた。
「……どうして、泣いているの?」
声をかけると夫は勢い良く顔を上げた。
「キャロル! 気がついたのか? 良かった……」
胸をなでおろす夫の瞳から、またポロポロと涙が流れる。
何がなんだかわからないけど、なんとなく予想はついた。
(アルデラ様が不思議な力で、私を助けてくれたのね……)
終わったと思った人生は、もう少しだけ続くようだ。
(それなら……)
キャロルは握ってくれている夫の手をそっと握り返した。
「今までごめんなさい。心を入れ替えます。だから、だから、もし許されるのなら……」
――これからは貴方の側にいていいですか?
涙を流しながら夫が微笑んだ。
キャロルはその笑顔を『可愛い』と思った。
この日から数年後。子爵家夫妻が『仲の良い理想の夫婦』と憧れられ、『私もああなりたいわ』と国中の女性から羨ましがられる日がくることを彼女はまだ知らない。