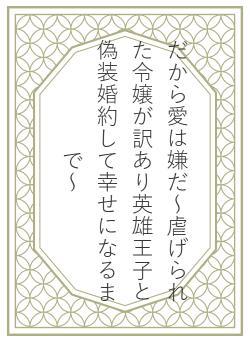ただ白魔術師のサラサは、魔術で他人に害を与えることができない。そのできないことをできるようにしているのが、この魔道具の首輪だ。
(おそらく、この首輪をつけると、『サラサに自分の魔力を捧げます』と契約したことになるのね)
白魔術は『回復や癒すことしかできない』という根底ルールは誰にも変えられないので、魔道具を使うことにより、『魔力提供の許可を受けた人物から、自身の魔力を回復するために魔力をわけてもらっている』というこじつけならできないこともない。
(でも、これは私の想像であって、真実ではないわ)
自分の首についた首輪にアルデラはそっとふれた。
(青い石がついた首輪が手に入れば真実がわかるかも?)
アルデラは、わざとフラッと身体を傾けた。
「どうしたの?」
すぐに心配そうなサラサの声がする。
「申し訳ありません。急にめまいが。少し疲れたようです」
サラサは椅子から立ち上がると、そっと腕を伸ばしてアルデラの頬にふれた。サラサにふれられた頬が、じんわりと温かくなっていく。それと共に、エネルギーを注がれたように身体が軽くなった。
(これが白魔術)
手を離したサラサは、「これでもう大丈夫よ。でも、今日はゆっくり休んでね。貴女の部屋へ案内するわ」と言いながら、アルデラの黒髪を優しくなでた。
(この優しさが平等で本物だったら、彼女はまさしく聖女なのにね)
サラサのお気に入りの美形男子の一人に部屋へと案内された。扉を開けるとメルヘンな空間が広がっている。
たっぷりのレースがついた黒いカーテンや、リボンまみれのベッドを見て、アルデラはため息をついた。
(サラサの私のイメージっていったい……?)
しばらく部屋で大人しくしていると、ノックの後にブラッドと銀髪騎士がそろって入ってくる。
ブラッドに「アルデラ様、ご無事で?」と確認されたので、アルデラは頷きながら「そちらはどうだった?」と聞き返すと、ブラッドは指で自身のメガネを押し上げた。
「アルデラ様の指示通り、ここを辞めて言った者について聞き込みをしました。多くの者が『体調不良』だったそうです。仕事中に倒れた者もいたようで。辞めたあとに亡くなったらしいというウワサもあるそうです」
「なるほどね」
サラサが魔道具の首輪を使って魔力を奪っていることは間違いないようだ。
「この首輪は魔道具よ。サラサは首輪をつけた者から魔力を奪うことができるわ。黄色い石の首輪をつけた者は愛玩用。青い石の首輪をつけた者は、サラサの魔力の供給源として飼われているようね」
銀髪騎士が「……は?」と声を漏らした。
「ちょっと待ってくれ! 青い石は……なんだって?」
ブラッドが「アルデラ様に無礼な口を聞くな!」と注意したけど、騎士はそれどころではないようだ。
「お願いだ、もう一度、言ってくれ!」
アルデラは「青い石の首輪をつけた者は、サラサから魔力を奪われているわ。魔力は一度に多く奪われると衰弱死してしまうことがあるくらい危険よ」と言葉を繰り返す。
騎士は「は、はは……」と乾いた声で笑ったあとに「あのクソ女ぁあ!!」と大声で叫んだ。
アルデラが「どうしたの?」と尋ねると、騎士は怒りで顔を赤くして頬を痙攣させる。
「あの女、俺の妹を治癒した後に、『お守りだから』と『体調を安定させるためよ』っつって、この首輪を妹にも渡してるんだ! しかも、青い石のやつを!!」
「貴方の妹もこの首輪をつけているの?」
「ああ、『そうすれば体調が良くなる』って、あのクソ女に言われたんだよ!」
「落ち着いて。妹さんは無事なの?」
荒い呼吸を繰り返しながら騎士は頷いた。
「……手紙のやりとりをしている」
「だったら、大丈夫よ。妹さんに首輪をつけさせたのは、たぶん、貴方が逃げようとしたときの人質にするためだわ」
安堵からか、騎士は肩を落として深いため息をついた。
「あのクソ女だけは許さねぇ……殺す」
呪いの言葉と共に騎士の周りに『殺意』と言う名の黒いモヤが広がっていく。腰の剣に手をかけ、今にも部屋から飛び出していきそうな騎士をアルデラは制止した。
「少し落ち着きなさい。王宮お抱えの白魔術師を殺したら、貴方も妹さんも、ただではすまないわ」
騎士はグッと言葉に詰まる。
「だったら、アンタはあの女をどうするつもりなんだよ!?」
「それはもちろん」
アルデラは、酷薄そうに瞳を細めて口端をあげた。
「私がサラサの飼い主になって、しっかりと躾けてあげるのよ」
*
その日の夜、アルデラの部屋の扉が開き、複数の人が入って来る気配がした。
アルデラがベッドの上で上半身を起こすと、侵入者は悪びれもせず部屋の明かりをつけた。そこには、サラサとサラサに侍っていた二人の美形男子が立っていた。
サラサは語尾にハートマークをつけるかのように、ねっとりとアルデラの愛称を呼ぶ。
「アル」
ゾクッとアルデラに悪寒が走った。
「ねぇ、わたくし達、もっと仲良くなれると思うの」
そう囁きながらサラサはベッドに近づいてくる。
(まさか、本当に向こうからくるなんて……)
銀髪騎士に『夜になったらサラサがこの部屋にくるぞ。気をつけろ』と言われていたけど正直、半信半疑だった。
近づいてきたサラサは、「可哀想に。クリスとは白い結婚なのでしょう? クリスが教えてくれなかったこと、私がアルにたくさん教えてあげるわぁ」と怪しい笑みを浮かべている。
アルデラが美形男子二人を指さし、「後ろの人達は?」と尋ねると、サラサは「今日は、皆で一緒に楽しもうと思ってぇ」とウィンクした。
思わず深いため息が出てしまう。
「完っ全にアウトよ!」
アルデラがそう叫ぶと、クローゼットに隠れていたブラッドと銀髪騎士が飛び出し、素早く美形男子達を取り押さえた。
サラサは「なぁに?」と言いながら少しもあせる様子を見せない。
「わたくしに歯向かうということは、王家に歯向かうということになるのよ? それに……」
サラサの身体が一瞬、白い光に包まれた。
「ふふっ、白魔術だって、魔力量さえ多ければ、こんなこともできるんだから」
白い光が、ブラッドと銀髪騎士に流れていくと、二人は急に苦しみだす。
「なるほどね。癒す必要のない人を、強制的に癒し続けて身体に不具合をおこさせているって感じかしら? その方法で、この騎士の妹さんも苦しめて、治す振りでもした?」
アルデラはベッドから下りると黒魔術セットを入れているバスケットを開いた。そして、緑の髪束を取りだしそのまま黒魔術を発動させる。
「サラサの魔術を封じて」
髪束が勢いよく黒い炎に包まれると、白い光が徐々に弱くなっていく。サラサはゆっくりとアルデラを振り返った。
「なぁに? 何をしたの?」
「私の黒魔術で貴女の白魔術を一時的に封じたわ」
サラサはとても可笑しそうに笑い声を上げた。
「卑しい黒魔術では、高貴な白魔術を封じることなんてできないわ。わたくしが今までいったいどれほどの人助けをしてきたと思っているの?」
「そうね、黒魔術では穢れのない魂を呪い殺すには、とんでもない代償が必要になるわ」
「そうでしょう? 見て。私の周りの輝きを」
サラサは両手を広げた。彼女の周りの空気はキラキラと輝いている。
「わたくしは、何も悪いことはしていないわ。ただ、行った善行と同価値の褒美をもらっているだけ。この輝きがその証拠よ」
アルデラは「本当に『同価値』かしら? うまく騙して相手に気がつかせていないだけじゃない?」と少し首をかしげた。
「同価値よ。だって、わたくし、誰にも恨まれていないもの。誰も私を疑わないわ」
「なるほど『死人に口なし』ってことね」
その言葉に同意するように、ニィと悪魔のようにサラサは微笑む。アルデラはあらかじめ身につけていた、真紅のアクセサリーにふれた。このアクセサリーは魔術の増幅効果があり、黒魔術の代償としても使える魔道具だ。これを使って広範囲で黒魔術を発動させる。
「サラサに魔力を奪われて亡くなった人達を実体化して」
パキパキと赤い宝石が割れる音がする。砕け散った宝石は床に落ちると黒く激しい炎に包まれた。燃え盛る黒い炎はバチッと弾けて勢いよくあちらこちらへ飛んでいく。
その炎の一つが、アルデラの部屋の床に黒い焼け跡を作ったかと思うと、そこから黒いモヤに包まれた青年が現れた。
しばらく、ぼうっとしていた青年は、サラサを見つけるとニコリと微笑みかけた。
『サラ、さ、様』
サラサの眉がピクリと動いた。
『なんだか、最近、体調が悪いの、です』
青年はフラフラしながらサラサに近づいてくる。
『サラサ様、愛しています。飽きたなんて言わないで。私をまたお側においてください』
そう囁く青年の首には、青い石の首輪がついている。サラサのお気に入り男達は、青年を見て「お前、死んだばずじゃ……」と声を漏らした。
「なるほど、そう言うってことは、貴方たちはサラサが何をしていたのか知っているのね?」
アルデラが微笑みかけると、美形男子達は顔を青くしたけど、サラサは顔色一つ変えなかった。
「これ、なぁに? 子ども騙しね」
サラサからあふれ出る白い光と共に、黒いモヤに包まれた青年は消えた。
「こんなことで、わたくしを脅したつもり?」
アルデラは「しっ、静かに」と囁くと、人差し指を自身の唇に当てた。
静まり返った室内の外から、複数の悲鳴や何かが割れる音が聞こえてくる。
「なに? アル、何をしたの!?」
「何って、今の見ていたでしょう? 私の黒魔術で、貴女が魔力を奪って殺した人達全員を実体化したのよ。この屋敷中に今の青年のような死者があふれ返っているわ。さて、皆、貴女のことどう思っているのかしら? 全ての人が、さっきの青年みたいに死ぬ直前まで騙されて貴女を愛してくれていたらいいわね」
ここまで規模が大きければ、サラサは自分の魔力だけで対処できず、他人から魔力を奪うかもしれない。それは予想通りで、さすがに顔色を変えたサラサは、慌てて胸元からネックレスを取りだした。そこには首輪と同じような、黄色と青い石がついている。
「ブラッド、あれを奪って」
「はい!」
素早く飛び出したブラッドは、サラサのネックレスを思いっきり引っ張った。悲鳴と共に体制を崩したサラサの首から、ブラッドはネックレスの鎖部分だけを器用に剣で切るということをやってのける。
次の瞬間には、サラサがつけてたネックレスは、アルデラに捧げられていた。
「どうぞ、アルデラ様」
ブラッドからネックレスを受け取ると、サラサは「返しなさい!」と叫んだ。
「ふーん、これで全ての首輪の魔道具をコントロールしていたのね?」
アルデラが魔道具に自分の魔力を注ぐと、黄色と青色の石が真っ黒に染まっていく。
しばらくすると、パチンと音がしてアルデラがつけていた首輪が取れた。
気がつけば、サラサを取り囲むキラキラした空気が、黒いモヤへと変わっていっている。そのモヤには、サラサへの恨みや憎悪が見て取れた。
「貴女の悪事、順調に広まっているみたいね」
サラサが「あ、ああ」と視線を彷徨わせて、すがるように美形男子達を見たが、首輪が取れた美形男子達はサラサを助けることもなく、逃げ出そうとしたので、銀髪騎士が二人を殴って気絶させた。
「さて、サラサ」
アルデラが声をかけると、サラサはガクガクとふるえながら床に座り込んだ。
「貴女は、もう他人から魔力は奪えないけど私と戦ってみる?」
青い顔をしたサラサは、無言で首を左右に振る。
「そうね、今の穢れた魂の貴女なら、簡単に呪い殺せてしまうから、その方が賢明ね」
アルデラはサラサの目の前に、石が黒くなってしまったネックレスを突きつけた。
「この魔道具、どこで手に入れたの?」
質問の意味がわからないようでサラサは少し首をかしげた。
「この魔道具がなければ、白魔術師である貴女はここまで人を殺(あや)めることはできなかったはず。貴女の罪はとても重いわ。もちろん、償ってもらう。でも、この魔道具を作った人物の罪も見逃せない」
「それは、陛下の……」
「陛下?」
すっかり大人しくなったサラサは、ハッと自身の口を両手でふさいだ。
「陛下ってことは、この国の国王ね? 陛下の何?」
黙ってうつむくサラサの首に黒い石の首輪をつけようとしたら、嫌がって暴れたので、ブラッドに取り押さえられている。
アルデラは「自分がされて嫌なことを、人にしたらダメでしょう?」と言いながら、サラサの首に首輪をつけた。ついでに気を失っている美形男子二人の首にも首輪をつけておく。
「この二人には、あとから事情を聞きましょう」
どこまでサラサの悪事に加担していたかによって、二人の対処は変わってくる。
「わ、わたくしをどうするの? こ、殺すの?」
その言葉に銀髪騎士が「当たり前だろう!」と怒鳴ったが、アルデラは首を振った。
「残念だけど、今は殺さないわ。サラサに魔道具を渡した奴、そして、サラサの白魔術を利用して甘い汁を吸っていた奴らが必ずいる。サラサをエサにそいつらを全員引きずり出すのよ。でも、まぁそれでも怒りは収まらないでしょう?」
アルデラは銀髪騎士に、黒い石がついたネックレスを手渡した。
「サラサは貴方の好きにしていいわ。何をしても良い。ただし、命だけは取らないで」
ネックレスを握りしめた銀髪騎士がサラサをにらみつけると、サラサは「ひっ」と悲鳴を漏らした。
「俺の妹が病気になったのは、お前のせいか?」
サラサはふるえながら頷いた。
「どうしてそんなことをした!? 答えろ!」
「あ、あなたが、ほしくて……」
「俺を手に入れるために? そんなくだらないことのために、妹を苦しめたのか!?」
「ご、ごめんなさい! ごめんなさい!」
銀髪騎士は苦しそうに右腕を振り上げた。しかし、振り上げた腕はいつまでも振り下ろされない。
「クソッ、殺してやりたいくらい憎いが、この女を痛めつけても妹は喜ばない。反抗できない人間を自分の思い通りにするようなクソ女と、俺は同類にはなりたくない!」
そう叫ぶと銀髪騎士は、ネックレスをアルデラに返した。
「甘いわね。私だったらサラサをボコボコにするのに」
アルデラがため息をつくと、騎士は「……俺は役に立ちませんね。アルデラ様に相応しくない」とうなだれた。
「そういえば、貴方、名前は?」
騎士は力なく「コーギルです」と名乗った。
「コーギル、貴方を雇いたいわ。伯爵家は、ちょうど人手が足りなかったの」
勢いよく顔を上げたコーギルにアルデラは微笑みかけた。
「私とブラッドは少し過激すぎるから、貴方みたいな人もいてくれたほうが良いと思うわ」
(おそらく、この首輪をつけると、『サラサに自分の魔力を捧げます』と契約したことになるのね)
白魔術は『回復や癒すことしかできない』という根底ルールは誰にも変えられないので、魔道具を使うことにより、『魔力提供の許可を受けた人物から、自身の魔力を回復するために魔力をわけてもらっている』というこじつけならできないこともない。
(でも、これは私の想像であって、真実ではないわ)
自分の首についた首輪にアルデラはそっとふれた。
(青い石がついた首輪が手に入れば真実がわかるかも?)
アルデラは、わざとフラッと身体を傾けた。
「どうしたの?」
すぐに心配そうなサラサの声がする。
「申し訳ありません。急にめまいが。少し疲れたようです」
サラサは椅子から立ち上がると、そっと腕を伸ばしてアルデラの頬にふれた。サラサにふれられた頬が、じんわりと温かくなっていく。それと共に、エネルギーを注がれたように身体が軽くなった。
(これが白魔術)
手を離したサラサは、「これでもう大丈夫よ。でも、今日はゆっくり休んでね。貴女の部屋へ案内するわ」と言いながら、アルデラの黒髪を優しくなでた。
(この優しさが平等で本物だったら、彼女はまさしく聖女なのにね)
サラサのお気に入りの美形男子の一人に部屋へと案内された。扉を開けるとメルヘンな空間が広がっている。
たっぷりのレースがついた黒いカーテンや、リボンまみれのベッドを見て、アルデラはため息をついた。
(サラサの私のイメージっていったい……?)
しばらく部屋で大人しくしていると、ノックの後にブラッドと銀髪騎士がそろって入ってくる。
ブラッドに「アルデラ様、ご無事で?」と確認されたので、アルデラは頷きながら「そちらはどうだった?」と聞き返すと、ブラッドは指で自身のメガネを押し上げた。
「アルデラ様の指示通り、ここを辞めて言った者について聞き込みをしました。多くの者が『体調不良』だったそうです。仕事中に倒れた者もいたようで。辞めたあとに亡くなったらしいというウワサもあるそうです」
「なるほどね」
サラサが魔道具の首輪を使って魔力を奪っていることは間違いないようだ。
「この首輪は魔道具よ。サラサは首輪をつけた者から魔力を奪うことができるわ。黄色い石の首輪をつけた者は愛玩用。青い石の首輪をつけた者は、サラサの魔力の供給源として飼われているようね」
銀髪騎士が「……は?」と声を漏らした。
「ちょっと待ってくれ! 青い石は……なんだって?」
ブラッドが「アルデラ様に無礼な口を聞くな!」と注意したけど、騎士はそれどころではないようだ。
「お願いだ、もう一度、言ってくれ!」
アルデラは「青い石の首輪をつけた者は、サラサから魔力を奪われているわ。魔力は一度に多く奪われると衰弱死してしまうことがあるくらい危険よ」と言葉を繰り返す。
騎士は「は、はは……」と乾いた声で笑ったあとに「あのクソ女ぁあ!!」と大声で叫んだ。
アルデラが「どうしたの?」と尋ねると、騎士は怒りで顔を赤くして頬を痙攣させる。
「あの女、俺の妹を治癒した後に、『お守りだから』と『体調を安定させるためよ』っつって、この首輪を妹にも渡してるんだ! しかも、青い石のやつを!!」
「貴方の妹もこの首輪をつけているの?」
「ああ、『そうすれば体調が良くなる』って、あのクソ女に言われたんだよ!」
「落ち着いて。妹さんは無事なの?」
荒い呼吸を繰り返しながら騎士は頷いた。
「……手紙のやりとりをしている」
「だったら、大丈夫よ。妹さんに首輪をつけさせたのは、たぶん、貴方が逃げようとしたときの人質にするためだわ」
安堵からか、騎士は肩を落として深いため息をついた。
「あのクソ女だけは許さねぇ……殺す」
呪いの言葉と共に騎士の周りに『殺意』と言う名の黒いモヤが広がっていく。腰の剣に手をかけ、今にも部屋から飛び出していきそうな騎士をアルデラは制止した。
「少し落ち着きなさい。王宮お抱えの白魔術師を殺したら、貴方も妹さんも、ただではすまないわ」
騎士はグッと言葉に詰まる。
「だったら、アンタはあの女をどうするつもりなんだよ!?」
「それはもちろん」
アルデラは、酷薄そうに瞳を細めて口端をあげた。
「私がサラサの飼い主になって、しっかりと躾けてあげるのよ」
*
その日の夜、アルデラの部屋の扉が開き、複数の人が入って来る気配がした。
アルデラがベッドの上で上半身を起こすと、侵入者は悪びれもせず部屋の明かりをつけた。そこには、サラサとサラサに侍っていた二人の美形男子が立っていた。
サラサは語尾にハートマークをつけるかのように、ねっとりとアルデラの愛称を呼ぶ。
「アル」
ゾクッとアルデラに悪寒が走った。
「ねぇ、わたくし達、もっと仲良くなれると思うの」
そう囁きながらサラサはベッドに近づいてくる。
(まさか、本当に向こうからくるなんて……)
銀髪騎士に『夜になったらサラサがこの部屋にくるぞ。気をつけろ』と言われていたけど正直、半信半疑だった。
近づいてきたサラサは、「可哀想に。クリスとは白い結婚なのでしょう? クリスが教えてくれなかったこと、私がアルにたくさん教えてあげるわぁ」と怪しい笑みを浮かべている。
アルデラが美形男子二人を指さし、「後ろの人達は?」と尋ねると、サラサは「今日は、皆で一緒に楽しもうと思ってぇ」とウィンクした。
思わず深いため息が出てしまう。
「完っ全にアウトよ!」
アルデラがそう叫ぶと、クローゼットに隠れていたブラッドと銀髪騎士が飛び出し、素早く美形男子達を取り押さえた。
サラサは「なぁに?」と言いながら少しもあせる様子を見せない。
「わたくしに歯向かうということは、王家に歯向かうということになるのよ? それに……」
サラサの身体が一瞬、白い光に包まれた。
「ふふっ、白魔術だって、魔力量さえ多ければ、こんなこともできるんだから」
白い光が、ブラッドと銀髪騎士に流れていくと、二人は急に苦しみだす。
「なるほどね。癒す必要のない人を、強制的に癒し続けて身体に不具合をおこさせているって感じかしら? その方法で、この騎士の妹さんも苦しめて、治す振りでもした?」
アルデラはベッドから下りると黒魔術セットを入れているバスケットを開いた。そして、緑の髪束を取りだしそのまま黒魔術を発動させる。
「サラサの魔術を封じて」
髪束が勢いよく黒い炎に包まれると、白い光が徐々に弱くなっていく。サラサはゆっくりとアルデラを振り返った。
「なぁに? 何をしたの?」
「私の黒魔術で貴女の白魔術を一時的に封じたわ」
サラサはとても可笑しそうに笑い声を上げた。
「卑しい黒魔術では、高貴な白魔術を封じることなんてできないわ。わたくしが今までいったいどれほどの人助けをしてきたと思っているの?」
「そうね、黒魔術では穢れのない魂を呪い殺すには、とんでもない代償が必要になるわ」
「そうでしょう? 見て。私の周りの輝きを」
サラサは両手を広げた。彼女の周りの空気はキラキラと輝いている。
「わたくしは、何も悪いことはしていないわ。ただ、行った善行と同価値の褒美をもらっているだけ。この輝きがその証拠よ」
アルデラは「本当に『同価値』かしら? うまく騙して相手に気がつかせていないだけじゃない?」と少し首をかしげた。
「同価値よ。だって、わたくし、誰にも恨まれていないもの。誰も私を疑わないわ」
「なるほど『死人に口なし』ってことね」
その言葉に同意するように、ニィと悪魔のようにサラサは微笑む。アルデラはあらかじめ身につけていた、真紅のアクセサリーにふれた。このアクセサリーは魔術の増幅効果があり、黒魔術の代償としても使える魔道具だ。これを使って広範囲で黒魔術を発動させる。
「サラサに魔力を奪われて亡くなった人達を実体化して」
パキパキと赤い宝石が割れる音がする。砕け散った宝石は床に落ちると黒く激しい炎に包まれた。燃え盛る黒い炎はバチッと弾けて勢いよくあちらこちらへ飛んでいく。
その炎の一つが、アルデラの部屋の床に黒い焼け跡を作ったかと思うと、そこから黒いモヤに包まれた青年が現れた。
しばらく、ぼうっとしていた青年は、サラサを見つけるとニコリと微笑みかけた。
『サラ、さ、様』
サラサの眉がピクリと動いた。
『なんだか、最近、体調が悪いの、です』
青年はフラフラしながらサラサに近づいてくる。
『サラサ様、愛しています。飽きたなんて言わないで。私をまたお側においてください』
そう囁く青年の首には、青い石の首輪がついている。サラサのお気に入り男達は、青年を見て「お前、死んだばずじゃ……」と声を漏らした。
「なるほど、そう言うってことは、貴方たちはサラサが何をしていたのか知っているのね?」
アルデラが微笑みかけると、美形男子達は顔を青くしたけど、サラサは顔色一つ変えなかった。
「これ、なぁに? 子ども騙しね」
サラサからあふれ出る白い光と共に、黒いモヤに包まれた青年は消えた。
「こんなことで、わたくしを脅したつもり?」
アルデラは「しっ、静かに」と囁くと、人差し指を自身の唇に当てた。
静まり返った室内の外から、複数の悲鳴や何かが割れる音が聞こえてくる。
「なに? アル、何をしたの!?」
「何って、今の見ていたでしょう? 私の黒魔術で、貴女が魔力を奪って殺した人達全員を実体化したのよ。この屋敷中に今の青年のような死者があふれ返っているわ。さて、皆、貴女のことどう思っているのかしら? 全ての人が、さっきの青年みたいに死ぬ直前まで騙されて貴女を愛してくれていたらいいわね」
ここまで規模が大きければ、サラサは自分の魔力だけで対処できず、他人から魔力を奪うかもしれない。それは予想通りで、さすがに顔色を変えたサラサは、慌てて胸元からネックレスを取りだした。そこには首輪と同じような、黄色と青い石がついている。
「ブラッド、あれを奪って」
「はい!」
素早く飛び出したブラッドは、サラサのネックレスを思いっきり引っ張った。悲鳴と共に体制を崩したサラサの首から、ブラッドはネックレスの鎖部分だけを器用に剣で切るということをやってのける。
次の瞬間には、サラサがつけてたネックレスは、アルデラに捧げられていた。
「どうぞ、アルデラ様」
ブラッドからネックレスを受け取ると、サラサは「返しなさい!」と叫んだ。
「ふーん、これで全ての首輪の魔道具をコントロールしていたのね?」
アルデラが魔道具に自分の魔力を注ぐと、黄色と青色の石が真っ黒に染まっていく。
しばらくすると、パチンと音がしてアルデラがつけていた首輪が取れた。
気がつけば、サラサを取り囲むキラキラした空気が、黒いモヤへと変わっていっている。そのモヤには、サラサへの恨みや憎悪が見て取れた。
「貴女の悪事、順調に広まっているみたいね」
サラサが「あ、ああ」と視線を彷徨わせて、すがるように美形男子達を見たが、首輪が取れた美形男子達はサラサを助けることもなく、逃げ出そうとしたので、銀髪騎士が二人を殴って気絶させた。
「さて、サラサ」
アルデラが声をかけると、サラサはガクガクとふるえながら床に座り込んだ。
「貴女は、もう他人から魔力は奪えないけど私と戦ってみる?」
青い顔をしたサラサは、無言で首を左右に振る。
「そうね、今の穢れた魂の貴女なら、簡単に呪い殺せてしまうから、その方が賢明ね」
アルデラはサラサの目の前に、石が黒くなってしまったネックレスを突きつけた。
「この魔道具、どこで手に入れたの?」
質問の意味がわからないようでサラサは少し首をかしげた。
「この魔道具がなければ、白魔術師である貴女はここまで人を殺(あや)めることはできなかったはず。貴女の罪はとても重いわ。もちろん、償ってもらう。でも、この魔道具を作った人物の罪も見逃せない」
「それは、陛下の……」
「陛下?」
すっかり大人しくなったサラサは、ハッと自身の口を両手でふさいだ。
「陛下ってことは、この国の国王ね? 陛下の何?」
黙ってうつむくサラサの首に黒い石の首輪をつけようとしたら、嫌がって暴れたので、ブラッドに取り押さえられている。
アルデラは「自分がされて嫌なことを、人にしたらダメでしょう?」と言いながら、サラサの首に首輪をつけた。ついでに気を失っている美形男子二人の首にも首輪をつけておく。
「この二人には、あとから事情を聞きましょう」
どこまでサラサの悪事に加担していたかによって、二人の対処は変わってくる。
「わ、わたくしをどうするの? こ、殺すの?」
その言葉に銀髪騎士が「当たり前だろう!」と怒鳴ったが、アルデラは首を振った。
「残念だけど、今は殺さないわ。サラサに魔道具を渡した奴、そして、サラサの白魔術を利用して甘い汁を吸っていた奴らが必ずいる。サラサをエサにそいつらを全員引きずり出すのよ。でも、まぁそれでも怒りは収まらないでしょう?」
アルデラは銀髪騎士に、黒い石がついたネックレスを手渡した。
「サラサは貴方の好きにしていいわ。何をしても良い。ただし、命だけは取らないで」
ネックレスを握りしめた銀髪騎士がサラサをにらみつけると、サラサは「ひっ」と悲鳴を漏らした。
「俺の妹が病気になったのは、お前のせいか?」
サラサはふるえながら頷いた。
「どうしてそんなことをした!? 答えろ!」
「あ、あなたが、ほしくて……」
「俺を手に入れるために? そんなくだらないことのために、妹を苦しめたのか!?」
「ご、ごめんなさい! ごめんなさい!」
銀髪騎士は苦しそうに右腕を振り上げた。しかし、振り上げた腕はいつまでも振り下ろされない。
「クソッ、殺してやりたいくらい憎いが、この女を痛めつけても妹は喜ばない。反抗できない人間を自分の思い通りにするようなクソ女と、俺は同類にはなりたくない!」
そう叫ぶと銀髪騎士は、ネックレスをアルデラに返した。
「甘いわね。私だったらサラサをボコボコにするのに」
アルデラがため息をつくと、騎士は「……俺は役に立ちませんね。アルデラ様に相応しくない」とうなだれた。
「そういえば、貴方、名前は?」
騎士は力なく「コーギルです」と名乗った。
「コーギル、貴方を雇いたいわ。伯爵家は、ちょうど人手が足りなかったの」
勢いよく顔を上げたコーギルにアルデラは微笑みかけた。
「私とブラッドは少し過激すぎるから、貴方みたいな人もいてくれたほうが良いと思うわ」