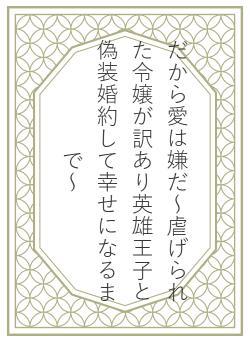ブラッドにブローチを奪われ、呆然としていた公爵もようやく我に返ったようで、「それを返せ!」と叫んだ。
「それは、私のように選ばれた者が持つものだ」
「選ばれた者、ね。この家の紋章が入っているし、もしかして、このブローチが、公爵家当主の証し?」
「だったらなんだ!?」
この公爵家は、過去に王家の危機を救ったとされる英雄の魔術師を先祖に持っている。
(確か、恐ろしい黒魔術師がこの国を滅ぼそうとしたときに、ご先祖様が退治して、逆に黒魔術を自分のものにしたのよね)
それ以降、公爵家の一族の中には、黒魔術が使える者が出てくるようになり、一族の中で、黒魔術が最も強いものが代々公爵家の当主に選ばれた。
そして、最も黒魔術が強いはずの現当主は、今、守ってくれるブローチを奪われ、実体化した黒い物体に襲われ叫んでいる。
「う、うわぁあ!?」
「現当主の黒魔術の実力がこの程度だったら、本当ならアルデラが当主になっていたんじゃないの?」
そう呟いて、アルデラは気がついた。
「ああ、そっか。これこそが、『公爵がずっと恐れてきたこと』だったのね」
自分より遥かに強い黒魔術の素質を持った娘が生まれ、殺そうとしても黒魔術に守られ殺せない。十五歳になっても黒魔術が発現せず安堵していたところに、術を使いこなせるようになった娘が戻って来てしまった。
アルデラはニタリと笑い、楽しそうに瞳を細めた。
「なるほど、今から私が公爵家の真の当主ってことね」
「違う! 当主は私だ! 『使い魔』どこだ!? 私を助けろ!」
「使い魔?」
アルデラが不思議に思っていると、どこからともなく全身黒ずくめの人物が現れた。
「来たか、使い魔!」
使い魔と呼ばれた人物が短剣を一振りすると、公爵を襲っていた黒い人型の物体が霧散する。
「へぇ、やるじゃない」
憎悪が実体化した物体を祓える武器は、神殿で祝福を受けたものだけだ。
「いいぞ使い魔、アイツらを早く殺せ!」
公爵に命令され、こちらを振り返った使い魔は、黒い仮面で顔を覆っていて性別すらわからない。素早く切りかかって来た使い魔の一撃をブラッドが剣で弾いた。
「アルデラ様、お下がりください!」
(『使い魔』って、もしかして、公爵家の当主に仕える忍者的な人? それとも、お金で雇われている暗殺者ってやつ?)
どちらにしろ強そうだ。アルデラが、いくら最強の黒魔術使いでも、黒魔術を発動させる前に倒されてしまったら負けてしまう。
(素早い敵は厄介だわ)
ブラッドの背後に隠れながら、緑の髪束から急いで髪を引き抜いた。そのとたんに、使い魔が高く宙を舞いブラッドを飛び越えた。
使い魔の短剣がアルデラの目の前に迫る。
(あ、死んだ……)
アルデラが死を覚悟した瞬間、ピタリと短剣が止まった。そして、仮面の下からくぐもった声が聞こえる。
「……どうして? ここに、戻って来たの?」
そのポツリポツリと話す、独特な話し方には聞き覚えがあった。
「え? もしかして、お姉ちゃん?」
両親に見捨てられたアルデラにいろいろと教えてくれた、どこの誰だかわからないお姉ちゃん。一本のキャンディを半分こして一緒に食べたお姉ちゃん。
公爵が「早く殺せ!」と叫び、使い魔はビクッと身体を動かせた。背後からブラッドに切りかかられ、使い魔は器用に避ける。
「使い魔、何をしている!? 当主の命令は絶対だろうが!?」
公爵の言葉を聞いてアルデラは微笑んだ。
「ああ、そういうこと?」
この『使い魔』と呼ばれる存在は、公爵家の当主に忠誠を誓っているらしい。
(だったら、簡単)
アルデラは手に持っていたブローチを使い魔に見えるように掲げた。
「お姉ちゃん、この家の本当の当主は私よ。私はこの家を出てから黒魔術が使えるようになったの。そこにいる男は、私の足元にも及ばない」
「そう、なの?」
「そうなの!」
使い魔が構えていた短剣を下ろすと「本当だ。命令に背いても、痛くない」と呟いた。その言葉は聞き捨てならない。
「お姉ちゃん、痛いことされてたの!?」
使い魔は袖をめくり右腕をこちらに見せた。そこには、ブローチと同じ琥珀色の石が肌に直接、埋め込まれていた。
「当主の命令は、絶対。背くと、この石がとても痛くなる」
アルデラが公爵を睨みつけると、公爵は狼狽えた。
「馬鹿め! そいつは人間ではないわ! 代々当主に仕えるために作られたバケモノだ!」
アルデラは「だったら何?」と言いながら、手に持っていた緑の髪を握りしめた。
「本当のバケモノは、アンタよ。お姉ちゃんが今まで味わった苦しみを、あの男にも」
緑の髪が黒い炎に包まれると、使い魔の腕から琥珀色の石がポロリと落ちた。そして、公爵の額へと飛んでいき、その肌へとめり込んでいく。
「ひっ! う、うわぁあああ!?」
絶叫が辺りに響いた。額を押さえながら床にうずくまった公爵をアルデラは見下ろす。
「これでアンタが、私の使い魔になったってことね?」
勢いよく顔を上げた公爵の顔からは血の気が引いていた。アルデラは黒髪を指でもてあそびながら、「お父さまぁ、おねがーい」と甘えた声を出す。
「今すぐ伯爵家に支払うはずだった持参金を払ってぇ。あと、これから毎年、今まで私に使うはずだったお金を伯爵家に振り込んでぇ。使用人はイジメないでぇ。暴力も暴言もダメよ、パパぁ」
「ふ、ふざけるなっ!」
怒りで唇を震わせている公爵に、アルデラは微笑みかけた。
「主に逆らう気?」
そのとたんに、額の石が輝き公爵は激痛に叫び、のたうち回った。
「い、痛い! や、やめろ!」
「やめろ?」
「やめてくれ! や、やめてください!」
公爵がそう叫ぶと、石の光は消えていく。公爵は涙を流しながら、荒い呼吸を繰り返した。
「この頭の悪い使い魔は、私の命令をちゃんと理解したかしら?」
公爵がこちらを睨みつけてきたので、アルデラはそっと公爵に顔を近づけた。
「そんなに生意気な態度だと、公爵夫人のように消しちゃうぞ」
パチンとウィンクをすると、公爵の顔から血の気が失せた。真っ白になった公爵は項垂れ小刻みに震えている。
「さぁ、主に敬意を払いなさい」
公爵は歯ぎしりをしながら、両手を強く握りしめた。
「……我が主、アルデラさ、ま」
「そうね。じゃあ、私の命令を守って伯爵家にお金を払いきるまでは生かしてあげる。せいぜい残りの人生をおびえながら過ごすことね」
「そ、そんな……」
アルデラは部屋中の黒いモヤを見渡した。
「だって貴方、これまでにいったい何人、殺したの?」
返事はなかった。威厳がなくなり、すっかり小さくなってしまった公爵を見下ろしてアルデラは思った。
(ねぇ本当のアルデラ、これで少しはスッキリした? 貴女の無念は晴らせたかしら?)
もう用も済んだので、アルデラが書斎部屋から出ると、その後にブラッドとお姉ちゃんがついて来る。
廊下でバッタリと見知らぬ身なりの良い青年に出会った。青年は何か恐ろしいものを見てしまったかのように顔面蒼白だ。
アルデラが「貴方は誰?」と聞くと、青年ではなくお姉ちゃんが「公爵家の、令息」と教えてくれる。
「ああ、貴方がアルデラの兄?」
ビクリと兄は身体を震わせた。おそらく、書斎部屋の中で起こったことを見てしまったのだろう。
「これから公爵家の当主は私だけど、あの男が死んだら、表向きは貴方が公爵家を継ぎなさい。雑務は任せるわ」
兄は、コクコクと必死に頷いている。
「逆らったら……」
「逆らいません! アルデラ様!」
勢い良く頭を下げた兄は、父よりも物分かりが良さそうだ。
「だったら、人に手をあげたり、暴言を吐いたりするのはやめなさい。犯罪はもってのほかよ。これからは、領民に尽くし、富める者の義務を果たしなさい」
「はい、アルデラ様!」
兄の返事を聞いて、アルデラは満足そうに頷いた。
「さぁ、用事も終わったことだし、私達は帰りましょうか」
ブラッドが「はい」と答えアルデラの後に続いた。その後を、お姉ちゃんも無言でついて来てくれたので、アルデラは嬉しくてニッコリと微笑んだ。
「それは、私のように選ばれた者が持つものだ」
「選ばれた者、ね。この家の紋章が入っているし、もしかして、このブローチが、公爵家当主の証し?」
「だったらなんだ!?」
この公爵家は、過去に王家の危機を救ったとされる英雄の魔術師を先祖に持っている。
(確か、恐ろしい黒魔術師がこの国を滅ぼそうとしたときに、ご先祖様が退治して、逆に黒魔術を自分のものにしたのよね)
それ以降、公爵家の一族の中には、黒魔術が使える者が出てくるようになり、一族の中で、黒魔術が最も強いものが代々公爵家の当主に選ばれた。
そして、最も黒魔術が強いはずの現当主は、今、守ってくれるブローチを奪われ、実体化した黒い物体に襲われ叫んでいる。
「う、うわぁあ!?」
「現当主の黒魔術の実力がこの程度だったら、本当ならアルデラが当主になっていたんじゃないの?」
そう呟いて、アルデラは気がついた。
「ああ、そっか。これこそが、『公爵がずっと恐れてきたこと』だったのね」
自分より遥かに強い黒魔術の素質を持った娘が生まれ、殺そうとしても黒魔術に守られ殺せない。十五歳になっても黒魔術が発現せず安堵していたところに、術を使いこなせるようになった娘が戻って来てしまった。
アルデラはニタリと笑い、楽しそうに瞳を細めた。
「なるほど、今から私が公爵家の真の当主ってことね」
「違う! 当主は私だ! 『使い魔』どこだ!? 私を助けろ!」
「使い魔?」
アルデラが不思議に思っていると、どこからともなく全身黒ずくめの人物が現れた。
「来たか、使い魔!」
使い魔と呼ばれた人物が短剣を一振りすると、公爵を襲っていた黒い人型の物体が霧散する。
「へぇ、やるじゃない」
憎悪が実体化した物体を祓える武器は、神殿で祝福を受けたものだけだ。
「いいぞ使い魔、アイツらを早く殺せ!」
公爵に命令され、こちらを振り返った使い魔は、黒い仮面で顔を覆っていて性別すらわからない。素早く切りかかって来た使い魔の一撃をブラッドが剣で弾いた。
「アルデラ様、お下がりください!」
(『使い魔』って、もしかして、公爵家の当主に仕える忍者的な人? それとも、お金で雇われている暗殺者ってやつ?)
どちらにしろ強そうだ。アルデラが、いくら最強の黒魔術使いでも、黒魔術を発動させる前に倒されてしまったら負けてしまう。
(素早い敵は厄介だわ)
ブラッドの背後に隠れながら、緑の髪束から急いで髪を引き抜いた。そのとたんに、使い魔が高く宙を舞いブラッドを飛び越えた。
使い魔の短剣がアルデラの目の前に迫る。
(あ、死んだ……)
アルデラが死を覚悟した瞬間、ピタリと短剣が止まった。そして、仮面の下からくぐもった声が聞こえる。
「……どうして? ここに、戻って来たの?」
そのポツリポツリと話す、独特な話し方には聞き覚えがあった。
「え? もしかして、お姉ちゃん?」
両親に見捨てられたアルデラにいろいろと教えてくれた、どこの誰だかわからないお姉ちゃん。一本のキャンディを半分こして一緒に食べたお姉ちゃん。
公爵が「早く殺せ!」と叫び、使い魔はビクッと身体を動かせた。背後からブラッドに切りかかられ、使い魔は器用に避ける。
「使い魔、何をしている!? 当主の命令は絶対だろうが!?」
公爵の言葉を聞いてアルデラは微笑んだ。
「ああ、そういうこと?」
この『使い魔』と呼ばれる存在は、公爵家の当主に忠誠を誓っているらしい。
(だったら、簡単)
アルデラは手に持っていたブローチを使い魔に見えるように掲げた。
「お姉ちゃん、この家の本当の当主は私よ。私はこの家を出てから黒魔術が使えるようになったの。そこにいる男は、私の足元にも及ばない」
「そう、なの?」
「そうなの!」
使い魔が構えていた短剣を下ろすと「本当だ。命令に背いても、痛くない」と呟いた。その言葉は聞き捨てならない。
「お姉ちゃん、痛いことされてたの!?」
使い魔は袖をめくり右腕をこちらに見せた。そこには、ブローチと同じ琥珀色の石が肌に直接、埋め込まれていた。
「当主の命令は、絶対。背くと、この石がとても痛くなる」
アルデラが公爵を睨みつけると、公爵は狼狽えた。
「馬鹿め! そいつは人間ではないわ! 代々当主に仕えるために作られたバケモノだ!」
アルデラは「だったら何?」と言いながら、手に持っていた緑の髪を握りしめた。
「本当のバケモノは、アンタよ。お姉ちゃんが今まで味わった苦しみを、あの男にも」
緑の髪が黒い炎に包まれると、使い魔の腕から琥珀色の石がポロリと落ちた。そして、公爵の額へと飛んでいき、その肌へとめり込んでいく。
「ひっ! う、うわぁあああ!?」
絶叫が辺りに響いた。額を押さえながら床にうずくまった公爵をアルデラは見下ろす。
「これでアンタが、私の使い魔になったってことね?」
勢いよく顔を上げた公爵の顔からは血の気が引いていた。アルデラは黒髪を指でもてあそびながら、「お父さまぁ、おねがーい」と甘えた声を出す。
「今すぐ伯爵家に支払うはずだった持参金を払ってぇ。あと、これから毎年、今まで私に使うはずだったお金を伯爵家に振り込んでぇ。使用人はイジメないでぇ。暴力も暴言もダメよ、パパぁ」
「ふ、ふざけるなっ!」
怒りで唇を震わせている公爵に、アルデラは微笑みかけた。
「主に逆らう気?」
そのとたんに、額の石が輝き公爵は激痛に叫び、のたうち回った。
「い、痛い! や、やめろ!」
「やめろ?」
「やめてくれ! や、やめてください!」
公爵がそう叫ぶと、石の光は消えていく。公爵は涙を流しながら、荒い呼吸を繰り返した。
「この頭の悪い使い魔は、私の命令をちゃんと理解したかしら?」
公爵がこちらを睨みつけてきたので、アルデラはそっと公爵に顔を近づけた。
「そんなに生意気な態度だと、公爵夫人のように消しちゃうぞ」
パチンとウィンクをすると、公爵の顔から血の気が失せた。真っ白になった公爵は項垂れ小刻みに震えている。
「さぁ、主に敬意を払いなさい」
公爵は歯ぎしりをしながら、両手を強く握りしめた。
「……我が主、アルデラさ、ま」
「そうね。じゃあ、私の命令を守って伯爵家にお金を払いきるまでは生かしてあげる。せいぜい残りの人生をおびえながら過ごすことね」
「そ、そんな……」
アルデラは部屋中の黒いモヤを見渡した。
「だって貴方、これまでにいったい何人、殺したの?」
返事はなかった。威厳がなくなり、すっかり小さくなってしまった公爵を見下ろしてアルデラは思った。
(ねぇ本当のアルデラ、これで少しはスッキリした? 貴女の無念は晴らせたかしら?)
もう用も済んだので、アルデラが書斎部屋から出ると、その後にブラッドとお姉ちゃんがついて来る。
廊下でバッタリと見知らぬ身なりの良い青年に出会った。青年は何か恐ろしいものを見てしまったかのように顔面蒼白だ。
アルデラが「貴方は誰?」と聞くと、青年ではなくお姉ちゃんが「公爵家の、令息」と教えてくれる。
「ああ、貴方がアルデラの兄?」
ビクリと兄は身体を震わせた。おそらく、書斎部屋の中で起こったことを見てしまったのだろう。
「これから公爵家の当主は私だけど、あの男が死んだら、表向きは貴方が公爵家を継ぎなさい。雑務は任せるわ」
兄は、コクコクと必死に頷いている。
「逆らったら……」
「逆らいません! アルデラ様!」
勢い良く頭を下げた兄は、父よりも物分かりが良さそうだ。
「だったら、人に手をあげたり、暴言を吐いたりするのはやめなさい。犯罪はもってのほかよ。これからは、領民に尽くし、富める者の義務を果たしなさい」
「はい、アルデラ様!」
兄の返事を聞いて、アルデラは満足そうに頷いた。
「さぁ、用事も終わったことだし、私達は帰りましょうか」
ブラッドが「はい」と答えアルデラの後に続いた。その後を、お姉ちゃんも無言でついて来てくれたので、アルデラは嬉しくてニッコリと微笑んだ。